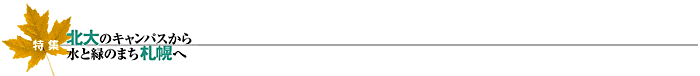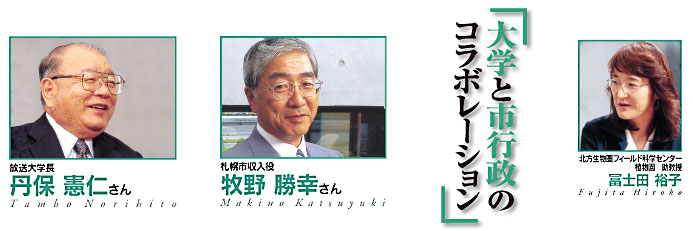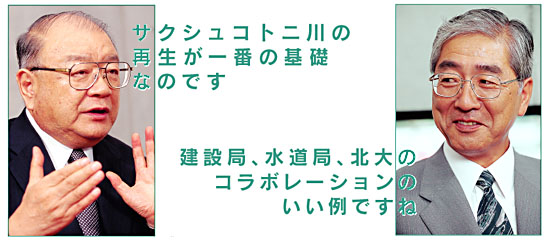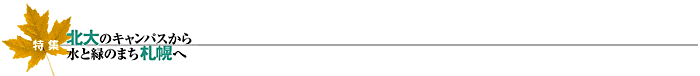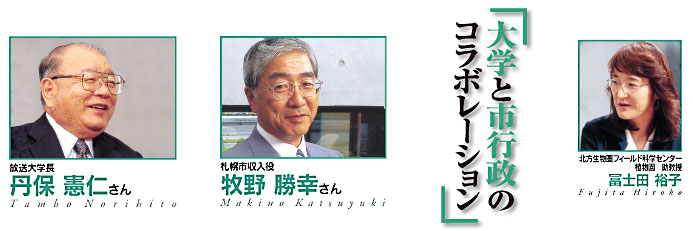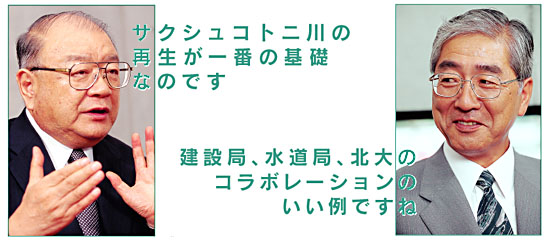|
冨士田 |
メムは涸れたのですから、川の再生には水源が大問題だったと思います。今回は市の協力があったのですね。 |
|
丹 保 |
昭和26年ころ、教養部の学生であったぼくはよく図書館の前で野球をやっていました。ボールが川に落ちると、川の中は水藻がいっぱいで、とるのが大変でした。そのころボールは貴重品でしたから。まだ自然の川がありました。
ぼくが教授になって、あなたが来たころは自然の川だった? |
|
牧 野 |
いえ、もう地下水を汲み上げてました。昭和40年ころです。 |
|
丹 保 |
もうなかったんだ。
じつは市では水環境再生の話が2つあって、ひとつは創成川の再生。札幌オリンピックで道路にしてしまった創成川沿いを戻そうというもので、建築系の人たちが一生懸命にやっています。しかしあれは街の景観に配慮したもので、自然とはほとんど関係ありません。札幌を水の都に戻すなら、北大に水を入れるのが効果的なのです。
桂前札幌市長はぼくの一期上で、彼が課長のころからの付き合いでしたので、相談するには最適でした。牧野さんのような卒業生も中枢部にたくさんいましたし、川を戻したいと話をしたら、北大OBだけでなく室蘭工大や東北大の人たちものってくれたのです。しかし市長には水利の決定権はありません。開発局に行ったら、そこでも「やりましょう」と言ってくれたのです。 |
|
冨士田 |
水利権には河川法のしばりなどいろいろな問題がありますね。牧野さんは、今回の水の供給の件でいろいろケアされたとうかがっています。 |
|
牧 野 |
きょうはサクシュコトニ川のお話ですが、じつは市にとってはサクシュコトニ川以外の北部地区の小河川も視野に入っています。先ほど先生のお話にもあった、以前メムから出て川になった地域だと思いますが、いまその地域の地下水位が下がっており、河川流量がどんどん減って夏には枯渇する状況です。市としても環境面から、もともと流れていた清流をなんとか取り戻したい、もしくは水質改善したいということで以前から取り組んではいたのです。
たまたま国の方から「水と緑のネットワーク」構想が出され、札幌でもその検討協議会で3案をつくっていました。ひとつは創成川ルート、もうひとつは雁来川ルート、そしてサクシュコトニ川ルートです。それぞれ創成川経由もしくは直接豊平川から水を上げ、それぞれの末端の小河川に流して本来の河川の姿に戻そうという考えです。先生からのご相談が、そんなわれわれの計画とタイミングが合ったのです。
もう一つの経緯として、環状通りエルムトンネルの問題がありました。これは以前から北大と協議をしていたもので、平成8年にお互いに基本的合意を取り付け、建設GOという状況にあった計画です。事務局や丹保先生、学内の委員会で詰めていたところ、構内のサクシュコトニ川の末端が市の準用河川で、トンネル工事と境をなしており、それなら、そこも整備するのだからということになりました。
事業にはそういうタイミングが大きなファクターになるのです。今回はまさにその一例だと思います。 |
|
丹 保 |
市の税金で北大だけ水をもらうわけにいきません。市全体のなかで考える必要があります。北大が札幌市民に大公園を提供しているといっても、それをお金に勘定することもできません。今回は市と大学のトップ、それを支える人たちの「あ・うん」の呼吸でうまくいったのでしょうね。 |
|
冨士田 |
今回、札幌市からいただく水は、藻岩浄水場できれいにした処理排水ですが、豊平川あるいは創成川から導水する計画もありましたね。 |
|
牧 野 |
先ほどの水と緑のネットワークでは、豊平川からいちど創成川に入れ、そこからサクシュコトニ川のルートに乗せることをまず考えました。ところが事業費の面で、多額になるのです。それと藻岩浄水場は昭和12年にできた創設の浄水場で、昭和30年、40年代に拡張した浄水場の改修工事が計画されていました。
最近では、水道の水質の問題も出ていました。返送水を原水に戻すのはどうか。たとえばクリプトスプリジウムなどの問題。返送するうちに悪い物質がだんだん濃縮・蓄積され、飲料水に悪さを及ぼすことを避けたいというのが一つです。さらに、それを原水に戻すにはポンプでかなりの動力が必要です。いまの処理能力と水質優先を考えると、返送ではなく、河川や下水など別の系統に流すことも考えましたが、下水は容量的に間に合いません。
市ではちょうど界川あたりのパイプの更新もやっており、界川であれば河川に放流する能力もあります。古くなって廃止するパイプを有効利用すれば街の中心部までつなげられます。オール札幌市として考えるとかなりの事業費軽減になり、界川の清流の復活にもなり、廃棄物も出ないとまさに一石三鳥だったのです。
これは建設局と水道局の共同事業でやりましたが、両方にとってひじょうに良かった。そして北大にとっても水源が得られる。三者のコラボレーションのいい例ですね。 |