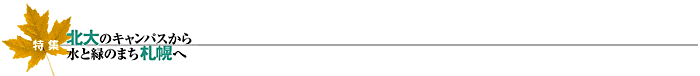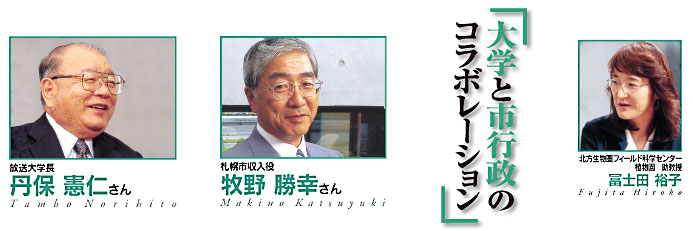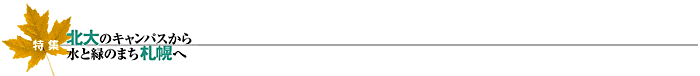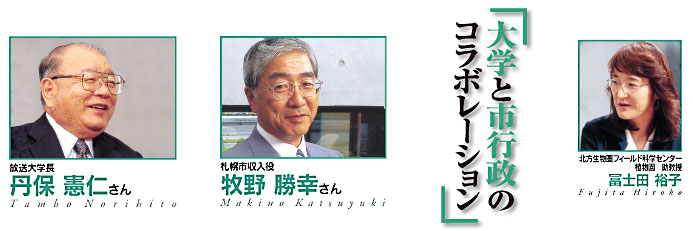|
牧 野 |
私は学生のとき、いかに勉強から逃げるかばかり考えていましたが、社会に出ると逆にいろんなことを経験していろいろなものに興味を持ち、もう一回勉強してみたいと思うことが何回かありました。そういう連中が大学に来れば、こんどは意欲を持って勉強するでしょうね。 |
|
丹 保 |
 自分のところの宣伝になりますが、放送大学はそういうシステムです。100人の教授と、客員を入れても800人の教員しかいませんから、それなりの講義しか出せませんが、これからは諸大学もそういう方向に動くと思います。 自分のところの宣伝になりますが、放送大学はそういうシステムです。100人の教授と、客員を入れても800人の教員しかいませんから、それなりの講義しか出せませんが、これからは諸大学もそういう方向に動くと思います。
ぼくはヨーロッパで500年、日本でいえば150年続いたこの大学のシステムは、あと15年もつかどうかとかなり懐疑的な考えをもっています。固定的な学部学科システムはなくなると思います。世の中が変化して多様な視野でものを見る必要が高まったからです。たとえば、工学も経営もわかる人材なんて、一回の卒業ではできません。最近では福祉や健康や安全など、人間のことを視野に入れない分野はほとんどありませんし。アメリカの大学では、学期ごとに3分の1ぐらいの学生が動くそうです。来学期は1,000人増えるとか。 |
|
冨士田 |
仕事も一度企業に入ったら定年までいる時代ではなくなりました。 |
 |
|
丹 保 |
企業自体もそんなに長くもつ時代ではない。新しい学部ができたり潰れたり。
こうなると何度も出たり入ったりできる学校にしなければなりません。しかも40歳とか50歳の人がぞろぞろ出たり入ったり。ボコボコと穴があいてもかまわないというシステムをやらざるをえない。もしかして、クラーク先生時代のユニバーサルな教育に戻るのかもしれません。そのとき、キャンパスは絶対的なよりどころとなります。自分の心が帰る家のようなものです。
20年ぐらい前の「近過去」に失われたキャンパスの再生には倍ぐらいの時間、ぼくは50年、半世紀だと思っていますが、努力さえしていれば戻ります。みんな気づいてきたし、ようやく引き金が引かれた感じです。
サクシュコトニ川の再生で緑と生態系をとりもどしたとき、北大は全国のどこにもないような素晴らしい大学になりますよ。 |
|
冨士田 |
本日は貴重なお話を伺うことができました。本当にお忙しい中ありがとうございました。 |