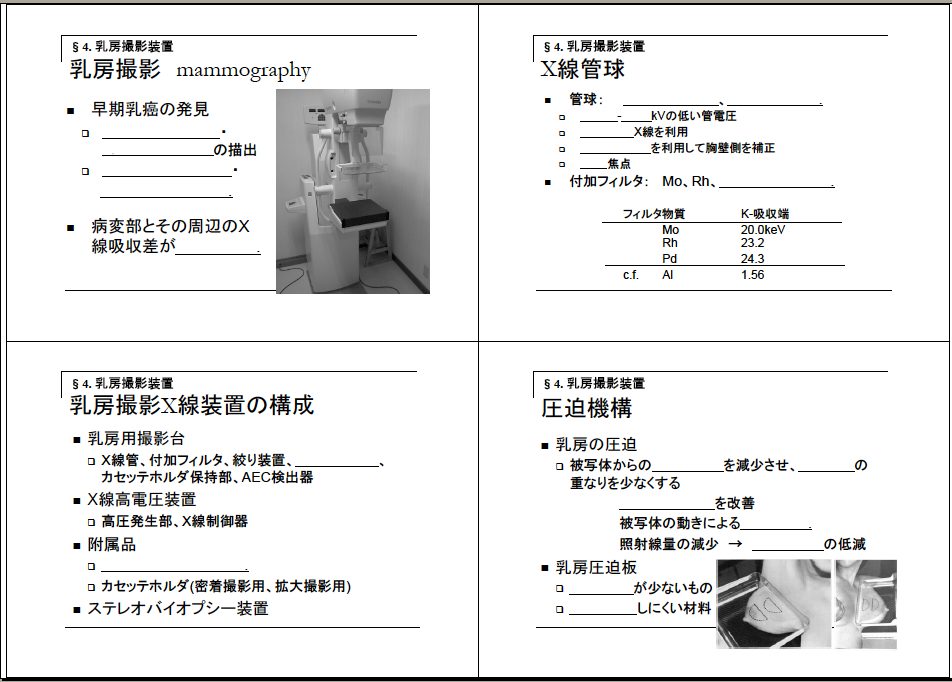
配付資料の例
放射線技術科学専攻では、卒業時に診療放射線技師免許取得し、医療機関や医療機器メーカへ就職する学生が多い。本科目では、診療放射線技師の道具と言ってもよいX線TV装置、マンモグラフィ装置やDSA装置など医療機関に十分に普及した画像診断機器について、電子工学、放射線物理学、画像情報学など既に学習した理工学の知識に基づき、患者の被曝管理、撮影技術と画像診断など臨床の視点を加えて、原理・構成・特性について講義している。また、本科目は思考中心というよりは、知識獲得中心の講義である。
この科目は、最先端の画像診断機器ではなく、十分に普及している画像診断機器の理論や特性について解説する講義であるため、学問的な鮮度で学生の興味を引くことは難しい。そこで、これらの機器に興味を感じてもらうために、私の臨床で失敗談や感じた問題点など機器ユーザーの視点から、画像診断機器と臨床業務との関連性を取り上げている。また、医用画像機器開発をとりあげた「プロジェクトX」を講義中に視聴し、画像診断機器の開発過程や最近の動向だけではなく、臨床の視点からの画像診断機器の研究開発の可能性についても触れている。
授業はパワーポイントを中心に進めている。以前はスクリーンに投影しているパワーポイントをそのまま講義資料として配布していたが、学生は「資料を持っている」という安心感からか、居眠りや内職など授業への集中力を欠いた学生が多かった。そこで、4枚のスライドをA4横として紙一杯に入れ、スライド毎のポイントを空欄とした講義資料を配布することとした(下図)。この資料は、このままでは講義資料としての役割はなさない。講義の際には、空欄のないパワーポイントをスクリーンに投影していることから、学生は配布資料の空欄にポイントを確認しながら板書し、その資料を完成することにより授業ノートを兼ねた講義資料が完成することになる
。本講義では、授業への積極的な参加を促すため、講義関連の発言には1日1点を限度として、テストの得点に加点している。教員も前回までの講義内容の確認や講義内容に関する関連事項など、講義中にできるだけ質問を投げかけるようにし、多くの学生に得点のチャンスが得られるように心がけている。発言も、誤答を歓迎し、挙手なしの自由発言としている。発言者の確認は自己申告制とし、講義当日のみに限定して発言者から学生番号と発言内容のメールを受け付けている。
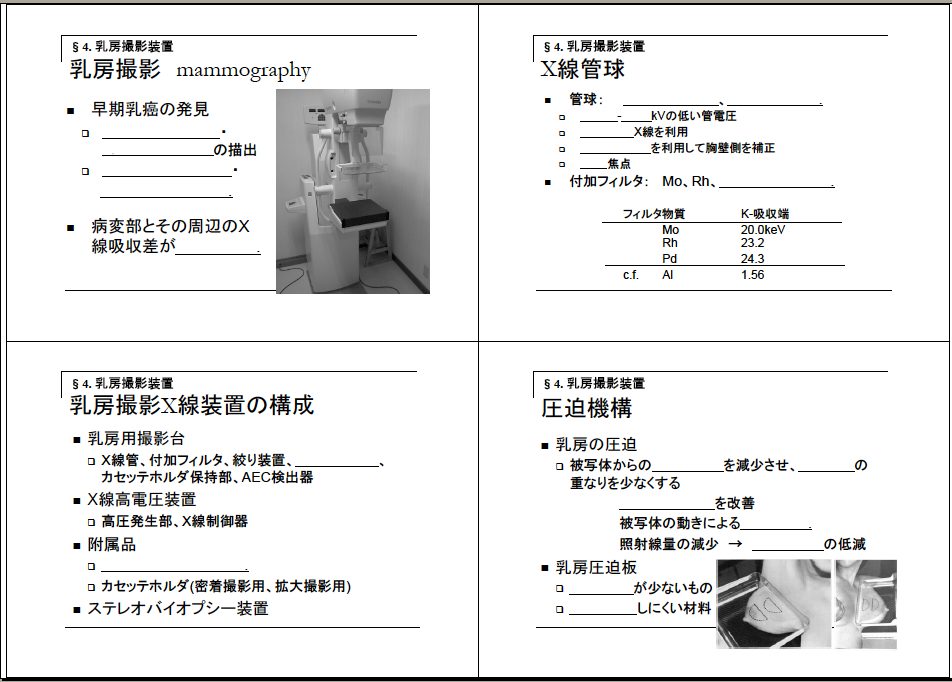
配付資料の例