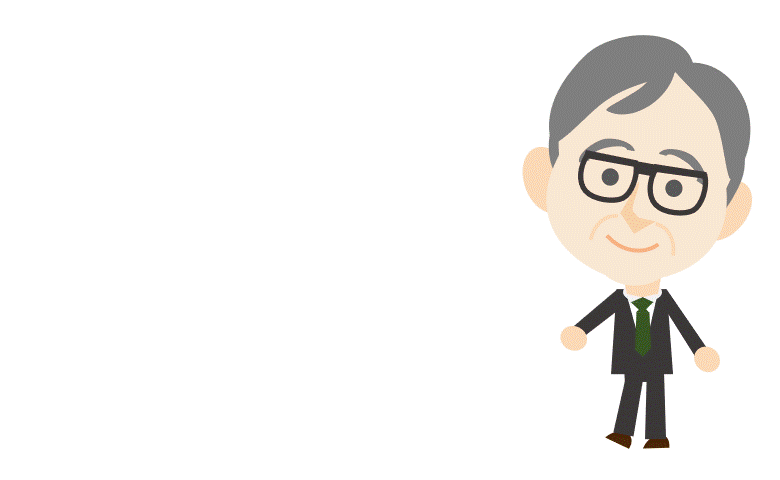オピニオン
Opinion
-
No.13「Flat Earthers and the rise of conspiracy theories」地球が平面だという説を改めて信じる人々がいる。Flat Eartherと呼ばれている人々である。同様に、今、地球で起こっている様々な現象に対して、科学的な検証を無視する動きがある。中には、政治的な権力、あるいは、ビジネスでの成功者と結びついて、私たちが築いてきたサイエンスを揺るがす事態も起こっている。
でも、私は言いたい・・「それでも地球は丸い」と。 -
No.12「The Second Challenge in 150 years」先端半導体のラピダスの北海道進出がきっかけになり、世界的なメディアに「北海道」や「千歳」の言葉をしばしば見かけるようになった。
アメリカも中国も、日本の半導体産業の再生に強い関心を持っている。
世界から注目されている、札幌農学校以来の北大の第二の挑戦、歯車はすでに回りだした。 -
No.11「A blue Nobel Prize week」ノーベル賞の受賞対象を見ると、科学の大きな転換点が見える。今年のノーベル賞のうち、物理学賞と化学賞は、いずれも、人工知能・AIに関連したものであった。特に、ノーベル化学賞については、AIを活用したたんぱく質の立体構造解析の業績に与えられた。
その内容は、この賞に相応しいものであり、文句なしの受賞であると敬意を表したい。しかし、科学に関わるものとして、大きな戸惑いも生まれた。それは、これまでのノーベル化学賞と異なり、業績の中核的な部分にAIによる解析があったことである。
その意味で、今年のノーベル賞は、大きな科学的業績がAIにより生まれる時代の幕開けを意味しているような気がする。 -
No.10「United States of America - An Enviable, chaotic superpower」1年ぶりに、大統領選間近のアメリカを訪問した。心なしかホームレスの人々が増えた。銃による不条理な犯罪を身近に感じ、根底にある人種差別の根深さ、そして、国際政治における課題も実感された。しかし、この30年に関して言えば、日米の力の差は、ますます拡大したように思われる。
今回もニューヨーク周辺の半導体産業の発展、そして、西海岸シリコンバレーの想像を超える発展を目の当たりにした。巨大な国土を持ち、現代の国家ビジョンの実験とも言えるような多様な人種が織りなす混沌とそこから生まれるエネルギーの大きさとダイナミズムを持つ国、アメリカにはいつも圧倒される。 -
No.9「Fundraising for our 150th anniversary—What an arduous and fascinating job!!」いろいろな学問を広く浅く知ることができるのは、辛いことの多い総長職に対する、数少ないご褒美である。ただ、金融やお金集めのスキルまで学ぶことになるとは思っていなかった。子供の頃から、倹約と質素こそが美徳と教わってきた人間が、総長になって、寄付金集めに奔走することになった。
-
No.8「The weak yen and universities-Japan's research in jeopardy」最近のドラマのタイトルを借りれば、「不適切にもほどがある」。この数年続いてきた円安は、限界を超えた感がある。いろいろな場面で、驚くようなことが起こっているが、日本の研究にとっても、言葉で言い尽くせないほどの悪影響が及んでいる。
国際空港で、カップヌードルをトランクいっぱいに詰め込んだ知り合いの研究者に出会った。海外での食費を節約するためである。涙が出た。国の力が衰えるということは、こういうことだ。 -
No.7「Oppenheimer and AI」今、日本でも、アカデミー賞を受賞した映画「オッペンハイマー」が公開されています。原子爆弾を開発したマンハッタン計画の中心になったオッペンハイマー博士の苦悩を描いています。日本でも賛否両論も含めて、メディアが論評し、広く、取り上げられています。
今、私たちは、人工知能AIという新しい技術を手に入れています。このAI技術が、世界を幸せにするか、あるいは、オッペンハイマー博士らが開発した核兵器のように、世界に対して大きなリスクをもたらすかは、今後の私たちの肩にかかっています。社会科学も含めて科学に関わる私たちには、自分たちの研究がどのように世界に影響を及ぼすかという想像力が必要です。 -
No.6「87th in the world」今年の大学共通試験では、英語の難易度が高かったことが話題になった。このレベルで平均点以上を取る学生が北大に入学してくる。にも拘わらず、日本人の英語能力は、世界でも87位と惨憺たるものである。かく言うこの総長も、中学一年生以来50年以上、英語を勉強してきたし、留学も2年半もしている。それでも、いまだに、rightとlightの発音に苦労するし、ParisとPalaceが聞き取れないのは、悲しい限りである。どうして、日本人は、かくも英語が上達しないのか…
-
No.5「The day the language barrier disappears」最近のAIの進歩は、私たちの日常を変えている。いろいろな場面でAIの威力を実感する。その代表が、異なる言語間のコミュニケーションである。最近の同時通訳AIは日々進歩しており、身近なところでは、学会発表や論文の在り方を根底から変えるものになるかもしれない。最近も海外出張で、日本語から北京語への同時通訳アプリを使って会議に参加したが、その高性能に驚愕した。学術の世界も言語の壁がほとんど障壁でなくなるsingularityに到達する日も近い。学術の世界を席巻してきた「英語」の意味が変容するかもしれない。
-
No.4「Learning from the great predecessors who struggled 150 years ago」日本では、modest(控えめ)であることが美徳とされてきました。ただ、国際社会やグローバルな場面では、modestは少しも格好良くありません。特に、若い学生や研究者は、不完全な英語でも構いません。機会を逃すことなく、世界の一流の学者にコンタクトして下さい。それは、若さの特権です。総長もあの程度の英語で頑張っていると、学生を勇気づけていることに気がついてほしいですよね…。
-
No.3「Education and Research as soft power」各種大学ランキングを見ると、日本の教育・研究力が低下していることは明らかです。世界がパンデミックから復帰しつつある今、日本の大学の国際化を進め、国力の源泉の一つである教育・研究力を再興させるために、私達は、自律的な国際戦略を立て、大学評価の国際基準に積極的に関わる必要があるのではないでしょうか。
-
No.2「An enigmatic photo from 1879.」クラーク先生の写真は有名ですが、開学当時の札幌農学校の米国人教師とご婦人の写真をご覧になったことはあるでしょうか。この写真、よく見ると不思議な発見がありますので、是非じっくりご覧ください。
-
No.1「Nostalgic visit to Massachusetts— All the light goes down to Massachusetts —」4月に本学の初代教頭クラーク博士が校長を務めたマサチューセッツ農科大学(現在のマサチューセッツ州立大学アマースト校)を訪ねました。今回のコラムでは、私のクラーク博士への思い、そして、マサチューセッツ州立大学アマースト校と北海道大学との他に類を見ない長い友好関係について書きました。是非お読み下さい。