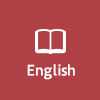北大人群像
ホーム > 活躍する卒業生 > 北大人群像 > 藤村 忠寿さん

大志を抱き、
名古屋から北海道へ
自由を謳歌し過ぎた
学生時代

僕が生まれ育った名古屋は、ある意味、閉鎖された大きなマチで、何となく進むべき道が決まっている感じがあったから、なるべく遠く離れたマチに行きたいと思っていました。北海道は、小学校の時、祖父と旅行をしたことがあって、その景色が忘れられなかった。「Boys be ambitious」という言葉にも惹かれましてね。「大志を抱くだけでいいの!?」っていう大雑把な目標がいいなと思って(笑)。
北大は、だだっ広くて、自由で、開拓精神のある学生が自分たちで何かを作り上げる――。そんなイメージでした。それで、北大を目指して受験したんだけど、見事に落ちて…。一年浪人して入学しました。
法学部を選んだのは、もともとクラスをまとめる役が好きで、小学校から高校まで学級委員長をやっていたので、その延長みたいな感覚で、町長とか市長とか政治家になりたいと思っていたから。

入学したら、ホントは文系のサークルに入ってチャラチャラしたかったんだけど、なぜか高校のラクビー部の先輩が何人もいて、待ち構えているような状況で、入学式の翌日には即入部。もう北大に入学したというより、ラグビー部に入学したような感覚なんですよね。ラグビーは中学時代から。多種多様な人間が集まって、その15人が集団としてゲームをするのが楽しくて。大学4年の時には、キャプテンもやりました。
入学当初は「初めて一人になれた!何時間でも好きなだけテレビを見ていいんだ!」っていう変な自由感がうれしかったな。
学生時代は、正直、ほとんど授業に出ていないんですよ。僕の場合、名古屋のいろんなしがらみから抜け出して北海道へやって来たので、北大は“自由に暮らせる場”だった。ラグビー部に入らなければ、もう少し勉強していたかもしれないけれど、結局、ラグビー部に入学したようなものだから。そこに集まってくる仲間は、東京からも大阪からも九州からもやってくる。全国各地からこの北海道の広大なイメージに憧れてやってきて、自由を謳歌し過ぎて、遊んでばっかりいた。もちろん、僕もその一人で、午後になると大学に行って、食堂でしゃべって、ラグビーの練習やって、夜は北18条か北24条あたりで飲むっていうのが、ほぼ毎日のルーティーン。3年生からはラグビー部のメンバーしか住んでいない、鍵もないような、家賃何千円のボロアパートに引っ越しちゃって。そうなると、まったくプライベートはなく、むさ苦しい男たちと一日中過ごす日々。だらだらしゃべって、ラグビーして、飯作って酒飲んで…。授業に出ていないから、留年もしちゃったけど、自由な空気を吸いまくっていた、人生で一番楽しい5年間だったんじゃないかな。
逆に、授業の思い出はないんだよね。試験の時、教室がわからないくらいだったから(笑)。
“自分が一番面白い
と思うこと”を原点に
大ヒット番組
「水曜どうでしょう」
を制作

HTB(北海道テレビ放送)に入社したのは、もともと留年時代、北大のラグビー部の先輩がHTBに何人か入社していて、「暇だったらバイトしないか?」って誘われたのがきっかけ。報道部のバイトで、カメラマンの助手を1年以上していました。テレビを見るのは最高に好きだったので、作るのも楽しそうだと思って。ちょうどバブル期だったから、10名以上の採用枠があり、俺もまんまと入社できた。
入社して報道部に配属希望を出していたんだけど、最初に配属されたのは東京支社の編成業務部。北海道で一生暮らそうと思っていたし、そもそも東京の企業が厳しそうで嫌だったから、この北海道のテレビ局に入社したのに、いきなり東京へ行けって言われて、それはどうだろう?と思いましたよ。
新入社員で東京へ行かされる人は僕以外いませんでしたからね。でも、会社としては、報道で1年以上バイト経験があるんだから、会社のことはだいたい分かっているだろうと。だったら一度、東京で厳しい目に遭ってこい、みたいなことだったんでしょうね。営業関連のお金の計算とかをやる仕事だったんですけど、社会って俺が思うようにはならないんだなぁと思いましたね。ずっと社内にいて視聴率とお金の計算をする仕事を5年間やり続けて、20代は仕事が楽しいって思ったことは一度もなかったな。

でも、その代わり、給料はちゃんともらえるわけで、車を買って、週末になれば、キャンプに行ったり、山登りしたり、カヌーに乗ったり…。東京って意外と遊びに行くには便利な場所で、北海道にいる時より、ものすごくアウトドアを満喫していました。稼いだ金はすべてプライベートにつぎ込んで、土日のために生きていたみたいな感じ。でも、後々「水曜どうでしょう」という番組で、カヌーに行ったり、旅をしたりするのは、この5年間で蓄積された経験が生かされたなと思います。
5年後、ようやく報道部に配属されると思ったら、今度は制作部へ。北海道のローカル局の制作部なんて、ドラマが作れるわけじゃないし、面白いバラエティを作っているわけでもないから、また夢も希望もないなぁと思っていたんだけど、自分で番組を任されることになって。僕らの頃は漫才ブームがあって、お笑い番組が全盛期。ドリフターズの「8時だョ!全員集合」をはじめ、小学生から大学時代まで、とにかくお笑い番組は、僕にとって“一番楽しいモノ”だった。だから、自分で番組を作るなら、「自分が一番面白いと思うことを作ってやろう!」と思って。それが「水曜どうでしょう」の原点ですね。
ずっと引退のない
ゲームのようなもの
これからも、
僕らの人生を見せていく

ローカル局では、有名なタレントさんを使えるわけではないから、そこらへんの人を使ってやろうと(笑)。それに、旅をしていて一番面白いのはアクシデントだから、なるべくアクシデントが起こる旅をして番組にしようと思って。実際にやってみると、初回から面白いものができた。
また、大泉洋が面白い男で、お互いバラエティ好きだからすごく波長も合って。しゃべることすべてが何か面白くて、1回目から面白いと思えるものができたから、これがゆくゆく全国に波及していくことが、不思議とは思わなかった。番組の知名度がどんどん上がって、いろんな人から「面白いね!」と言われるけど、「そうだよね!俺が一番面白いと思っているんだもん」って思う。それがずっと続いていて、今もそう思っていますよ。
そもそも面白いことって生み出せるものじゃないから、「水曜どうでしょう」では、旅に出て、面白いことが起きることをひたすら待つ。次はどこ行く?という企画も、単純に自分の感覚で行きたい場所を選んでいるだけ。温泉に行きたいなと思ったら「大泉君、痔だよね?温泉に行って治そうか!」みたいな。ただ、現場でとにかく楽しむ気持ちは大事ですよね。大泉君も「これテレビ番組じゃないよね?自分たちの旅を撮っているだけだよね?」って言いますけど、僕がやりたかったことが、まさにそれ。次々とヒットする企画を生み出して…なんて言われますけど、何も生み出してはいないんですよ。ただ行っているだけなんですから。

「水曜どうでしょう」は、タレント2人にディレクター2人が同行して男4人で旅をするという独自のスタイルから出来上がったもの。ラグビーと同じで、千差万別、年齢もバラバラの4人が集まって一つのチームを組み、「水曜どうでしょう」という舞台でいい戦い方ができた。だから、僕にとって番組のメンバーは、チームメイト、戦友、同志のような存在ですね。僕ら4人は、誰かが書いた脚本を演じていたわけではなく、自分たちが行った先々で、自分たちの言葉や表情で、面白さを作り出してきた。だから、「水曜どうでしょう」は、これからも僕らの人生を見せていくんだろうなと思っていて。大学生だった大泉洋が、今や日本のトップ俳優になったことも、番組の中身の一つだと思うし。「水曜どうでしょう」は、一生続く引退のないゲームですね。
学生という特権を
有意義に生かし
幅広い
コミュニケーションを!

今、北大生に向けて言いたいのは、あの広大なキャンパスでとにかくいろんな人と自由に交わってほしいということ。大学には、中学・高校と違って、さまざまな地域からやってくる千差万別な大勢の学生がいて、教授たちがいて、北大生だからこそ繋がれるOB・OGがいる。北大というコミュニティの中で、学生の立場を生かし、いろいろな人材と交流できるチャンスをどんどん生かしてほしいと思います。授業に出るだけの4年間にしたら、もったいない。僕はラグビー部の人脈の中で過ごしてきて、それができなかったから、振り返ると、なおさらそう思いますね。

北大に期待することは「Boys be ambitious」をもう一度、ですかね。東大、京大にどう勝つか、真正面から勝負するのではなく、北大に行くと、自由で大らか寛容で「大志を抱いているか?小さいことやってないか?」と問われる。僕が憧れたそんなイメージが、大学の全面からあふれているような存在であってほしいと願っています。

エグゼクティブ ディレクター
藤村 忠寿 さん
(1990年 法学部卒業)