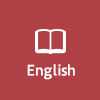北大人群像
ホーム > 活躍する卒業生 > 北大人群像 > 辻󠄀 秀一さん

バスケットボールを通じて
感動と仲間を得た
北大時代

高校は180人中60人が東京大学に行くような進学校でした。とても物理が好きで、将来は地球のためにエネルギー問題などを研究する仕事に就きたいと思い、高校3年の秋くらいまでは京都大学の理工学部を志望していました。ところが、無茶苦茶勉強が好きで勉強ができる周りの友達を見ていると、ずっと勉強を続けて原子力などのエネルギー問題について追及するということが、彼らほど好きじゃないかもしれないと思い、方向転換することに。うちは私で14代続く医者の家系で、親戚も医者ばかりという環境で育ったので、サラリーマンという発想はなく、第一志望だった物理工学から切り替えるならば、医者という道しか選択肢がなかったのです。
医学部を目指し、その中でも北大を選んだのは、大学でもバスケットボールを真剣にやりたいと思っていて、北大の医学部のバスケットボール部がいい戦績を残していると知ったから。札幌には行ったことは無かったのですが、明るいイメージを持っていたこと、苦手だった国語が二次試験になかったことなど、いろいろと総合的に判断して北大に決めました。

北大には、クラーク博士の「ボーイズ・ビー・アンビシャス」の有名な言葉はもちろん、大地があり、人も大らかというイメージを抱いていました。北海道に憧れて入学する学生が多いと思いますが、正直、私はそういった憧れはあまりなかったんですよ。1年目、入学してすぐ、5月のゴールデンウィークに雪が降った時には「うわぁ、ヤバいところに来ちゃったかも」と、さすがに衝撃を受けました(笑)
北大時代の思い出としては、2年目の東医体(東日本医科学生総合体育大会)で7連覇を達成した時、スタメンで出場できたことが一番印象的です。また、4年か5年の時に、全道大会で得点王争いに絡む活躍ができ、それを評価されて学生選抜に選ばれ、国体のチームと対戦したことも記憶に残っています。医学部のバスケ部は、大学構内の体育館が使えなかったので、小学校の体育館の一般開放を利用していたのですが、全学のバスケ部とも仲が良かったので、一緒に練習することも。振り返ると、バスケットを通じてつながりが広がっていった学生時代だったと思います。
スポーツドクターを
志したのは
「パッチ・アダムス」が
きっかけ

北大卒業後は、慶應義塾大学内科の入局試験を受け、研修内科医としてスタートしました。内科医としてようやく一人前になりかけた30歳頃、最も興味を持っていたのが膠原病リウマチでした。膠原病リウマチは全身疾患なので、人の体全体を見られると思い、先輩や父の助言もあって、その方向に進んでいました。
人生のターニングポイントは、実在の医師をロビン・ウィリアムズが演じた伝記映画「パッチ・アダムス」を見たことでした。この映画のテーマは「クオリティ・オブ・ライフ」。 “笑い”を通して人生の質を豊かにしていく主人公の姿を見て、自分の人生を振り返ると「今まで質について考えたことはなかったなぁ」と思いまして。人生の質、思考の質、行動の質…あらゆるところに質は存在しているもの。それならば、質を大事にする生き方を自分もしたいし、質の存在に気づいていない、つまり心の状態の大事さに気づいていない人がたくさんいるのではないかと思い、それを伝える仕事ができないかと漠然と考えるようになりました。とはいえ、パッチ・アダムスのようにピエロに扮して笑いの方向に転じるのはちょっと難しいかなと(笑)。では、パッチ・アダムスにとっての笑いは、私にとって何だろう?と考えた時に、自分自身が打ち込んできたスポーツに、何となくヒントがあるような気がしていました。

ちょうど当時、循環器内科の山崎元先生が、慶應大学の日吉キャンパスに慶大スポーツ医学研究センターという施設をつくるという話を聞き、「内科の先生がやるスポーツ医学って何なんだろう?」と思って、山崎先生を訪ねました。そこで、「アメリカでは健康医学の代表がスポーツ医学で、栄養、休養、運動などライフスタイルをマネージメントするのがスポーツドクターなんだよ。また、ヨーロッパでは、けがをした人を診るよりも、ピッチの上でプレイパフォーマンスに寄与していけるのがスポーツドクターなんだ」という話を聞き、私がそれまで抱いていたスポーツ医学、スポーツドクターの概念と全くかけ離れていたので、これは、今、私がとても関心のある「クオリティ・オブ・ライフ」につながっていくんじゃないかと思いました。そして、まずはスポーツ医学、スポーツドクターについてしっかり学ぼうと思い、山崎先生に弟子入りするような形で研究室に入り、無給からスタートし、働きながら勉強させていただきました。
慶大スポーツ医学研究センターに勤務して、最初にチームドクターにさせてもらったのがバスケ部でした。山崎先生から「辻󠄀君、バスケ大好きでしょう?」と言われ、ちょうど体育会バスケ部から要請があったと聞き「ぜひやらせて下さい!」と手を挙げました。まだ30歳で体も動く年齢だったので、学生たちと一緒に体育館のモップ拭きから始まり、バスケで汗を流しつつ、このチームに何が還元できるかを常に考えていました。栄養学からトレーニングの計画、ピーキング、超回復の原則まで、現場に役立つさまざまなスポーツ医学を、研究室で学んではチームに還元して、また学んでは還元するということを実践していました。そのうち、他の競技のチームからも依頼が増え、幅広くサポートするようになりました。

一方、私は、もともと膠原病リウマチ内科のステロイド骨粗鬆症の専門家で、当時、骨粗鬆症が世間で注目される中、骨粗鬆症のメカニズムと、ライフスタイル・マネージメントやスポーツの両方を研究している専門家はほかにいませんでした。私が骨粗鬆症の運動療法や運動と骨代謝などを同時に研究し始めると、面白いスポーツドクターがいると注目され、論文を書くことや学会で発表する機会がどんどん増えていきました。先日調べてみたら「骨粗鬆症の運動療法」をテーマにした論文は英文も含め80本ほど。これらの論文に取り組み、骨粗鬆症のサポートをしながら、大学の体育会ではコンディション・サポートをやっているうちに、ライフスタイル・マネージメントとスポーツ選手のコンディション・サポート、結局どちらも、最後に行きつくところは“メンタル”だなと気がついたんですね。
ライフスタイル・マネージメントをしていくためにも、もっと心の状態を知り、チームやアスリートたちがコンディションをより良くして活躍するためにも、メンタルをサポートするためにはどうしたらいいのだろう?と悩んでいたところ、知人からアメリカのメンタルトレーニング専門の応用スポーツ心理学会に誘われ、参加することに。そこで、スポーツ心理学を社会に応用するスペシャリストがたくさんいることを知り、これだ!と思いました。例えば、スポーツ心理学の先生がニューヨークのジュリアード音楽院でメンタルトレーニングをする一方、週末はオリンピック選手のメンタルトレーニングをしていたり、NBAでチームワークトレーニングしている先生が、ウォールストリートで金融企業のチームワークのトレーニングも手掛けていたり…。「これはすごい!ついに私のライフワークが見つかった!」と、とても感激しました。

しかし、日本ではまだメンタルや心理学というと、かなり怪しまれていた時代。医者仲間もスポーツ界も、まして一般社会では、宗教的なイメージとしてとらえられてしまう。メンタルはクオリティ・マネージメントに欠かせない実学という確信はあったのですが、周囲の反応はイマイチでした。
そこで起死回生の策として閃いたのが、当時大人気だったバスケットの漫画「SLAM DUNK」を題材にした、慶應の学生たちのメンタルトレーニング。いろいろなシチュエーションでこうするとチームワークが良くなるとか、こうやって集中力を増すんだとか、こうやって人間関係を築いていくんだとか、「SLAM DUNK」のさまざまなシーンを使ったメンタルトレーニングをやってみたんですね。すると、学生たちから「わかりやすい」とすごく好評で、二部のチームが一部に昇格するなど成果も出て、このレジュメが私の知らないところでどんどん広まり、なぜか早稲田の学生まで持っているという事態に(笑)。これはもう著作権侵害だなと思いまして、伝手の伝手を辿って作者の井上雄彦先生にコンタクトを取り、直接お会いして私の変遷と熱い思いをぶつけたところ、先生が「それは面白い。変わった医者だね」と了承して下さり、私の最初の著書「スラムダンク勝利学」が誕生しました。そして、これを機に人と社会の「クオリティ・オブ・ライフ」の向上を目指す株式会社エミネクロスを設立し、スポーツドクターとして独立しました。
揺らがず囚われず、
ご機嫌に!
独自の理論
「辻󠄀メソッド」

「スラムダンク勝利学」を書いた頃は、パフォーマンスの質に大きく影響を及ぼす心の“揺らぎ”をマネージメントし、安定的に自分らしさを発揮できるようにしていけばいいと考えていました。その後、さらに勉強していくうちに、“揺らぎ”をつくり出しているのは“囚われ”、つまり固定観念なんだと気づきまして。やはり人間が質を高めて生きていくためには、“揺らがず囚われず”という心の状態が重要であると、さまざまな学問から総合的に自分なりに考え、そういう概念に辿り着きました。この“揺らがず囚われず”をどう表現するとわかりやすいか考えている時に、シカゴ大学の行動学のミハイ・チクセントミハイ先生が「Flow」という言葉で表現していたんですね。これが“揺らがず囚われず”の表現にマッチするかもと思ったのですが、彼の「Flow」は無我夢中みたいな領域を意味するので、私はパッチ・アダムスの笑いのようにもっとみんなの日常に役立つ、新しい「Flow」を表現する言葉を模索しました。それが“機嫌よくやる”です。人は機嫌が悪い時、何かに囚われ、揺らいでいる状態なので、“機嫌よくやる”と表現すれば、誰にでもわかりやすいのではないかと。“機嫌よくやる”心の状態は、すべて脳がつくり上げるものなので、心の状態を整えるには、脳の訓練が重要と気づき、そこから今度は脳と心の関係を深く学び始めました。認知的な脳が僕らの揺らぎ、囚われ、不機嫌、ノンフロー、ストレスをつくり出しているから、その中で解決するのではなく、ヨガや瞑想、座禅の時に起こるマインドフルな脳の使い方を、それらに依存せず、思考の訓練をすることで、スポーツやビジネスの現場に生かせるのではないかと考えました。思考の訓練こそがメンタルトレーニングとして重要なのだと。どんな思考習慣があるのかが重要で、その思考習慣をライフスキルとして整理し、みんなに伝え、気づき意識していくことで、揺らぎや囚われが減り、自然体、ご機嫌な気分への切り替えが増えてきて、いろいろなことをやっていく上で質が高まる。それが私の独自の理論「辻󠄀メソッド」です。

海外ではほとんどの国でスポーツは文化の領域に位置づけられていますが、日本では体育という考えが、いまだに根付いているので、日本もスポーツが文化と思える国になってほしいと思います。だから、私の活動の根底は、スポーツは文化と意識・社会変革していくためのもので、行政やトッププロチームにコンサルしたり、スポーツの在り方をメッセージしていくことと、ライフスキルのメンタルトレーニングでご機嫌をつくっていく、その2つを大きな志として活動しています。この志だけは、ずっと持ち続けていきたいです。
北大時代に育まれた
感受性が
今の私のすべての
芽となった

私は東京生まれ、神奈川育ち。ずっと都会で過ごしてきました。私が北大に行って、今の自分の最も役立っていることは、感受性が育まれたことです。高校までは認知的に結果を出すために生きてきて、季節を感じることなどほとんどなかったのですが、北海道では季節の移ろいを当たり前に感じることができる。毎日、色が変化して、季節ごとに匂いも変わる。北大時代に四季の変化を敏感に受け止め、感受性を磨いていなかったら、きっと「パッチ・アダムス」を観ても、何も感じなかったかもしれません。心を大事にする、感じることを大事にする、今の私のすべての芽は、北大の6年間にあったと思っています。勉強はしなかったけど、スポーツに興じる環境があって、スポーツのすばらしさ、元気、感動、仲間、成長…いろいろなことを感じさせてもらい、私を大きく育ててくれた場でしたね。

辻󠄀 秀一さん
(1986年 医学部卒業)