ホーム > 大学案内 > 理事・副学長・副理事コラム > 令和6年度 > 第30回:清水 聖幸 副学長
第30回:清水 聖幸 副学長
半導体拠点形成推進本部の清水です。2023年10月、熊本大学からクロスアポイントメントで北海道大学に着任しました。私の使命は、熊本大学での経験を基に、北大における半導体分野の教育・研究体制をさらに強化することです。自己紹介とこれまでの仕事のエピソードを中心にお話しさせていただきます。
【出身から就職まで】
熊本大学に勤務して丸6年、大学院生時代の約4年間も含めると10年以上九州に住んでいますが、生まれは岐阜県高山市で、主な産業は、観光、農林業、木工業です。冬はかなりの積雪があり、高校時代はスノーモービルで通学する同級生もいました。そのため、私の原風景は、小学校の通学時の雪道と木材が積み上げられた製材所・木工所です。木の香りに触れると、強い郷愁を感じます。
大学・大学院では化学系を専攻し、炭素繊維の研究で学位を取りました。企業・大学・国研いずれでも就職可能な分野ですが、博士後期課程の時から声をかけていただいていた通産省工業技術院の資源環境技術総合研究所(現在の産業技術総合研究所)に28歳で就職し、新エネルギー開発を目的とするサンシャイン計画の末期の石炭の研究室に配属されました。「学位の炭素繊維と同じ黒もの系だから」という理由です。
【研究者としてのスタート】
当初「混ぜものの石炭に化学的なアプローチをしても、サイエンスと言えない」などと愚痴を言いながら、興味が湧かないまま研究を続けていました。そんな中、2年目のある日、酸性度が高く腐食性の高い薬品を使って、自ら設計して購入したばかりの反応装置の試運転を行っていたところ、装置から白煙が噴出しドラフト内が一面真っ白になりました。驚いて集まってきた研究者らに、薬品名とその量を伝えところ、大騒ぎとなりました。20分程で噴出はなくなりましたが、その日は、少しでも排気するためドラフトの運転を継続したまま帰宅しました。翌朝、「あれは夢ではなかったのか」と現場を見に行き、その次の日の朝も「やはりあれは夢ではなかったのか」と見に行きました。とてもショックを受けていました。
事故原因は、反応装置に耐酸性・耐腐食性のシール材が使用されていなかったことにあり、設計通りではなかったため、装置メーカーの責任も問えたのですが、安全上重要な確認を怠った私のミスでした。事故後、幹部や関係部署への報告と謝罪、事故報告書の作成を行いましたが、叱責も処分も受けることはありませんでした。逆に研究所からは、まとまった研究費が提供され、「安全に実験ができるよう設備を整えて研究を継続するように」と指示されました。不貞腐れている場合ではないと考え、挽回しようと研究に取り組みました。
事故から半年後、研究所の屋上を上回る高さのクレーン工事が始まり、私が事故を起こしたドラフトに関連する設備も含めて全て交換されることを知りました。それを聞いて、どれほどの損失と迷惑を研究所や国に与えたのかを痛感し、暗澹たる気持ちになりましたが、関係者の厚意、追加予算で準備した新設備、一緒に研究をしてくれる学生のことを考えると気持ちが落ち着き、もうしばらく頑張ろうと決心しました。
【北大との出会いと留学】
研究所に入って3年目の終わり、通産省サンシャイン計画が終了に近づく中、将来のため新たに固体超強酸の研究を始めることを目指しました。1990年代は、産業界で使われる触媒の半分以上は酸触媒でほとんどが液体だったため、安全や環境の面から固体化が求められていました。入所4年目に、提案書が採択され通産省の研究費を獲得する見込みが立ったのですが、細かな実験テクニック、研究の進め方について不安があり、国内留学制度を使って北大の服部英先生(当時工学部)の研究室に滞在しました。先生のご指導のもと、プロジェクトは順調に進み、企業からの資金提供や大学との共同研究、更には国費での海外留学の機会も得ることができました。辛抱強く研究指導をしてくださった服部英先生をはじめ北大の関係者への感謝もあり、今回クロアポのお話をいただいた時は、快諾しました。
留学先は、超強酸の研究所があり本分野のノーベル賞受賞者がいる南カルフォルニア大で、人脈形成とこの大学でしかできない固体超強酸の表面分析の技術を身に付けることが目的でした。半年が過ぎたころから研究は順調に進み、これはもっと成果が得られると思い、2年目の延長を考えていた矢先、研究所長から「4月から通産省工業技術院本院に行って欲しい、通産省からの指名である」との人事異動打診のメールを受けました。当時の研究所長は、事故を起こした時の企画室長で、本省対応していただいた上に、追加予算を提供してくれた方であり、断ることなどできませんでした。
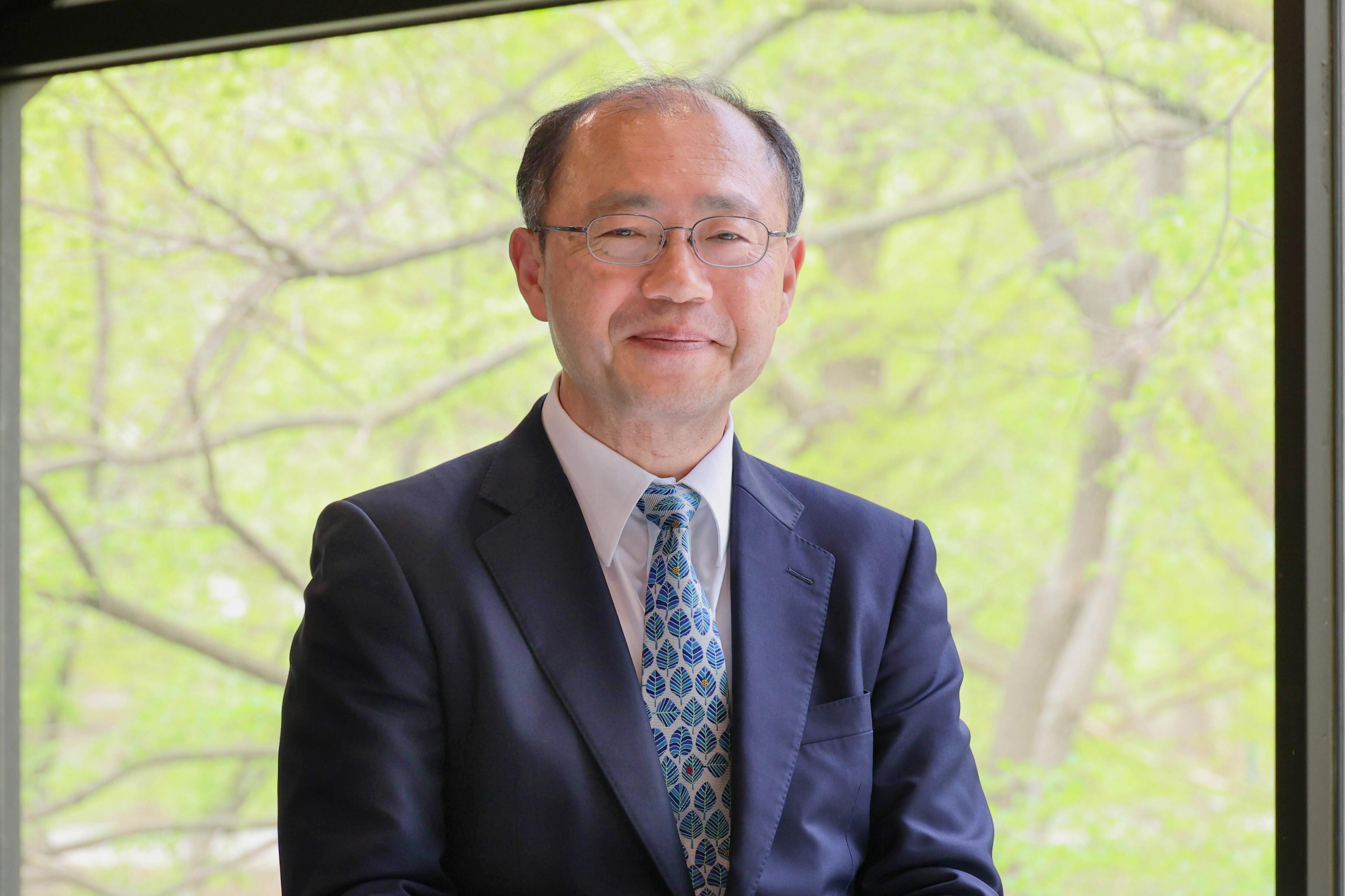
【霞ヶ関勤務】
2000年3月下旬に帰国し、4月から霞が関の通産省で勤務を開始しました。仕事の内容は、研究職員の人事、新法人産総研の人事制度とキャリアパスの構築という初めて経験するものでした。私は当時、任期付研究職員制度の廃止を模索したことがありました。1997年に発足したばかりの制度で廃止には至りませんでしたが、2022年に産総研では任期付研究職制度が廃止され、任期途中のものも含め全員が同日にパーマネント化されました。組織の目的に向きあえる人事制度という上で英断だと思います。
霞が関には、36歳から6年間在籍し、内閣府総合科学技術会議事務局、経産省研究開発課、エネ庁新エネルギー対策課で、調査官、参事官補佐、企画官として、科学技術政策、産業技術政策、新エネ技術政策に従事しましたが、その時の同僚とは、今でも繋がりがあります。
近年、官民交流が定着してきたためか、政府の管理職から、特定分野の専門知識や研究経験のある専門官(補佐級)や少し上のポジションの出向・兼業候補者の紹介を頼まれることがあります。候補者は、若手の大学教員・研究者、医員、URA等です。大学の現場を最短2年間離れることは簡単ではありませんが、「自分の専門や興味と近く、問題意識を持って取り組める部署と役職であれば積極的にやってみる」ことを勧めています。送り出す大学側の協力と家族の理解が必要ですが、政策の企画立案の体験、概算要求のプロセスや研究開発事業の審査プロセスへの理解、他大学・研究機関等の状況把握や人脈形成など、多くのメリットがあります。業務での優れた研究者との接触は、専門家としても成長の機会となることは言うまでもありません。組織としては、遠隔地の大学ほど、霞が関との繋がりを持つメリットは、更に大きいと考えています。
【岐阜県庁へ出向】
霞が関出向中に、次男も生まれ4人家族、40歳過ぎになっていました。連日遅い帰宅で、この生活をいつまで続けるのか、妻だけでなく私も疑問に思うようになり、プライベートな時間の取れる所への配置転換を申し出ました。
偶然と人事担当者の計らいもあり、経産省OBが知事になったばかりで私の出身地の岐阜県庁に出向することになりました。慌ただしく準備をしていたところ、岐阜県庁不正資金問題が発覚、それが自分にどれ程影響があるかわからないまま、2006年8月42歳の時、家族で岐阜に移り住みました。
仕事は、県庁の科学技術政策の推進と地元企業・農林水産業者等の支援、そして、農林水・工業・保健・環境・バイオの試験研究所などの約15の機関を統括することでしたが、最も期待されたのはプロジェクトを企画立案し、地元の大学・企業と一緒に国の事業を獲得し研究開発を実施すること、研究成果の事業化でした。
赴任してすぐに、不正資金問題は深刻であることがわかりました。多くの職員が調査の対象となり、マスコミや抗議電話への対応が続き、職員は精神的に疲れていました。2006年9月、岐阜県庁は信頼回復に向けた「岐阜県政再生プログラム」をまとめましたが、調査の結果、多くの職員が処分を受けるなど、県庁内部に大きな傷跡を残しました。
そのような重い空気の中で仕事を始めましたが、興味の湧く仕事が多くありました。これまでは研究も行政も主に工学系の内容でしたので、農林水産や医薬の分野は新鮮でした。特に、岐阜大学、名古屋大学等と一緒に産学官連携の研究プロジェクトを企画することは楽しく、この時の経験が大学に職を移すきっかけになっています。当時は、文科省・JST・経産省・農林水産省・環境省など、本当に多くの方にお世話になりました。
【熊本大学へ】
2016年4月の熊本地震からの復興のため、翌年4月、熊本大学は地域連携や産学連携などの部署を再編し、熊本創生推進機構を設置しました。私は、2009年11月産総研に復帰していましたが、いつか大学で勤務したいと思っていたため、同機構の教授に応募し、2018年9月54歳の時に採用されました。10月に副学長(産学連携)になり執行部メンバーの会議に出席した際、感銘を受けると同時に驚いたのは、教育は責任が重く大変な事業であり教職員は真摯に取り組んでいること、その割に運営費交付金は少なく一定割合で減り、経費負担に合わせて授業料を独自に改定できないことでした。国立大学法人は、経営面で大きなジレンマを抱えています。
熊本大学に移ってから、地域連携や産学連携に関するプロジェクトを進める中で、多くの課題と向き合いました。特に、着任前後から研究資金の使途に関する改善要望があり、大学がこれに対応することができなかった結果、重要な研究グループと複数のプロジェクト等を失うこととなりました。
この経験から、私は、研究資金を用いた教員の処遇改善や自由裁量予算の捻出、高時給のリサーチアシスタント制度の設立など、研究実施者のインセンティブ、研究環境の維持・改善に自由に使える資金活用の制度創設を目標にして、数年をかけ情報収集と制度作りに取り組みました。他の専門職と同様、大学研究者の産学連携における取り組みや知的貢献を処遇に反映することが、大学がイノベーションに取り組む上で最重要だと考えています。
【半導体産業の活況とTSMCの進出】
熊本大学では、半導体企業との共同研究の件数や金額は他分野を大きく上回っており、県内の半導体関連企業との連携は特に重要です。現在、熊本県には、主に修士課程修了者を対象とする新卒採用枠が約5百人あり、熊本大学からも約百人/年が就職していますが、着任したばかりの2018年は、半導体の組織や教育カリキュラムはなく、今とは全く異なりました。
赴任して1年経った2019年の夏、地元半導体企業の関係者から、「熊本大学から毎年多くの学生を採用しているが、半導体に関する知識が不足していてがっかりします」と言われたことがありました。「半導体産業は、熊本県の最大の業種(総工業出荷額の1/3)で多くの学生が就職しているのに、熊本大学は半導体を重視していない」と言われたと感じました。私は、半導体分野を強化する必要があると確信し、必要な体制と資金を国内外の先行例で調べたところ、最低でも半導体専門教員20名増、毎年6億円の予算が必要であることがわかりましたが、到底無理だと考え、具体的な行動には至りませんでした。
しかし、2021年9月、TSMC(台湾積体電路製造)の熊本進出決定の発表で、状況は一変します。半導体企業からの採用予定人数等の具体的な要望、熊本の半導体産業の今後の発展予測の中で、熊本大学はいち早く半導体分野の強化を決定しました。半導体カリキュラムの充実だけでなく、半導体の名称を冠した新学環や新学科創設を含む大学改革を行い、高専からの編入学定員増、大学院の学生定員大幅増を次々と決定し、半導体人材輩出数の大幅増を目指しています。
半導体企業の社員は、国際的なビジネスの中で国際水準の処遇を受けて活躍し、熊本は、かつての高度成長期のような状況の中にいます。熊本大学はこの高揚感の中の3年間、痛みを伴いながら、トップスピードで様々な改革を進めてきましたが、まだ道半ばです。教育と研究の成果を出し軌道に乗せるには、あと3~4年かかるでしょう。北海道でも、長期間かかることを覚悟して取り組む必要があると思います。

【北大】
北大における半導体分野の教育・研究体制の強化は、熊本大学に比べ難易度が高いと考えています。理由は、先端半導体産業という挑戦的な事業であること、また、北大には、先端半導体産業に対応できる高度半導体人材の輩出と高い研究力が求められているからです。熊本大学のように半導体企業から具体的な要望と大きな民間資金が提供されるのとは異なり、北大は、未踏の先端半導体産業において自ら仮説を立て、先を見据えて人材育成と研究開発を企画・実施して早急に軌道に乗せる必要があります。北大では、寳金総長のリーダーシップの下、多くの北大関係者が、学内だけでなく、企業や自治体を巻き込んで企画案をまとめて政府に提案中ですが、日本の大学として、これまで経験したことのない挑戦的な取り組みだと考えています。
私は、北海道の半導体分野の教育・研究体制では、道内外から北海道の大学・高専に入学してきた学生を大切に育て、道内の半導体企業で活躍する仕組みを構築することが重要と考えています。Rapidus株式会社をはじめとする先端半導体産業の成功と北海道に半導体企業が集積するかどうかは、北海道の高等教育機関が人材を提供し、その人材が中核となり半導体業界の国際的な水準の処遇を受け、国際的に活躍するようになることが必須条件だと考えています。
北大の半導体分野の教育・研究体制の強化とともに、その成果が地域に反映され、北海道が半導体とDX産業の重要拠点に発展するよう、力を尽くしていきたいと思います。

























