市立札幌開成中等教育学校のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業、本学の技術支援・設備共用コアステーション(CoSMOS)との連携で「課題研究スタートアップセミナー2024」が開催され、アカデミックファンタジスタとCoSMOSから計9名が講義を実施しました。本セミナーは、札幌開成中等教育学校SSHの3、4年生が課題研究に取り組むにあたり、最新の研究に関する話を聴講するとともに、研究者たちから研究やテーマについてアドバイスをもらう機会として実施しています。アカデミックファンタジスタは、2021年度からこのセミナーに参加協力しています。
講義を受講した生徒、および教員のみなさまから、講義レポートが届きましたのでご紹介します。
「健康に暮らすための室内環境とは」保健科学研究院 教授 池田敦子
参加生徒:3・4年生 32名
講義では、日本や札幌市に住む人びとの住宅を訪問して行ってきた健康調査の結果から、自宅環境と居住者の健康、特に湿気や換気、化学物質とシックハウス症候群やアレルギーとの関係について紹介していただきました。人々の健康を維持・増進するうえで、住宅改善や整備をどう進めたらよいか討論し、実際に簡単な室内環境測定を体験しました。生徒からは、「水や食べ物には気を付けていたが、空気は注目したことがなかった。今後は環境をよくするためにも意識を向けたい」、「考察の仕方、先生のプレゼンの進め方などから新しい学びがあった」などの振り返りがあり、今後の探究活動や学校生活のプレゼンにも活用できる方法を学んでいました。
 化学物質とシックハウス症候群やアレルギーとの関係について解説する池田教授
化学物質とシックハウス症候群やアレルギーとの関係について解説する池田教授「放射線・放射能の科学」工学研究院 教授 小崎 完
参加生徒:3・4年生 29名
北大の学生向けに開講している「北大対ゴジラ 映画『シン・ゴジラ』をもとに学ぶ放射線・放射能の科学」の講義内容をベースに、放射線や原子力の概念について講義を行っていただきました。福島第一原子力発電所の廃炉や放射性廃棄物の処理・処分に関する研究例なども分かりやすく解説していただき、放射線検出器で自然界の放射線を実際に測定する機会もありました。「今までの自分の課題研究とは違う切り口を見つけることができた」、「放射線が身近にあることが理解できた。匂いを数値化できる方法も放射線の応用についても探究を深めたい」などの振り返りがあり、今後の探究活動を進めていく上で視野を広げることができました。
 放射線や原子力の概念について講義を行う小崎教授
放射線や原子力の概念について講義を行う小崎教授「実験で読みとく国際政治と人の心のかかわり」公共政策学連携研究部 准教授 小浜祥子
参加生徒:3・4年生 35名
インターネット上で行う実験の手法を用いて、私たちの国際問題に対する考え方や意見が、外国政府の活動にどれほど影響されているかを明らかにする方法について講義を受けました。実験をどのように行い、何が分かるのかを詳しく解説していただき、実際に実験に参加して、データ収集や分析の様子を見せてもらいました。 受講した生徒からは、「態度の作られ方や内生性、確証バイアスなどの人の心理について視野が広がった」、「質問フォームを作成した時に、内生性を理解したつもりで対策方法までは考えていなかった」などの振り返りがあり、探究活動だけでなく、今後の生活でも応用できることに感銘を受けていました。
 生徒たちと対話をしながら講義を進める小浜准教授
生徒たちと対話をしながら講義を進める小浜准教授「環境と健康のデータサイエンス」環境健康科学研究教育センター 特任講師 田村菜穂美
参加生徒:3・4年生 37名
環境と子どもの健康について研究を行う田村さんは、エコチル調査・北海道スタディを中心に、環境と健康のデータサイエンスの世界を紹介してくれました。健康に関する情報に接すると出てくる「疫学」は、人々の健康を実現するために情報を集めて対策を考える学問、医学に特化したデータサイエンスだと解説しました。受講した生徒からは、「実験の時にデータを収集、解釈する方法や注意点を学んだ」「疫学とは何かを学んだ」「データの質を上げるためにチェックすること、具体例からみてデータを取ることの大切さについて知ることができた」などの感想があり、今後の探究活動を進めていく上でデータの取り扱いで結果の表現に違いが生まれることを学んでいました。
 疫学について解説する田村特任講師
疫学について解説する田村特任講師「ロボットとコンピュータによる化学空間探索」創成研究機構化学反応創成研究拠点 特任准教授 原渕 祐
参加生徒:3・4年生 35名
量子化学計算を用いた化学反応解析、化学情報学と人工知能(機械学習)を用いた化学反応の予測、自動合成装置(ロボット)を用いた有機合成実験の基礎から最先端についてわかりやすく講義をしていただきました。講義を受講した生徒からは、「計算だけで分子の構造がわかることがすごい」「化学反応を物理的に読み解くところが面白かった」などの振り返りがあり、今後の探究活動では、計算と他分野の研究を組み合わせて取り組んでいきたいという意識の変化が見られました。
 量子化学計算の基礎から最先端について解説する原渕特任准教授
量子化学計算の基礎から最先端について解説する原渕特任准教授「新種のウイルスを見つける」人獣共通感染症国際共同研究所 准教授 松野啓太
参加生徒:3・4年生 34名
獣医師でもある松野さんは、将来のウイルス感染症に備えるために、野生動物やマダニにひそむ未知のウイルスを探索し解析しています。北海道内でも誰も見つけたことのないウイルス、つまり新種のウイルスが見つかることもあると話す松野さんは、どのようにウイルスを見つけ、解析するかをわかりやすく紹介してくれました。受講した生徒からは、「ウイルスの研究は日常とかけ離れた話だったが、見えないところで人のために研究をしているのだと思った」、「新種かどうかの判断は、治療法の研究にも重要な役割を担っていると学んだ」などの振り返りがあり、今後の探究活動を進めていく上で実験方法の精度を上げることが大切だと学んでいました。
 ウイルスの模型を用い講義を行う松野准教授
ウイルスの模型を用い講義を行う松野准教授「対称性の破れた物質たち」理学研究院 教授 吉田紘行
参加生徒:3・4年生 33名
物質の中の電子の状態が「対称な状態」から「非対称な状態」に変わると現れる機能性について、磁石などを例に分かりやすく解説していただきました。物質の「非対称性」を駆動力としたピタゴラコースの動画を見て、物質の対称・非対称が生み出す現象から、新しい非対称物質を創造する面白さも紹介していただきました。生徒からは、「非対称や超電導について専門的な話を聞くことができた」、「非対称を利用・操作し機能性が生まれるという話は初めて聞き、身近な探究活動において活用できると思った」、「小さなものも非対称は機能性が高いことに驚いた」などの振り返りがあり、今後の探究活動を進めていく上で新たな視点を得ることができていました。
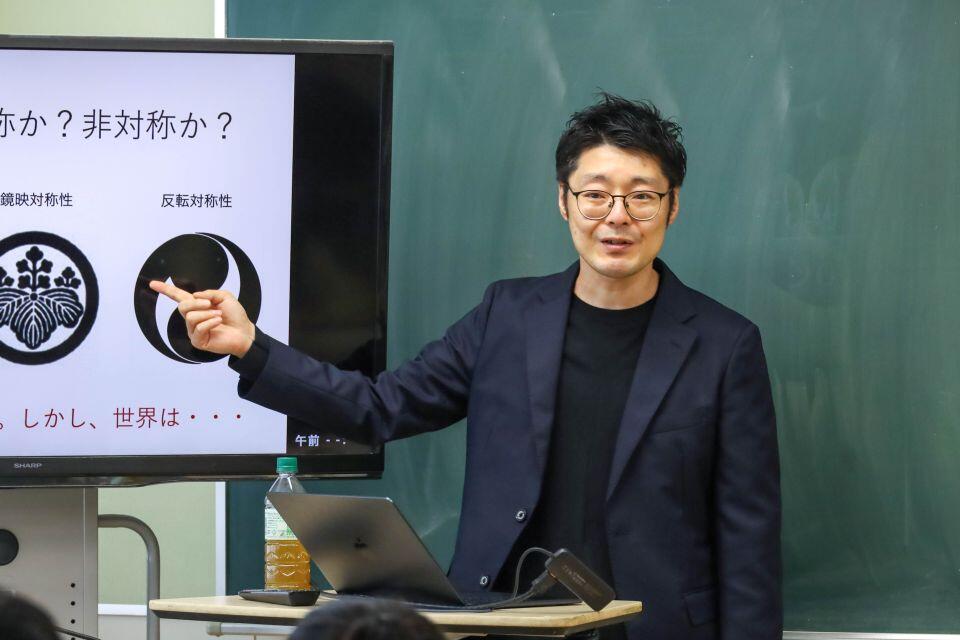 対称・非対称について解説する吉田教授
対称・非対称について解説する吉田教授「見えない光 "放射線" と向き合う」アイソトープ総合センター 技術専門職員 阿保憲史
参加生徒:3・4年生 29名
人間が認知できない光である放射線について、その正体や検出方法についてわかりやすく解説してくれた阿保さん。放射線に関する理解を深め、安全と危険の自己判断ができるレベルの理解と「適切な恐れ方」を身に着けるための講義をしてくれました。さらに、放射線を利用した研究や社会実装例が紹介され、受講した生徒からは、「放射線の長所と短所を理解できたので、聴講により見方が変わった」、「放射線の種類やそれぞれの影響など、知らなかった大切な知識を学ぶことができた」などの振り返りがあり、正確な知識の下に物事を判断することの大切さを学んでいました。
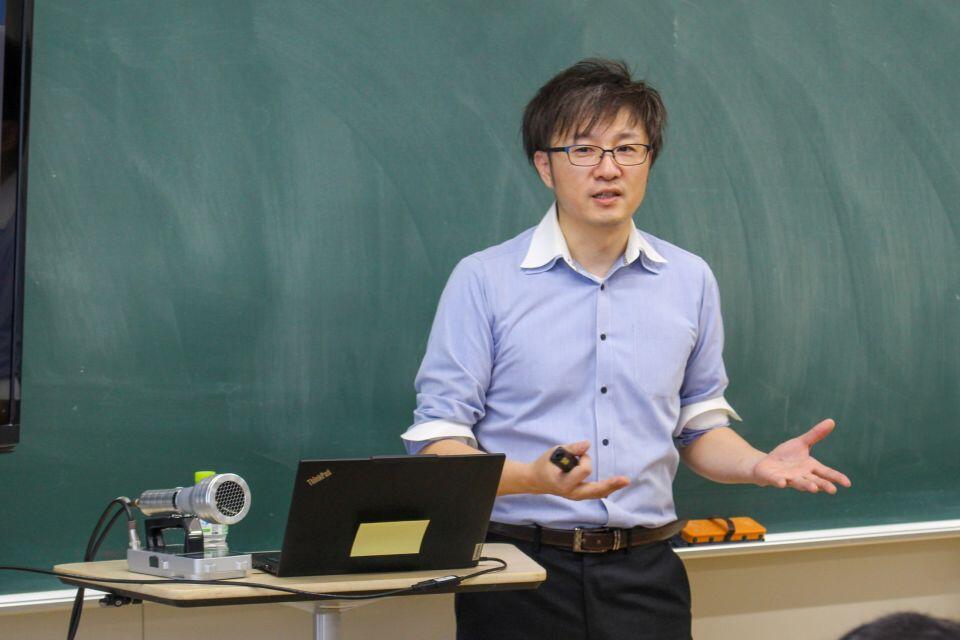 放射線の正体や検出方法について分かりやすく解説する阿保技術専門職員(提供:CoSMOS)
放射線の正体や検出方法について分かりやすく解説する阿保技術専門職員(提供:CoSMOS)「より良い研究のためのモノづくり、より良いモノづくりのための思考」電子科学研究所 技術専門職員 武井将志
参加生徒:3・4年生 39名
研究仮説を実証する際に、技術者として研究者のパートナーとなり、実証手段を開発し研究に貢献しているという武井さん。手段を開発すること自体も開発研究と定義され、研究支援を越えたモノづくりの醍醐味をお話されました。過去の開発製作を例に、技術の大切さや面白さを聞いた生徒からは、「モノづくりの上でプロセスと糸口が大切だと学んだ」、「なぜ研究を行うのか、どこで行うのかを明瞭にすることが大切」などの振り返りがありました。今後の探究活動を進めていく上で内容を細分化し、どの部分が課題になっているのかを明確にして解決への糸口をつかむことの大切さを学んでいました。
 技術の大切さや面白さを話す武井技術専門職員(提供:CoSMOS)
技術の大切さや面白さを話す武井技術専門職員(提供:CoSMOS)日時:2024年10月9日(水)13:10―14:00
会場:市立札幌開成中等教育学校
(広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門)
アカデミックファンタジスタとは?
北海道大学の研究者が知の最前線を出張講義や現場体験を通して高校生などに伝える事業、「アカデミックファンタジスタ(Academic Fantasista)」。内閣府が推進する「国民との科学・技術対話」の一環として、北海道新聞社の協力のもと2012年から継続的に実施しています。今年度は北海道の高校等を対象に29名の教員が講義を実施しています。2024年度の参加教員はこちら。
本サイトだけではなく、学内向け広報誌「北大時報」やFacebookでも講義レポートを随時更新していきます。合わせてぜひご覧ください。
Facebook
北大時報





