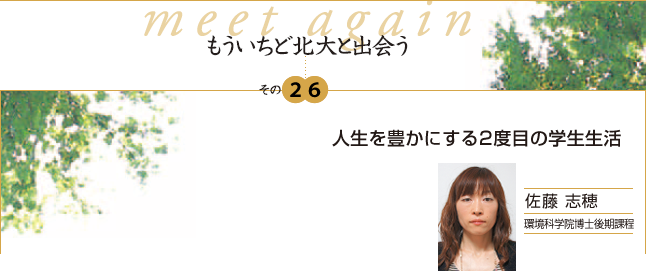環境科学院の玄関前で実践環境科学コース修士課程の学生たちと
(右から2番目が筆者)

星野リゾート・トマムで2012年7~9月に実施された「雲のしたマルシェ」にて、地元農産物の販売を通したコミュニケーション研究を実践
「勉強がしたい」。この思いが高じて、2011年10月から再び北大生になりました。北大は、十数年前に大学入学から大学院理学研究科化学専攻修士課程を修了するまで6年間過ごした学び舎。今、その当時とは異なる感覚で、学ぶことの楽しさを日々満喫しています。
今の自分と昔の学生時代とを比べると、学びに対する興味の持ち方が全く違います。昔を振り返ると、大学で一日中実験し講義を受ける生活に閉塞感すら覚えていました。結局、修士課程修了後は専門と全く異なる観光分野に就職。これが思いのほか楽しく、様々なことを学びました。特に「思いを持ち」「楽しく」取り組むことの大切さを学んだことで、自然と興味の向かう方向に突き進む強さが身につき、今に至っています。
そんな中、仕事を通じて出合ったのが環境科学院でした。観光が自然に与える影響に関心を持つようになり、環境保全の現状について伺うため訪問したのが最初です。そこで、久々に入った大学構内はとても新鮮で、対応して下さった教授の話は非常に面白く、いずれ北大で環境科学の勉強をしたいと考えるきっかけになりました。その後、鈴木章名誉教授がノーベル賞を受賞した年に、私は勤続10年を迎えました。その時は、自分の出身学科の遠い先輩の偉業に一人勝手に何か契機を感じたものです。程なく、また仕事を通じて環境科学院実践環境科学コースを知りました。この2度目の出合いが、再び北大で学ぶのは今だ、と決心させる最後の一押しとなりました。
入学して、改めて学生生活というのはとても贅沢で特別な時間だと感じます。興味のあることを学び、考え、追及していける。しかも、北大にはわからないことがあれば教えて下さる2000名もの教授がいる。色々な知識を得られることが本当に楽しく、興味があちこちに行きがちなのを抑える日々です。また、社会人を経験したことで、研究においても「実社会でどう役立つか」という視点で考えることができます。ここも、昔の学生時代とは大きく異なる面白い点です。
今は、環境科学院と連携協定を結んでいる星野リゾート・トマムで、地域コミュニケーションの研究をしています。「環境」という言葉は幅広い意味を含んでいますが、私は人が自分の周囲の状態や世界との関係性をどう認識するかという部分に注目しています。地域に住む人たちが、自然と共生しながら生き生きと楽しく過ごせる環境づくりにつながる研究をしていきたい、と思っています。
(さとう しほ)