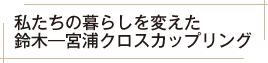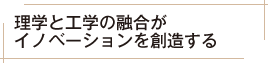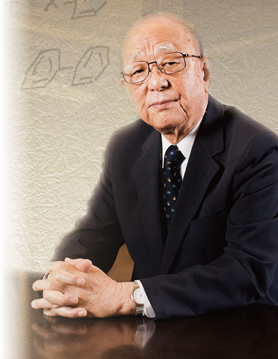
化学は、天然物の構造を解析するとともに、物質の相互作用や反応を利用することで人工的に物質を合成することを可能にしました。新たな物質は、産業技術などに応用され、私たちの暮らしに大きく関わっています。化学は、応用範囲の広い、社会を大きく変える力を持った学問なのです。
北海道大学における化学の研究は、鈴木章名誉教授のノーベル化学賞受賞をはじめとして多くの実績があり、世界の先端を走り続けています。また、理学と工学を融合して誕生した大学院総合化学院では、分野を横断した化学の研究と人材育成を行っています。
私たちの暮らしや社会を変える化学の研究とはどのようなものなのでしょうか。北大の化学の扉を開けてみましょう。


鈴木―宮浦クロスカップリングの活用

- 2010年、鈴木章名誉教授は、「鈴木―宮浦クロスカップリング」の開発によりノーベル化学賞を受賞しました。
- クロスカップリングは、構造が異なる二つの分子を結合させて、新しい分子を作る化学反応です。それまでも有機金属化合物を利用した反応が利用されていましたが、わずかな水にも反応してしまい、目的の化学反応を起こすには反応の環境をきびしく制御しなければなりませんでした。それに対して、有機ホウ素化合物を用いた鈴木―宮浦クロスカップリングは、[1]水に対して安定している[2]反応が容易に進行する[3]毒性がない[4]反応により得ることのできる物質の割合が高い[5]反応が高純度で進行する―といった特長があり、非常に利用しやすい反応です。取り扱いが容易で効率的に物質を合成できる画期的な化学反応なので、現在では、医薬品や農薬、液晶などの製造をはじめ、幅広く活用されています。

- このように社会で広く活用される研究ができた背景には、理学部で学び、工学部で研究をしてきた鈴木先生の経歴があります。
- 鈴木先生は、「理学が新しさを求める基礎研究を主としているのに対し、工学は実社会への貢献を重視するという点で異なっている。広く社会に役立つ研究をするには、二つの要素を兼ね備えていることが重要だ」と語っています。
- こうした基礎研究と実用性を合わせ持った研究への取り組みは、北大の総合化学院にも通じています。総合化学院は、理学と工学が融合した化学に特化した大学院として、国立大学のなかでは全国に先駆けて、2010年に設置されました。物質の探究を通し、未知の理論や法則を探究する理学と、理論を応用してより豊かな社会を創造する工学が日常的に交流する環境を整えることで、私たちの暮らしや社会を変える画期的な研究が生まれるのです。