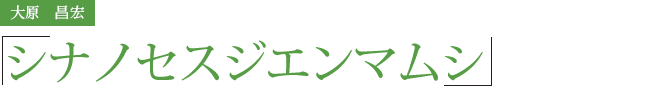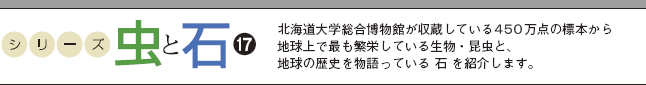
 クロクサアリの巣内に住む好蟻性甲虫エゾクサアリハネカクシ Pella kidaorum
クロクサアリの巣内に住む好蟻性甲虫エゾクサアリハネカクシ Pella kidaorum
 シナノセスジエンマムシ
シナノセスジエンマムシ
 クロクサアリLasius fuji
クロクサアリLasius fuji
1880年、著名な英国甲虫研究家ジョージ・ルイス(George Lewis)は、採集のため日本を縦断。2月17日、横浜に入国、北は小樽、南は熊本人吉に至り、翌年9月28日に横浜から出国。シナノセスジエンマムシ♭Onthophilus silvae♪は、信州諏訪湖で採集され、1884年にルイス自身により英国自然史学雑誌(Annals and Magazine of Natural History)に新種として記載された。標本はロンドン自然史博物館(旧大英博物館自然史部門)に所蔵されている。
◆
エンマムシ類は、通常、蛆(ハエの幼虫)の捕食者であるため、動植物腐敗物や獣糞などから採集される。日本の甲虫研究者や愛好家は、ひたすら動物の死骸や糞をひっくり返し、エンマムシ類の記録を蓄積してきた。しかし、シナノセスジエンマムシの記録は、神奈川の甲虫研究家平野幸彦が1986年に生態的な報告をするまで、ルイス以外は皆無であった。
◆
シナノセスジエンマムシは、クロクサアリの巣内に生息する好蟻性甲虫。体は泥を被り、人などの気配を感じると動かなくなる。平野は大木の根元にあるクロクサアリの巣前に座り、根気よく巣周辺を眺めていると、突然泥粒が動きだし、採集できることを報告した。以来、シナノセスジエンマムシは国内各県から報告がなされ、ある程度の大きさに成長したクロクサアリの巣には、普通に生息していることがわかってきた。北海道、本州、四国に分布。今年の農学部の学生実験で巣材を調査したところ、北大キャンパス内のクロクサアリの巣からも採集された。
◆
さて、約130年前、ルイスはどのようにしてシナノセスジエンマムシを採集したのであろうか。採集方法の記述は残されていないが、甲虫一般を研究、採集していたルイスは、好蟻性甲虫を採集するため、巣材の土を宿に持ち帰り丹念に調べるか、巣前に座り込み地面を睨んでいたに違いない。
◆
日本の自然史博物館は、欧州に100年遅れているといわれる。当時の英国博物学の見識や、大英博物館の大コレクション構築は、ルイスのようなナチュラリストたちの知恵と知識、そして努力によって支えられていたものなのであろう。欧州に追いつくには、建物や組織をそれなりにするばかりでなく、自然の価値と博物館の意義を理解しているナチュラリストが育たなければならない。大学博物館の教育にはそういう責務がある。
(総合博物館 おおはら まさひろ)