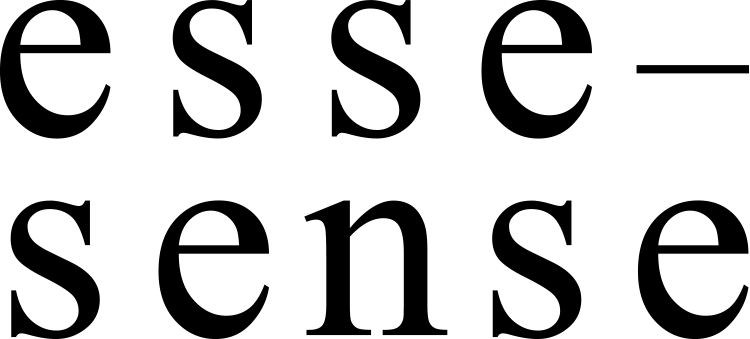リサーチタイムズとesse-sense(エッセンス)のコラボレーション記事をお届けします。esse-senseは、分野の垣根を超えた研究者たちのインタビュー記事を通して「あなたの未来を拓く」をコンセプトに、株式会社エッセンスが運営するウェブメディアです。本学の研究者たちにもスポットライトを当て、インタビュアーである西村勇哉氏(エッセンス 代表取締役)が、最先端の研究、そして研究者ならではのものの見方や捉え方に迫ります。ライターはヘメンディンガー綾氏が務めました。
今回インタビューした山内さんは、人類の進化と環境への適応を視座に入れながら人間の健康とは何かを追究する人類生態学者です。宇宙に関心があったという幼少期のエピソードから、途上国における水と衛生についての研究まで多岐にわたる研究内容を伺いました。
山内太郎
1993年東京大学医学部保健学科を卒業。同大学大学院医学系研究科国際保健学専攻修士課程に進学し、1998年に博士課程修了。オーストラリア国立大学太平洋アジア研究学院・研究員を経て、東京大学大学院医学系研究科にて助手を務める。2007年より北海道大学大学院保健科学研究院に異動し、2013年より現職(教授)。2018年5月から2022年3月まで総合地球環境学研究所・教授およびプロジェクト・リーダーを兼務(クロスアポイントメント)。2022年4月より北海道大学環境健康科学研究教育センター・センター長(兼務)。
天体観測が好きだった幼少期
西村 大学時代から国際保健の方向性で学ばれていたとのことですが、子どもの頃はどんなことに興味や関心がありましたか?
山内 子どもの頃は、宇宙に興味がありました。小さな望遠鏡で星や惑星を観測したり、プラネタリウムに行ったりするのが好きでした。それと同時に人間にも関心がありました。人体の不思議というか、身体機能や食と栄養、脳。そして人間がつくる社会にも興味がありました。そうしたことを研究する道があることは、中学生で知りました。
西村 中学の友人のお父さんやお母さんに研究者がいた、ということですか?
山内 はい。地元の公立の小学校から、くじ運がよくて国立の附属の中学校に入りました。ホームルームの時間で「将来何になりたいか?」みたいなことを各々話すことがあったのですが、その時に「おじいさんもお父さんも大学の先生なので、自分も研究者になりたい」と答えた同級生がいて驚きました。研究者という職業があることを知ったんです。子どもの頃は外洋航路の船医に憧れていたのですが、その時は手塚治虫の『ブラック・ジャック』の影響で「外科医になりたい」と答えたような記憶があります。
附属の高校に進学し、どちらかというと文系人間だったのですが、医者になるか、研究者を志すか...ということで、あまり深く考えずに理系に進み、自宅から徒歩で通える東大の理科二類に入学しました。その後、駒場から本郷へ移る進学振り分けの時に文転を目論んだり、食堂が美味しいという噂の農学部もいいなと悩んだのですが、これからは健康、ヘルスが重要だと思い、保健学科に進学しました。
そして、大学4年の時に卒業研究のために研究室に配属されることになり、「人類生態学」というなんだかよく分からないけれど興味深い名前の研究室に入りました。そこで教授になられたばかりの大塚柳太郎先生に出会いました。振り返ると、現在につながる運命的な出会いでした。
大塚先生は東大理学部人類学教室のご出身で、1960年代後期からパプアニューギニアでフィールドワークをされていました。そのご縁もあり、大学院修士課程でパプアニューギニアに調査研究に行くことになったんです。学部の卒業旅行で初めてパスポートを取得してアメリカ旅行をしたのですが、人生2回目の海外渡航がパプアニューギニアとなりました。特にアウトドアの経験もなく、楽器演奏や音楽制作などが趣味のインドア派だったのですが、自然の中で暮らしている社会で、言葉もわからない人たちと生活する異文化体験は鮮烈でした。
 パプアニューギニア高地人とともに
パプアニューギニア高地人とともに山内 いわゆる「伝統社会」でのフィールド調査では、日本とは大きく異なる食生活や日常生活の中で経験したことのないカルチャーショックを受けたり、怪我や体調不良も頻繁に起きました。何とか元気に帰国したのですが、数日後に高熱が出て倒れ、4ヶ月ほど長期入院しました。幸い、家の近くに感染症で有名な総合病院があり、パプアニューギニア帰りで高熱を出して苦しんでいるが原因不明ということで、隔離病室に入れられました。消毒をして防護服を着た母親が身の回りの世話をする以外は、小さな白黒の画面とインターフォンによるテレビ面会でした。その後、急性劇症A型肝炎と診断されました。食べ物や水による経口感染です。現地で食べた食事が原因だと思いますが、原因はよくわかりません。
4月になってようやく退院し、通院となりました。留年せずに修士課程を修了して早く博士課程に進みたかったので、医師はよい顔をしなかったですが、夏休みにパプアニューギニア高地を再訪しました。2回目の訪問ということもあり、現地で大歓迎してもらいました。人々とのコミュニケーションや調査研究にも自分なりに手応えを感じることができ、フィールドワークのおもしろさに目覚めました。なんとかデータをとって修士論文を書きあげました。やや大げさに言えば、この2回目の調査でフィールドワーカーというアイデンティティを確立しました。
 狩猟採集民と行動をともにし、獲物を秤量している様子
狩猟採集民と行動をともにし、獲物を秤量している様子西村 ニューギニアは、どういう点がおもしろかったんですか?
山内 なんでしょうね......。自分は東京生まれ東京育ちで、登山やキャンプなどアウトドア活動にはあまり縁がなかったのですが、ニューギニアでは毎日がサバイバルでした。日本では1年に一度起こるか起こらないかという事件が、毎日起こるんですよ。
西村 例えばどんなことですか?
山内 首都のスラム地区で調査しているときに借りていた部屋(家)が放火されたり......。1年にいっぺんどころか、普通は一生にいっぺんもないですね(笑)。
西村 確かにないかもしれない(笑)。
山内 修士課程では高地の農村で調査しましたが、博士課程では首都のいわゆるスラム地区で調査したんです。村で修士課程の2年間、計10ヶ月ほど暮らしたお陰で、現地の言葉も少し話せるようになりました。調査対象集団の文化や社会の基本についても一応わかっていたので、高地の母村からの移住者が住み着いた不法居住区でも受け入れてもらえたんです。けれども、やはり治安は相当悪くて、「お前は村のことを知っているし大丈夫だけど、警察も入れない危ないところだから先生や友人は連れてくるなよ」とよく言われました。
西村 年に1回あるかどうかということが毎日起こるのは楽しかったですか?
山内 はい、とてもエキサイティングでした。あと感じたのは、日本だと自分自身が「中年男性」とか「父親」とか「大学の先生」とか、いろいろと装飾されているじゃないですか。でもフィールドでは「ただのよそ者の男性」としか見られないんです。自分がいい人間だったら良く扱われるし、嫌なやつだったら相応に扱われる。ゼロから周りの世界を開拓していって人間関係をつくっていく。それが心地よくて楽しかったです。
しかし、異文化での生活を楽しむだけではダメで、データを取って論文を書かなきゃならないので、「熱い心と冷たい頭」といわれるように、常に冷静な部分を持っていないといけない。現地で生活しながらいろいろな出来事に出会ったり、珍しい経験をして感情が大きく揺さぶられるのですが、同時に頭の片隅でどうやってデータを取ったらいいかと冷静に考えている。そのバランスがおもしろい。調査に協力してくれる人と仲良くならないと調査はできないのですが、冷静にデータを取ることも忘れてはならないのが難しいところであり、フィールドワークの醍醐味でもあります。
 狩猟採集民の子どもを身長測定する山内さん
狩猟採集民の子どもを身長測定する山内さん西村 普通は行動を観察すると思うんですが、GPSのトラッキングをつけて調査されていますよね。被験者は数日間もよくつけてくれますね。
山内 小型軽量のGPSロガーだけでなく、胸ベルト式の心拍数モニターもつけてもらいました。本当は1週間連続データを取りたかったのですが、熱帯でかなり暑いので、胸ベルトの装着は連続3日間が限度でした。
そもそも人間が同じ人間を観察するのは、ある種おこがましいところがあります。また小規模なデータを元に論文を書いても、限定されたミクロな話になってしまいます。人類生態学のフィールド調査は、信頼関係を確立した、顔を知っている数少ない対象者についての「生態」について調査する。つまりさまざまなことを観察したり、測定したりします。
一方で、大勢の人々に質問紙を配って得られたデータを統計解析してある特定の集団の健康について特徴をまとめたり健康問題の要因を探ったりする、疫学と呼ばれる研究分野があります。少人数の深いフィールド調査と大規模なデータ解析はいわば「車の両輪」で両方とも必要で大切なんですよね。小集団を対象にしたミクロなフィールド調査を専門とする自分が、大学で統計学や疫学を教えているのをちょっと不思議に思うことがあります。
話を戻しますが、地域に密着した現地フィールド調査を学生時代から30年やってきました。しかし現地の人たちの生活や健康状態が向上するというような具体的な成果は見えなかった。こちらは調査に協力してもらって得られたデータで論文を書いて学位を取得したり、大学に就職できたりなど恩恵を得ているのですが、自分は彼らに何もお返しができていないことに気づいて愕然としました。
研究者は精緻なデータをとって論文を書けばいい、それを元にアクションするのはNGOとか地元の行政であってそれぞれ分業なんだ、と当時は納得していたのですが、北海道大学で自分の研究室を立ち上げて大学院生を指導するようになってから、論文を書くだけではなく、もっと直接的に現地にお返ししたいという思いが強くなりました。それが、最近取り組んでいるサニテーションの仕組みづくり、地元の住民やNGOや行政などさまざまなステークホルダーを巻き込む「超学際研究」につながっています。
人類進化と暮らしの関係から健康を考える
西村 山内先生は、人類進化と暮らしの関係を健康という視点で研究をなさっていますが、そこに関心を持たれた背景は何でしょう。
山内 ちょっと専門的になりますが、人類生態学は文字通り人類の生態学なので、研究の関心は生態、つまり人の環境適応にあります。一方で人類と生態を反対にした生態人類学という学問分野があって、フィールド調査においては人類生態学とほとんど違いがありません。生態人類学は人類学の一分野なので人類の進化に関心があるわけです。加えて、出身の東大人類生態学教室は医学部の国際保健学専攻に位置づけられていたので、「環境適応と人類進化から健康を考える」という研究スタンスになったのだと思います。今振り返ってみるとそのようにまとめられますが、当時はただ目の前のおもしろいテーマを夢中で追いかけていただけでした。
大学院生のときから、人類(現生人類=ホモ・サピエンス)の健康とは何かということに関心をもってきました。健康については、国際的にはWHO、国内では厚労省が定義しているのですが、それらは本当に正しいのだろうか。考えてみると、近年...古くても第二次大戦後の70年ぐらいの健康な人々をたくさん集めてデータを取った平均値的なものを健康の指標と考えているに過ぎないのではないか、と気づかされます。
例えば、日本人と西洋人では遺伝要因も環境要因も異なるので同じ基準は使えません。また、同じ日本人でも江戸時代の日本人に「1日にどのくらいエネルギー(カロリー)、たんぱく質、脂質を摂取しましょう」とか「1日に何歩歩きましょう」という現代日本人の健康基準を当てはめてもあまり意味があるとは思えません。身長や体重や身体能力、食事内容など現代日本人とは大きな違いがあるからです。人類学者として健康の原点、言い換えれば、ホモ・サピエンスの健康とはなんだろうということが研究の関心の根底にあります。
我々の祖先であるホモ・サピエンスがアフリカで誕生して、約1万数千年前に農耕が始まるまで、20万年〜30万年は狩猟採集生活が続きました。さらに、ホモ・サピエンスが誕生するに至るまでの人類の進化を含めて考えると、私たちの身体や精神・心は数百万年という途方もなく長い狩猟採集時代に適応していると考えられます。わずか1万年前に農耕が始まり、250年前に産業革命があり、今や情報革命の時代を迎えています。急激な社会の変化に身体や精神・心が追いついていないといえるのではないでしょうか。
「人類の健康とは何か」を知るためには、タイムマシンで数万年前に行って、狩猟採集をしている人々の食べ物の種類を調べ、食べている量を測ったり、心拍数計や加速度計を装着してもらって活動量を測定できればよいのですが、そんなことはできません。そこで飛行機に乗って1万マイルほど飛んでアフリカの熱帯雨林に暮らしている狩猟採集民に会いに行きます。
注意しなければならないのは、現代の狩猟採集民は1万年以上前の狩猟採集民と比べものにならないほど劣悪な環境に暮らしているということです。都市が拡大し、その周りには農地が広がっています。植物相も動物相も過去と現代では全然違います。とはいっても、やっぱり現代の狩猟採集民や狩猟採集社会に過去の狩猟採集民の生活や健康のヒントがあると考えています。このような、いわゆる伝統的な生活を色濃く残している社会で人類進化を考えながらライフスタイルと健康の調査研究を長年やってきました。
西村 まさに「目指す健康の姿って何だろうか」というのが研究の根底にあるんじゃないかと思っていました。健康って、寿命がどんどん延びればいいのかというのも、疑問です。これまで狩猟採集民の運動と健康について、時には握力といった細かいことも調査してデータとして残されていますね。狩猟採集民の生き方が、人類本来のあり方だということがデータをとったことでわかる事例を教えてください。
山内 狩猟採集民の生き方、ライフスタイルはどれも現代社会で暮らしている自分にとってはおもしろいのですが、これまでの調査で特に興味深かったのは育児です。狩猟採集民の乳児を観察して、30秒単位のチェックリストで観察したところ、1日あたり1人の乳児を育児する人数が母親を入れて16.8人もいたのです。育児の定義ですが、ちょっと体をなでるとか、抱っこするとか、目(手)の届く範囲に乳児を置いておくということも含まれます。日本だったら1日母親のみ(1.0人)、父親も乳児に関わって(2.0人)となります。育児に携わる人数の桁が違います。日本でも昔は地域社会で子どもを見ていたと言われますが、そもそも人類の育児は、周囲の大人や子どもが大勢関わるものだったと思うのです。
また、子どもの運動量、とくに歩数にも驚かされました。年齢や性別で異なりますが、子どもの1日の歩数の国際推奨値は大体1万2〜3千歩といわれています。狩猟採集民の子どもたちに歩数計が内蔵された加速度計をつけて測ってみたところ、1日平均2万歩を超えていたんです。現代の基準は全然甘いというか、足りないのではないかと疑ってしまいます。とはいっても、現代社会の子どもたちは学校で何時間も座って授業を受けなければならないので、1日2万歩歩くようなライフスタイルはそもそも難しいですね。1万年以上前の狩猟採集社会と現代の狩猟採集社会は物理的環境も社会的環境も大きく異なっているのですが、人類の健康を考える上で重要なヒントになるのではないかと考えています。
人類の健康に欠かせないものは何か
西村 山内先生は狩猟採集民の身体とフィットネスについて研究されていますが、その報告書を読んでいると、体を動かすことの意味は「本来これぐらい動いているから、動きましょう」ということで、その「本来」に結構近いのがこの狩猟採集民の身体なのかなと。彼らは狩猟のために体を動かさなくてはいけないから、1日1万歩歩くことはしないですよね。
山内 そうですね。意識せずに自然にやっていますよね。高い身体活動をともなうライフスタイルを人類は何十万年も繰り返してきて、それに適応してきたので、そこに人間の健康の本質があると思います。
ライフスタイルに加えて教育も現代社会とかなり違っていて興味深いです。狩猟採集民の定住集落に学校がある場合もありますが、キリスト教の教会が運営しているミッションスクールのような例外的なものを除いて、あまり機能していないようです。子どもたちは、朝起きたら男の子はお父さんやお兄さん、おじさんなど男性と一緒に森へ入って狩猟する。女の子もお母さんやお姉さん、おばさんと一緒に森に入って狩猟採集する。そこで大人の真似をしながら「遊んでいる」と従来の研究では言われていました。一般的な社会だと「こういうふうに弓を持ってこうやってこうやるんだ」と子どもに教えそうなものですが、狩猟採集民の大人は教えない。子どもは見よう見まねで勝手にやっているのですが、だんだん熟達して、結構獲物をたくさんとっていることが分かりました。
研究室の大学院生の調査では、子どもたちによる狩猟によって、エネルギー(カロリー)やたんぱく質として一家に必要な量の3割をとっていることがわかりました。子どもは体が小さいので子どもたちがとってくる獲物で、子どもたち自身が必要とするエネルギー量の8割を満たしているんです。こうなるともう遊びではなくて立派な狩猟活動といったほうがいいかもしれません。
西村 すごい。
山内 でも必要な栄養の8割しか賄えないということは、子どもたちは自身の狩猟活動だけでは生きていけない。残る2割については、当然ながら大人が子どもに食料を分配しているということです。狩猟採集民は森の中で自然と共生して生きていて、平等社会であると言われますが、私たちは、実際に測ってみて、本当に何%なんだということを数量データで明らかにするというマニアックなことをやっています。
西村 狩猟採集民のライフスタイルと健康が紐付いたとしても、都市に住む人に同じことを求めても仕方がない、ということも報告書などで書かれていました。ではそこからどう学んだり、取り込んだりすればいいのかを知りたいと思いました。
山内 ライフスタイルや生活環境が異なるので、狩猟採集民のライフスタイルを現代人がまねるのは難しいです。狩猟採集社会で生活しながら思ったことは、エネルギーや栄養素をこのくらいとりましょうとか、もっと運動しましょうとか、そういうことはもちろん重要なのですが、それだけではなく、現代社会は、自然とのコミュニケーションが足りないのではないかと気になりました。現代社会の健康問題である生活習慣病は、単に栄養や運動の問題だけではなく、自然との関係が希薄になっていることにも原因があるのではないかと。じゃあ、何ができるかと言うと、アイデアがそれほどなくて。ありきたりですが、キャンプとか、野外活動するとか...。ぜひ良い案を教えて欲しいです。
科学的な視点では、スポーツやさまざまな運動を行って、運動量や消費エネルギーを増やせばよいということになるのですが、スポーツなどの構造化された運動ではなく、構造化されていない動きが大事だと思います。アフリカの狩猟採集民の子どもたちは、森でアフリカオニネズミ(ジャイアントラット)の巣穴の前で火を焚いて煙であぶり出して捕まえたり、木の上に見つけた蜂の巣をとるために、交代で小さな手斧で木を切り倒したり、小川を泥でせき止めて水を掻い出して魚を獲ったり。こうした活動をチームプレーでやるんです。仲間と一緒に森で獲物を捕るという活動は、現代社会ではとても難しいと思いますが、同じようにカロリーを消費するとしても、野球やサッカーやテニスみたいな構造化された動きよりは、鬼ごっこや追いかけっこのような不定形で構造化されていない遊びを屋外ですることに意味があるように思います。
西村 今のお話を伺っていて思い出したのが、先日東大の演習林の齋藤暖生先生に伺ったお話です。今キャンプに行く人は増えているんだけど、キャンプにかかる費用も増えてキャンプ格差が広がっている。教育熱心で、お金をかけられる家族はキャンプに行くけれど、そうじゃない人は締め出されて、アクセスできる森が減っている現状があるとおっしゃっていました。キャンプをするだけではなくて、どうやって自然にフリーアクセスな環境をつくるか。例えば北欧では自然へのアクセス権が権利として存在していますが、これがすごくおもしろいなと思っています。海に飛び込めるとか、そういうのがすごく大事ですよね。
山内 その通りです。自然とのコミュニケーションが増えると周囲の環境に対する意識が高まり、ひいては地球環境問題ともつながってくると思うんですよね。ナチュラル・リレーテッドネス(Natural Relatedness、自然へのつながり度)という概念があって、人の健康やウェルビーイングと関係しているといわれています。自然へのつながりを高めていくためには自然環境をどうやって保全して、人々がアクセスできる場をどうつくっていくかということも重要です。自然に対する意識と行動の変化、そして環境保全。これら全てが一体となって健康やウェルビーイングにつながっていのだと思います。
西村 先ほどの斎藤先生は山梨の富士演習林で、地域住民の方々とキノコの採集に関する知識収集をされているんです。自然にアクセスできても、そこで何をすればいいのかがわからないと行かなくなる。だから、いかに自然に対しての知識を残して伝えていくのかが大事なんだとおっしゃっていました。先ほどの子どもたちがネズミをとる話を伺っていても、子どもたちもすごい知識を持っていて、それが伝承されているんだなと思いました。
山内 自然に対する知識の豊富さにはいつも驚かされます。子どもたちがどのようにして自然の知識を学んでいくのか興味深いです。狩猟採集民の子どもたちは、森で大人たちがやっていることをワクワクして見ていて、見様見真似でやってみる。最初は下手でも、だんだんコツを掴んでいく。同じゴールに到達するとしても自分で発見や工夫しながらやっていくのと、教えられるのとでは全然違うと思うんです。失敗を含めてゴールまでのプロセスを体験するのがベストな教育だと感じます。逆説的ですが、教えないことが教育の本質なのかもしれませんね。
他に思うのは、年齢が多様なグループで年上の子どもや年下の子どもと一緒に遊ぶのが、最近の子どもは少ないかもしれませんね。自分が子どもの頃は、近所の子どもたちで一緒に遊ぶ場合は、当然自分より小さい子もいれば、お兄さんもいて、自然に社会性を身に着けたり、リーダーシップを学ぶことができた。また、弱い人たちへの配慮も遊びを通じて自然に学んだように思います。現代の子どもは、そのような機会が非常に減っているのではないかと思います。
西村 うちは4歳、6歳、9歳の子どもがいるんですが、4歳の子が9歳の子についていけなくて喧嘩することがあります。狩猟採集民の子どもも、誰か大人が引き上げてあげるのではなくて、頑張ってついていくのでしょうか。
山内 小さい子どももがんばってついていこうとするのですが、年長の子どもが引き上げてあげることもあります。戦前の日本の農村などで、子どもが弟や妹をおんぶしている情景を写真で見たりしますが、まさにそういう感じで年齢が上の子は小さな子どもをよく世話をします。大人が手取り足取り教えなくても、子どもの社会の中で、子ども同士で教え合ったり助け合ったりしているのでしょうね。
西村 怪我をすることもありそうですね。
山内 怪我はしょっちゅうします。どうしても子どもたちで手に負えなくなった時、はじめて大人が介入するんですね。森の中で起こることは、狩猟採集民の大人も子どものころに全部経験していて、例えば自分も同じような怪我をして血を出したりしていて、このくらいなら大丈夫だみたいな肌感覚でわかっているんだと思います。子どもたちを放任しているように見えて、大人なりの「これなら大丈夫」という判断基準があるんじゃないかと。
西村 おもしろいですね。そしてずっと続くのがすごい。どこかで途絶えてしまうと、もう一度つくるのはすごく大変ですね。
山内 日本もそうですが、現代社会では、おじいさん、おばあさん世代のライフスタイルと、父母の世代と子ども世代では、社会も日常生活も全然違っています。人類は途方もない時間、変わらない日常を過ごしてきたのに、産業革命以降の250年程度の間に生活環境もライフスタイルも大きく変わりました。自分の下の世代、とくに今のデジタルネイティブといわれる子どもたちは自分たちとは違う価値観を持っているのではないでしょうか。日々、大学生と接しているとそのように感じます。
人類学者が考えるトイレの問題
西村 先生は安全な水とサニテーション(狭義ではトイレ)、衛生についても研究されていますね。トイレって、狩猟採集民は野外で排泄するとしても、都市で考えるとなくてはならない機能です。トイレを考えることは人類学的なテーマだなと思うんです。
山内 おっしゃる通りです。人類生態学や生態人類学では人々のライフスタイルに焦点を当てて調査、研究しています。食べ物や栄養については大きな関心が持たれるのですが、排泄やトイレはとても重要であるにも関わらず、実はあまり手が付けられていないテーマです。自分自身、長年のフィールド調査でトイレ(野外排泄)については見過ごしていたんです。狩猟採集民の調査では食べ物の種類や重さを測って栄養摂取量を計算したり、1分ごとの行動観察と同時に心拍数を計測して運動量を調べたり、彼らのライフスタイルについてはよくわかっていたつもりでした。しかし思い返してみると、行動調査中に「トイレに行きたい」と言われたら、観察を一時中断していました。それは当然のことだと全く疑問に思いませんでした。しかし、ある時「山内さん、狩猟採集民のトイレはどうなっているの?」と他の研究者に聞かれた時に、自分は排泄やトイレ(野外排泄)についてほとんど何もわかっていないことに気づき、ショックを受けました。
国連のSDGsでは、「2030年までに野外排泄を撲滅する」(目標6)と謳われているのですが、狩猟採集民のように移動生活している人々に「トイレをつくりなさい」というのはナンセンスですよね。本当にトイレが必要なのは、途上国(最近は、低-中所得国やグローバル・サウスとも呼ばれます)の都市スラムです。昨年の3月に終了したのですが、京都にある総合地球環境学研究所で東南アジア、アフリカの都市スラムでサニテーションの仕組みづくりのプロジェクトに取り組みました。
 ザンビアのスラムでサニテーションについてレクチャーした時の様子
ザンビアのスラムでサニテーションについてレクチャーした時の様子山内 サブサハラ(サハラ砂漠以南)のアフリカの都市スラムでは、家にトイレはありません。コミュニティに共同トイレはあるのですが、ほとんどが壊れていたり、雨季に冠水してしまったり、ゴミなどが不法投棄されたりしていて近寄りたくない危険な場所になっています。早朝まだ暗いときや日が落ちて辺りが暗くなると野外排泄が行われますが、とくに女性は性暴力に合ったり、蛇などに遭遇したり危険なので、室内でコンテナやプラスチックに排泄する場合が多いです。そして、汚物を隣の家の敷地や道路に投げるんです。このような「フライング・トイレ」は都市スラムでは日常的に行われています。
スラムでは、朝スーツを着た男性や、ハイヒールを履いた女性が通勤する道端に、人間の排泄物が落ちている光景を目にします。スラムに住んでいる人々も飲み水の質にはうるさくて、水を買って飲んだりしていますが、排泄物やゴミは、自分の目の前になければそれでOKというように見えます。人類(ホモ・サピエンス)はとてつもなく身勝手なサル(霊長類)だな、とつくづく思わされました。
西村 フライングトイレットは、昔のパリでも行われていたことですね。本当かどうかは定かではないけれども、それをきっかけに日傘とハイヒールができたといわれますね。アフリカでのフライングトイレットについて、山内先生が取り組んでおられることを教えてください。
山内 大人たちは自分たちが暮らしているスラムでは、地下に下水道管を埋めるような大規模なインフラ工事はできないと諦めていて、道路に排泄物が散らばっているという状況に麻痺していているんです。そんな大人たちに外国の研究者や現地のエリートである大学関係者が上から目線で働きかけても聞く耳を持ってくれません。そこで、現地の子どもたちの力を借りることを思いつきました。
スラムに住んでいる小学生と地元青年団のメンバーで子どもクラブを立ち上げました。そして、研究者が調査をするのではなく、当事者(スラムの子どもたち)がコミュニティのサニテーションについて調査する「参加型アクション・リサーチ」を行いました。はじめに、子どもたちに飲用水やトイレや衛生について、グループ形式で楽しみながら学んでもらいます。それから、日本から持っていった中古のデジカメを子どもたちに配り、自分たちが住むコミュニティで水やトイレを中心とした衛生面で気になったところを写真に撮ってもらいました。そして写真にコメントをつけてもらいました。この活動を写真(フォト)とコメント(ボイス)を合わせて「フォトボイス」と呼んでいます。
 リサーチに参加した子どもクラブのメンバー
リサーチに参加した子どもクラブのメンバー 参加した子どもたちが撮影した写真
参加した子どもたちが撮影した写真山内 そして、2つのスラム地区でフォトボイスの展示発表会を開催しました。会場を借りたり、写真やコメントを貼る模造紙や文具の購入などは、研究者側でサポートしました。来場者は200人を超えて、予想以上の反響がありました。子どもたちの保護者、学校の先生や地元選出の政治家も来てくれました。このような地域の小さな取り組みが政治や行政へ反映されるには時間がかかると思いますが、コミュニティのレベルでは変化を感じています。プロジェクトの期間は5年ですが、2回続ければ10年です。十歳の小学生は二十歳になります。牛歩の歩みですが、地道に子どもクラブの活動を続けていくことでコミュニティが徐々に変わっていくと期待しています。
 ワークショップに参加した子どもクラブのメンバーの表彰式
ワークショップに参加した子どもクラブのメンバーの表彰式西村 これまではトイレの研究を「見過ごしていた」とおっしゃっていましたが、急速にサニタリーへの理解度が上がっているのですか?
山内 サニテーションの研究は、これまで見過ごしてきたのが悔やまれるくらい、おもしろくてのめり込んでいます。人間は二足歩行するので、しゃがんで用を足すことが多い。自分の体(お尻)が排泄物に触れてしまうので、倒木の上に登って排泄をするとか、排泄物の処理のために穴を掘るとか。それがトイレの原型ではないかと思います。フォトボイスのような参加型アクション・リサーチの調査研究と、人類学者としての人類の進化や適応という視点をあわせて『排泄人類学』というような本を書きたいと思っています。
またメタファー(比喩)として排泄物やその処理について考えるのもおもしろいです。廃棄物(ゴミ)や排泄物などは、社会の中で放置できず、なんとかして処理しなければならない「負の財(Bads)」です。社会には必ず「負」があって、それをどう処理するかが社会や文化によって異なります。例えば、インドではトイレ掃除人のカーストがあります。行政が「特定のカーストがサニテーション・ワークを担うのはよくない」と言ったら、逆にそのカーストの人たちから「サニテーション・ワークは自分たちのカーストの特権だ」として反対したという話があります。話は簡単ではありません。
話は変わりますが、今後人類が宇宙空間で生存するようになったときに、排泄物をどのように処理するのか、再利用できるのか、という点も技術的問題に加えて、文化的問題としても重要なテーマだと思います。
 インドネシアとザンビアと日本の子どもたちをオンラインでつないでディスカッション
インドネシアとザンビアと日本の子どもたちをオンラインでつないでディスカッション西村 以前、宇宙関連の企業と仕事をしていた時に出てきたのは、やはり排泄の問題でした。重力がない状態で排泄するのはとても難しいんですよね。重力がないから座って排泄できない。1回の排泄で平均30分ぐらいかかるそうです。宇宙飛行士がまず獲得しないといけない技術は、排泄をする技術だそうです。
山内 なるほど。やはり排泄は人間生活の基礎なんですね。話が広がりますが、現在の医学って、全てが地球の重力1Gを想定した医学なんですよね。これが宇宙空間で重力が0Gになった時には通用しない場合もあると思います。たとえば出産も変わってくるでしょう。
西村 そもそも無重力だと子宮に精子が着床しないんですよね。だから人工子宮が必要だという話になってきます。トイレも、都市だから現状のトイレが機能していますが、50年後は同じようにトイレが成り立つとは限らない。
山内 人類のトイレの歴史、変遷を考えると、まずは野外排泄で、やがて排泄の場が固定されて共同のトイレとなって、各世帯にトイレがつくられて、各部屋にもトイレがあるようになって。この流れでいくと、近未来には個人が持ち運べるようなトイレ、ポケットに入るようなトイレが出現するのではないかと妄想します。排泄物が一瞬で小さなキューブ状に圧縮されて、手でつまんでも指が汚れずにそのままゴミ箱にポイっと捨てられるとか。
西村 圧縮するのはおもしろいですね。水をかけたら圧縮されるような素材を使えばできそうです。
山内 ビル&ミリンダ・ゲイツ財団は、2011年から革新的なトイレの開発やトイレの再発明ということに取り組んでいます。水素と電気を発生させる太陽光発電トイレや排泄物を炭や燃料ガス、あるいは水と電気に変換したりするハイテクなトイレを開発しています。
西村 すごいですね。以前、パナソニックも体脂肪や尿検査ができる便座の研究をしていました。
山内 たしかに排泄物はいろいろな健康関連情報を含んでいるので、ただ捨てるにはもったいないですよね。コンポストで堆肥をつくって農業利用するとか、発生したバイオガスを回収するとか、下水汚泥を建築資材にするとかの利用価値もあります。でも人間よりも家畜の排泄物の方が利用効率が良く、社会・文化的にも受け入れやすいと思います。
西村 トイレって、自分とは遠い話だと思いがちですが、災害でインフラが遮断されると今のトイレは機能しなくて困りますよね。
山内 日本は災害が多いので他人事ではありません。おっしゃる通り、避難所生活の大きな問題としてトイレが挙げられます。災害が発生し、水洗トイレが機能しなくなると、排泄物の処理が大変です。衛生環境が悪化し、感染症の問題が生じたり、トイレが不衛生で不快な思いをする被災者が増えるし、トイレの使用を避けることによって排泄を我慢して健康問題を引き起こします。災害時のサニテーション問題の解決は急務です。
でもサニテーションの課題は、災害時でない平時にも存在しているんです。世界の中で日本は衛生状態がよく、古くは江戸時代においても、し尿を農業利用する循環型社会であったように、日本はサニテーション先進国といえます。日本の下水道普及率は人口の80%を超えています。しかし、下水道は高度経済成長時代に施設されたため、老朽化に直面しています。とくに過疎化、高齢化が進む田舎は下水道システムを維持管理する余裕がありません。大規模な中央集中型ではなく、小規模な分散型の仕組みへの転換が急務となっているんです。興味深いことに、サニテーションインフラが未整備の途上国においても、先進国と同じく、コストの低い分散型の下水処理の仕組みが求められています。
繰り返しになりますが人類の歴史を振り返ってみると、ホモ・サピエンスがアフリカで誕生してから30万年間、気の遠くなるほど長い間狩猟採集を行い、遊動生活を行ってきました。そして1万数千年前に定住し、農業を始めました。世界各地で文明が興り、都市がつくられました。産業革命が起こり、世界大戦を経て、情報社会の現在に至る...。つまり、人が定住して集住することで人口を増やし、文明が発展してきたんです。
気候変動、人新世、SDGsなどが話題となり、人間の活動が地球環境を激変させていると警告されていた最中、COVID-19感染症パンデミックが起こりました。ソーシャルディスタンスが要求され、一極集中型から多極分散へというパラダイム・シフトがおきました。サニテーションシステムも地下にパイプを張り巡らす大規模な中央集中型の仕組みから、小規模でその場で処理ができる自律分散型の仕組みへの転換が求められています。人間にとって、何をどのくらい食べるかと同じくらい、排泄やサニテーションの問題は重要です。これからも食と栄養、WASH(水、トイレ、衛生)をテーマとして人類進化と環境適応の視座から人間のライフスタイルと健康について考えていきたいと思っています。
インタビューを終えて
「健康」であることは、古今東西を問わず今も昔も人間の最重要な関心ごとのひとつです。山内先生のお話は、ここ数十年の健康という考えからもう一歩ひいて眺めて、人類としての健康とは何かを考える、とても興味深いものでした。また健康になるために食に意識を向ける人は多いですが、食べることの対義語である排泄は、なかなか直視しません。排泄までを円のように一つの営みとしてつなげて考えられるようになることが、これからの私たちには必要なのだと感じました。
(ライター:ヘメンディンガー綾 インタビュアー:西村勇哉 編集者:増村江利子)
この記事は、本学と連携し、株式会社エッセンスが制作しています。
https://esse-sense.com/articles/95