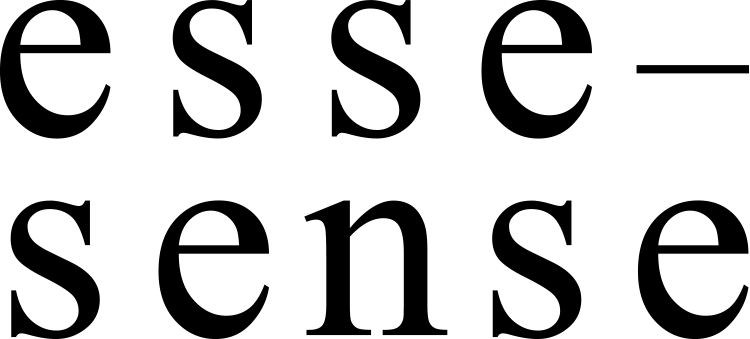今回インタビューした山口未花子さんは人類学の視点から「動物」について研究しています。主なフィールドはカナダ東部のユーコン準州。先住民であるカスカや内陸トリンギットの人々と動物との関わりについて研究を続けています。著書「ヘラジカの贈り物」ではカスカの古老に猟を学んだフィールドワークの様子が詳しく書かれています。カスカの人々の暮らしは当然のことながら食べ物を捕り、解体することが中心。狩猟採集民ではない私たちが仕事をしたり学校に行ったりするように、暮らしの真ん中に狩猟があるのです。
山口さんへのインタビューで最も驚いたのは「動物には集合意識がある」という概念。カスカの人々は獲物を獲ったらすぐに目玉をとる。そうじゃないと見た景色が他の動物たちに伝わってしまうのだそうです。カスカの人々にとって動物とは、自然とはどのような存在なのでしょう。現代社会に生きる私たちとは異なる視点に出会えるインタビューを、どうぞお楽しみください。
山口未花子
北海道大学文学研究院教授。1976年京都府出身。奈良教育大学で動物生態学を学んだ後、北海道大学大学院で文化人類学の修士号・博士号を取得。 東北大学東北アジア研究センター教育研究支援者、北九州市立大学地域共生教育センター講師、岐阜大学地域科学部助教をへて2019年4月より現職。 カナダ・ユーコン準州の先住民のもとに10年以上通い調査を行う。
小動物からヤギまで飼っていた幼少期
西村 幼少期のエピソードを教えてください。どこで動物好きだという認識が生まれたのでしょうか。
山口 動物を嫌になるきっかけがなかった、と言うほうが近いと思います。例えば文化人類学者レヴィ・ストロースは、人間は子どもが生まれたらすぐに動物を与える。それは狩猟採集民だった頃の名残だと言ってます。5歳の娘を見ていても確かにそうだと思うんです。もともと人間は動物に興味や関心があるけれど、現代社会で暮らすうちに社会に適応して、動物が親しいものではなくなっていくのかなと思います。
西村 人によっては動物好きが消えたりするけど、先生の場合は続いていった。
山口 そうですね。
西村 研究を仕事として続けようと思われた経緯を教えてください。
 自由の森学園時代の山口先生(写真左)。恩師の盛口満氏とともに
自由の森学園時代の山口先生(写真左)。恩師の盛口満氏とともに山口 「動物が好き」というのが変化していったと思うんです。少しさかのぼりますが、中学高校では盛口満(もりぐちみつる)先生や「イモムシハンドブック」の写真を撮られている安田守さんなどおもしろい先生が通っていた学校にいたので、生物学がおもしろいと思っていました。
西村 中学高校ですか?
山口 はい。自由の森学園という中高一貫の学校に通っていたんですが、制服もないし、校則もほとんどない。「こうあるべき」ということを一切教わらなくて、自分の好きなものを伸ばす教育を受けていました。先生たち自身がすごく生き物好きで森に行ったり、骨や貝を拾いに海に行ったりするうちに生物学がおもしろく思えて大学で動物生態学を学んだんですが、どちらかと言うとフィールドワークで動物の痕跡などを見て動物の生態の研究をしていたんです。でも哺乳類の生きている姿はなかなか見れない。見えたとしても一瞬で逃げ去ってしまう。
ある時、当時研究していたウサギを捕獲して調査しようとしたんですが全然獲れなかったんです。生物学者は動物に一番詳しいはずなのになんで獲れないんだろうと思って。そうしたら先生が「猟師さんなら獲れるけどね」と言っているのを聞いて「じゃあ猟師さんのほうが動物に詳しいのではないか」と思って。
動物生態学では、生態の学問的なアプローチとして数量化して普遍的なものとして動物の生態をとらえようとするのですが、地元の人に目撃談を聞けたとしても、一回性のウサギとの出会いはデータとして出せなかったりする。削り落とした一番信頼性の高いデータだけでウサギを語るんだけど、ウサギによっても個体差があるんです。そういうモヤモヤしたものが溜まっていきましたが動物に関する興味と関心は全然薄れなかった。むしろ、ウサギだけじゃない動物もやりたいなとか、もっといろんな見方でウサギを見たほうがおもしろいのにという具合に、どんどん興味が深まっていきました。そんな時にアメリカ人のリチャード・K・ネルソン氏の本を読んだんです。
彼はアラスカ大学で先住民の人類学調査をしたときに「動物生態学より自由に動物と向き合えるからしっくりきた」と書いていて、「動物生態学だけじゃなくて、人類学というアプローチもあるんだ」と思って。狩猟して動物を獲って食べなきゃいけない先住民は、真剣に動物の行動を観察しています。だから生態学的にも詳しい。一方で神話を語り継いでいたり、動物の身体を加工して使ったり食べたりもする。むしろ動物との関係も深いし、いろんなアプローチで動物のことを知れる。また一人の猟師が複数の種類の動物を対象にすることもできる。その辺りも生態学より自分には合ってるかなと思って。当時たまたまカナダの先住民の研究をされていた先生が北大にいらっしゃって、北米の先住民と動物との関係を見ていけたらいいなという思いがあって今に至ります。
西村 北大に移ってそのまま研究者になるという道が自然に続いたのですか?
山口 話すのが苦手だったので、先生になりたかったわけではないんですけど。修士や博士で研究していた時に、一人で現地に入っていくとやっぱりいろいろと大変なんです。そもそもカナダでは大きいヘラジカが獲れたらみんなで分け合ったりするし、人と助け合って暮らすのが楽しいような場所です。それが一人でできるかと言われると、イメージが沸かなかったです。それからお金を稼ぎながら研究ができるという意味でも一番合理的に研究、調査が続けられる研究者が第一志望でした。
西村 北米、もしくはカナダに行きたいと思われたのはリチャード・K・ネルソン氏の影響ですか?
山口 そうです。狩猟採集民の文化は、アフリカやアマゾン、東南アジアにもあるんですけど、北方のほうが動物への依存度が高いんです。一説には南方の狩猟採集文化の食べ物は半分以上は植物に依存しています。一方でエスキモー(カナダではイヌイット)は、ほぼ肉しか食べるものがない。つまり動物への依存度が高い。また北米は動物を家畜として飼育してきた歴史が浅いんです。インディアンは馬のイメージがあると思いますけど、それもヨーロッパから入ってきたものです。もともとは犬を飼育していたぐらいですね。
西村 犬は飼育というより、ついてくる感じですね。
山口 そうですね、パートナーのような感じです。なので北米は動物との関係が人間の初源的な形に近く、狩猟採集文化が残っている。そして、野生動物との関係にもずっと興味がありました。子どもの頃にいろんな動物を飼っていたんですが、小さい時から動物が好きでお年玉で「好きなものを一つだけ買っていいよ」と言われたら、ペットショップで動物を買うという感じで。
西村 どんどん増えていきますね。
山口 ウサギやウズラ、ニワトリや文鳥から最終的にはヤギまでたどり着いて、親もびっくりしたと思いますけど。やっぱり子どもだからうまく飼えなくて、ウサギには穴を掘って逃げられたり。ヤギは井戸に落ちて死んでしまったり。それで人間が動物を飼育するのは人間が動物を支配することで、動物にとって幸せじゃないかもしれないと思うようになったんです。一方で野生動物はすごく生き生きしていて、予測がつかない動きをして、そちらが本来の動物の姿でおもしろいと思うようになりました。そういうこともあって、野生動物への依存度が高い北米を選んだんです。
西村 ヤギを飼わせてくれる家って、なかなかない。それは家の中に動物を入れていくのか、動物がいるところで暮らすのかの違いですね。
動物には集合意識がある
西村 先生の著書『ヘラジカの贈り物』について「非人間の他者としての動物という関係性についてこの本では書かれている」という書評を目にしました。人間ではないけれど、他者であること。文字面では理解はできたのですが、それは「このヘラジカは山田さん、次は田中さん」みたいな感覚でしょうか。
山口 「動物が個体として見えてくる」というのはわりとわかりやすい話です。例えば、自分の飼っている犬や猫なら見分けがつくと思うんですよね。でも、一方で日本人が海外に行った時に全然人の顔の見分けがつかなかったりする。だから、親しさが個体性を可視化することに関係していると思うんです。ただ野生動物の場合、一回性の出会いなんです。一回性の出会いとはいっても結構その地域にずっといる動物なので、自分のコミュニティの中の他者というか、動物というよりは本当に他者。隣の村の住人ぐらいの感じなんですよね。だから、その人には一度しか会ったことがなくても、もしかしたらお母さんとかお父さんには会っているみたいな。それぐらいの近さというか、遠さですね。人間に置き換えてみると、日本人をよく知っていれば、一人ずつの違いもよくわかってくると。
他者との関係性という点については、カスカや内陸トリンギットなど北方の先住民は、シマリスやカエルといった小動物をすごく怖がるんですよ。中でもカエルは間違った扱いをすると人間が殺されると言われています。カエルと自分がきちんと向き合って、カエルのやってほしそうなこと、あるいはやってほしくなさそうなことを汲み取れないといけないとされています。それは人間が友人に対して「今日は疲れてるみたいだから、こういうことは言わないようにしよう」みたいな感じです。私も北海道の森の中で猟をしていると、シマリスにたまに会うんですけど、結構近くまで来たかと思えば、どこかに行っちゃったりして、わけがわからない動きをするから何を考えているのかわかりにくいんですね。
でも、シカと私はお互いに了解できる行動をする。見たら逃げるというのが基本で、変に近づいてくるシカなんか1頭もいない。あと、サイズが人間と近いのでだいたい通る道も似ているんです。だから、なんとなくシカの気持ちはわかる気がする。
西村 ヘラジカの目には集合意識があって、目玉を通して見たものを共有している、とも書かれていました。1頭ずつではなくて、集合意識があってつながっている。それはどういう捉え方をしている世界観なんでしょう。
山口 ヘラジカだけではなくて、カスカの人たちは動物には種によって集合意識があって、目玉を通して見たものを共有していると考えているんです。なのでウサギやヘラジカのように人間がその肉を食べる動物は仕留めた後にまず目玉をくり抜きます。そうしないと目玉を通して見たものを集合意識で共有してしまうから。小さい動物は目玉をとる以前にそもそも殺すことがものすごく危険なので、殺さないしなるべく触らないんですが。もちろん、ヘラジカやウサギ、特に大型のシカ類やヤギ、羊の仲間は群れで生きているので、集合意識に加えて種の一部としての個体という側面もあるのかなと思います。
西村 こうした関係性を築く動物は、群れで生活する草食動物が多いんですか?
山口 ヘラジカは草食ですが、単独性なのでちょっと違いますね。逆に狼のほうが群れだったりするので。
西村 狼とは関係性はないですか?
山口 カスカの人は狼をクランと呼んでいて、動物で一番賢いのが狼、鳥で一番賢いのがワタリガラスと言われていて、一番人っぽい動物とされています。狼とヘラジカとはライバルですね。
動物と波長を合わせると、動物の視点で景色が見えてくる
西村 カナダの先住民の中に弟子入りされて、最初はついて行くみたいな関係性だったと思うんですけれど。そこからだんだん横に並ぶ感じになって今は自ら狩猟をされている。「こういうことか」と理解が変わっていくみたいなことってありますか?
山口 すごくありますね。例えば「森の中で音を立てるな」って何度も言われていたんです。着ている服も化繊の音を立てるゴアテックスのレインギアとかを着て歩いていたら、「うるさい。音が出る服を着るな、毛のウールが一番いい」と言われて。毛は重いし血がつくし、と思っていたんですけど。今、自分でエゾシカを獲らなきゃと思って山を歩いてると、音がすごく気になるようになりました。
 森の中では音を立てないような服装で狩りに出る
森の中では音を立てないような服装で狩りに出る山口 あと、すごくおもしろいのは動物とのコミュニケーションの話です。山奥の猟師のもとに行ったことがあるんです。その人はいつも一緒に行く古老よりはちょっと若いんですが、一人で森の中で暮らして50〜60年も経つような人です。その地域でも「あんなに昔の暮らしをしている人はいない」と言われてるぐらい。もちろん電話も携帯もない。その人は学校を途中でドロップアウトして森に帰っちゃったから、文字の読み書きもあんまり得意ではないという人ですが、夜な夜な自分でつくった太鼓を叩きながら動物と交信するんです。そうして動物の守護霊を獲得していくんだという話を聞きました。
その時に、太鼓のリズムを動物のリズムと合わせていくと、ラジオの周波数を合わせるみたいに、動物の波長と自分の波長が合う。すると動物が見てるものが見えると言うんです。ある時「熊が後ろの山にいて、その熊の目から自分の後頭部が見えた」って言っていました。つまり、熊が後ろの山にいて、この角度で自分の頭が見えているということは、ここに熊がいるんだなと思っていたら、実際にガサゴソと熊が出てきたと。
私はそんなことはできませんが、リズムを合わせることは狩猟の中ですごく大事なんです。うまくいくときって、なんとなく全部リズムが合っている。歩いている時も、川の音や周りに溶け込めた時にシカが油断してるところを見つけることが多い。うまくいかない時は、途中で弾を落として慌てていたりします。そういう周りのリズムと合わせることの大事さは、なんとなくわかった気がしますが、だからといってまだ熊の視点は見えてない。経験を積み重ねていくとまた違う見え方がするのかもしれません。
野生動物を対象にするおもしろさは、人間の常識や社会で「これで大丈夫」とされている感覚では世界の認知が追いつかないことがあることです。自然の中でいろんな情報を分析しながら動物を獲る時は見るもの、聞くもの、匂い、体の動き、すべて都市にいる時と違う知覚にならないと、獲れない。体自体もやっぱり変わっていくのでカナダから日本に帰ってきた時も、感覚が全部開いていたために、あまりにも人が多い歩道で全方位から情報が入ってきてしまうのでどう歩いていいのかわからなくなったりしました。だから逆に都市で暮らすには全く違う、情報を取捨選択して場合によっては閉じられる身体じゃないとつらいと思うんです。人間は、ある意味人間社会から外に出ていくっていうことによって、今までとは違う感覚や自然とのつながりができる。そう実感したことで、荒唐無稽に思えたシャーマンの話も地続きで理解できそうだなという感じがしています。
西村 自然とつながるというと、自分があって自然があって、そこに橋がかかってつながるという感じに捉えられがちだと思います。でもそうではなくて、そもそも自然があって、そこに対してどれだけチャンネルを開いていくか。いつもは耳を塞いでいる状態だけど、耳を開くと自分と自然との橋がつながるような感じに近いのかなと思いました。
物理学者のデヴィッド・ボーム氏が書いた北米の先住民の話『ダイアローグ』という本の中で、先住民の人たちがずっと話をしていると、だんだんトーンが揃ってくるということをコヒーレンスと呼んでいるんです。トーンが揃うと自分がなくなる感じになって、結果としてますますトーンが揃うという感じです。今の話は植物も風も動物も含めた雄大なバージョンで、全ては後ろの背景とつながっているんだなと思いました。だから、ヘラジカと人間みたいな形もあるけれど、風もあるし森もある。そういう空間の中でのできごとなんだなと思いました。
山口 そうですね。自然と人間を切り取ることをしないのかもしれないですね。最近アーティストも交えて「描かれた動物の人類学」という研究会をやっているんですが「海獣の子供」を描いたマンガ家の五十嵐大介さんにお越しいただいたんです。「五十嵐さんはなぜそんなに動物を描くんですか?」と聞いたら、「僕は動物を描いているつもりはないんです」と言われて。研究会の趣旨が動物を描くということなので少し焦ったのですが、「人間を中心に描いていないんです」とおっしゃっていました。
例えば遊牧民の村の家の風景を描くときに、その空間にストーリー上は必要がないヤギの顔を描いちゃうらしいんです。編集の人に、「なんでここにヤギがいるの?」と聞かれたら「必然性は全くないけど風景としてそういうものだから」と言うそうなんですが。私たちは人間中心主義的な世界観を教育で受けてしまっているのか、カナダの先住民の人や五十嵐さんはそうではないふうに世界を捉えているんだなと思いました。
西村 おもしろいですね。最近、万葉集を勉強し始めたのですが、万葉集と古今和歌集は何が違うのかが気になってきたんです。それで気がついたことは、古今和歌集は美しいという概念が先にある。でも万葉集はその概念がない。先程のお話は動物の捉え方も「これが動物だ」と概念で捉えるのではなくて、そこにいるものが、たまたまヘラジカだったみたいな感じかなと思いました。
山口そうですね。もしかすると私が動物動物と追いかけているけど、現地の人たちにとっては、動物は特別ではないかもしれない。そこもおもしろいところです。
万葉集の話を聞いていて思ったのが、私も最近よく参照しているのがゴリラの研究者である山極壽一(やまぎわじゅいち)さんと中沢新一さんが対談された『未来のルーシー』という本。山極さんは「動物と人間は話せる」と力強く言っています。例えば、霊長類学者や狩猟者、動物園の飼育員の人はそれをわかっている。でも、その時に人間ってやっぱり一番自然なコミュニケーションだから言葉を使う。すると動物も動物なりの自然なコミュニケーションで返してくれる。
大事なのは、言葉はその時の情景を言葉で保存することができる、と。その山極さんも短歌や和歌には昔の人の自然の見方みたいなものがギュッとそこに凝縮されて残っているから、私たちが読んでもその情景がフワッと再現され、復元されるみたいなことが起こるんじゃないかとおっしゃっていて、今の話と近いなと思いました。人間が言葉を喋ることで人間の世界を構築する一方で、そうではない形の言葉もある。
西村 名前だって言葉を使っています。どういう関係性を築くのか、名前を通じて何回でも簡単に思い出せますよね。例えば、西洋人に対して使う名前のあり方と、動物に対しての名前のあり方は違う。これで関係性の距離感を常に保ち続けてるのかなと思いました。そうやって、ある意味固定しておくと、やりやすくなることもあるのかなと。
儀式を怠らずにいれば、動物は贈与されにやって来る
西村 先生にもう一つ聞きたかったのが、動物と贈与の関係です。動物を食べるというお話をしてきましたが、それはずっと風景として存在する山や川とはちょっと違いますよね。狩猟して、動物はやがて腐る。そこから、贈与という関係性がある意味自然に発生してくるんだなと思いつつ、贈与と交換経済についても論文に書かれています。贈与と交換経済って両立するのでしょうか。
山口 カスカの人たちは、自分たちの伝統的な文化が交換経済や管理システムといったものに蝕まれている感覚を持っています。それをよく表すのが、ツクコン・ケとデネ・ケという言葉。ツクコン=白人、ケ=やり方、デネ=人間。つまりツクコン・ケとデネ・ケというのは白人のやり方と我々のやり方みたいな感じです。因みに、動物はデネの方に入ります。
西村 おもしろいですね。
山口 今はデネ・ケがなくなってる、とよく古老たちは嘆いてるんですが「みんな森に行くとデネ・ケに戻るよね」と言います。同じ人でも、町にいる時と森にいる時で全然違うものの分け合い方をするんです。猟に行くとフルーツとか、肉とか新鮮な食べ物は腐ってしまうので始めの3日くらいでなくなって。だんだん魚を釣ったりその辺の植物を採集したりして食べていくんです。それだけではなくて、他の人が持ってきたものも食べるんですよね。特に断りもなく。私は、初めはそれに慣れなかったんですけど。「俺のものはみんなのもの。みんなのものは俺のもの」みたいな感じで。だけど、町だと人のものはそういうふうには食べない。
西村 勝手に食べないんだ。
山口 おそらく森の中にいる時は狩猟採集民的な心が戻って「食べ物が腐ってしまう」のは大きい気がするんですよ。食べないと腐るしおいしくなくなってしまう。さっきおっしゃった贈与がベースになって、動物との関係もつくられている。ヘラジカが贈与されにくるという話も北米を含む北方圏ではかなり広く見られる考え方なんですが、森の中では贈与が基本になっているのがやはり大きいかなと思います。わかち合わないとやっていけないっていうことかと。
あとは、ヘラジカってすごく大きいんですよね。森の中で会ったらもう震え上がって怖くて動けなくなるくらい。いくら鉄砲を持っていても、対峙するのは怖い。そのヘラジカを最近まですごく小さい22口径の銃で獲っていたらしいです。因みに私の大学院時代の先生もそれで熊を殺しているんです。それはつまりかなり近くから、心臓や頭を確実に撃ち抜けなかったらこっちがやられる世界。そういう時に、これまで動物を獲ったあとにきちんと儀礼して、無駄にしないで使うとか、しっかり規範を守っていることを動物が知っていてくれているという実感があれば、動物がおとなしく獲らせてくれるはずだと信頼して心を乱さずに撃つことができる。そうした動物との絆に基づいた社会関係があるということが贈与関係につながっていると思うんですよね。
贈与ベースの経済って、もらったらあげるというふうに、他者との関係をつくる行為でもあるので。儀礼をすることによって、今度は動物が返してくれるだろうと期待もできる。贈与って、全部もらってそれでいいということではなくて、誕生日プレゼントをもらったらその人の誕生日にはお返しをするという未来が起きているはずで。きっと神様にお供えするのもそうすればご利益をくれるだろうというのに近いのかもしれません。動物に贈与する、あるいは贈与されたものを正しく使うことが続いていくことは、実際に暮らしの中で贈与することで確信できるようになります。動物から贈与されたものを人間の間でも贈与する。そこも全部つながっているんですよね。
西村 ヘラジカとの関係において、人間側から提供していることは殺した後の儀式か、食べることなのか、あるいは他の行為がヘラジカに対して行われているのですか?
山口 真っ先にやるべきことは、ヘラジカを再生させる儀礼です。獲った後に器官や足、舌の先を木の枝にぶら下げます。ヘラジカの身体の一部を森の中に置いておくことによって、ヘラジカが再生すると考えられているんです。ヘラジカは死体になっても集合意識とつながっているとされているので、先住民はその目を気にして、ちゃんと儀式をしていることを見せたいんです。
でも先程言ったように、動物は集合でもあり個体でもあるので、今目の前にいる個体がどうしてほしいかは実はわからない。例えばもし贈り物として来てくれてるなら、ちゃんと受け取らないと恩知らずになります。そういう時はちゃんとヘラジカが止まって、こっちを見ている間に即死させるように撃つ。そしてその肉と皮をもらうのが一番礼儀正しいやり方です。ちなみに魂は死んでいないと考えるので「殺す」とは言いません。でも時にプレゼントしに来ていないヘラジカに出会うこともある。その場合は獲らないほうがいいんですが、そういう判断は難しいですね。
西村 今じゃない、と。
山口 そうですね。例えば、子どもがいる母鹿はとらないとか。ある時、猟について行ったらお尻のところに銃が当たってヘラジカが逃げちゃって。仕留められなかった時に「悪い印象を与えてしまったから、もうこれで3ヵ月ぐらいヘラジカには会えない」と言っておじいさんがガッカリしていたことがあります。
西村 ちゃんとふるまうことが大事なんですね。
山口 そうです。こちらもそれを見せている。むしろそれが戦略で、「自分はちゃんと儀式をしているから来てくれ」ということです。
西村 贈り物や「あげたから返す」みたいな感じよりも、ちゃんとした関係性を築いて循環している。そんな感じなのかなと。
山口 どっちかと言うと、助け合っているという感じがあるんです。どうしてもお腹が減って、死にそうになったら向こうから来てくれる、とよく言われました。私が調査しているキャンプはあまりクロクマやヒグマを獲らないんです。私の仲が良かったおばあちゃんも、人生で一度だけ熊を獲って食べたと言っていて。その時は、お母さんと一緒に森の中で暮らしていた時にお母さんが熊を撃って。熊の頭を切り取って木の枝に置いて「本当にお腹が空いていて死にそうだったので獲らせていただきました」というお祈りをしていたらしいです。そうしたら、その次の日にヘラジカがそのキャンプにやってきたんです。つまり今度は熊がヘラジカをよこしてくれたと言っていました。
本当はあんまり獲るのがよくない動物でも困っていたら肉をくれるし、しかもヘラジカまでよこしてくれる。人間が本当に困ってるのは、動物もわかっているんです。先住民には守護動物がいるという考えがあります。例えば、そのおばあちゃんはキツネやライチョウが守護動物なんですが、森で迷ったら帰り道を教えてくれたり、獲物のいる場所を教えてくれたりする。こういう特別な関係になる時は、森の中で死にそうなほど困っている時が多いんですよね。本当に困ってる時は人間同士だけではなく動物や、もしかしたら風や木、そういうものも含めた存在が助け合うこともあるのかと。人間も、例えばビーバーが木を集めていたら木を切って置いておいてあげたり。鳥がヘラジカの肉を食べたそうに集まって来たら投げてやったり。自分だけが独り占めすることをしない。
西村 ただの物語ではなくて、それが暮らしとして次の世代へと続いて、数万年単位で成立しているのがおもしろいですね。人間が今自分たちの都市の社会が持つ物語と暮らしが、うまくリズムが取れていたらもっとすっきりするなと思いました。
カスカの人々の時間概念
西村 最後の質問は、カスカの人たちにとっての時間の概念について。先ほどの動物の話からも、過去のふるまいが現在につながっていることはわかりました。では未来についてはどういう感覚を持っているのでしょう。
山口 それもこちらの考え方を当てはめながら考えないといけないので難しいところです。短期的な未来はあると思います。おもしろい事例は、死ぬ時に未来のビジョンが見えるという話。例えば、私がよく一緒に狩猟に行っていた方の祖父が亡くなる時、つまり約200年ぐらい前ですが、モスキートみたいに空を飛んで何かがやってきてそれが地面についたら、そこから人が出てくると話したそうです。あとからその方は飛行機のことだったと解釈していたんですけど。
このようにちょっと先の未来を子孫に残していく、その風習はあるので、そういう意味では、100年後ぐらいの未来は想定はしているんだろうなと思うんですね。一方でアボリジニの人たちのドリームタイムみたいに、死んだら過去や未来がない初源の世界に戻るという感覚もある。そこでは動物や人間が普通に話したりできる。でも、みんながその話をするわけでもないんです。こういう場所が森の奥にあって、儀礼など特別なときだけそことつながる、だから逆につながってよいタイミングでなければ儀礼用の楽器を鳴らしたりしてはいけないと聞いたこともあります。
またカスカの人は狩猟採集民なので、人が死んだらその場に埋葬して別のところに行く、みたいな感覚なんです。なので彼らにとっては時間って循環していくもの。もちろん所得倍増計画のように「どんどん発展しよう」という発想は全くない。どちらかというと維持するのが大事で、この「維持」も、自然に任せておけば勝手に維持してくれるという感覚です。なので、何か世界を変えたいということもない。どんどん変化していく感覚もそもそもないので、千年後とか地球が滅びるというようなことは、そもそもあまり意識に上らないのかなという気がします。ただ、人によっても捉え方が違うし変化してきているとは思います。
西村 お墓はあるんですか?
山口 カトリックが入ってきたので、今はお墓はあります。
西村 昔はなかった?
山口 昔は山の上、天に近いところに遺体を埋葬して、その印があるという話を聞いたことがあります。
西村 八重山や北海道でもフィールド調査をされていらっしゃいますが、日本とカスカの社会の接点や、日本の社会、もしくは日本における世界についても少し伺いたいと思っていたのですが、いかがですか?
山口 日本でも岐阜と北海道と西表島で狩猟をしたり、猟師さんに同行したことがあります。場所によって全然違うんですが、岐阜のフィールドは昔は動物がこなかったような場所なので動物を殺すことに対する忌避感がある。血は汚れだから、自分の土地では流さないでほしいとか。4つ足の動物を食べるのはよくないとか。でも獣害があるから狩猟はしなきゃいけない、シカやイノシシも獣害対策としてなら殺してほしい、という矛盾する感じがありました。
 西表での狩猟の様子
西表での狩猟の様子それが多分、一般的な日本人の感覚に近いと思います。一方で、西表の人の多くは狩猟をポジティブに捉えています。イノシシをカマイと呼ぶんですが、とったらみんなで食べるし庭でも解体する。血が汚れという感覚もない。むしろ、解体を手伝ったりしながら「おこぼれもらえないかな」と子どもも見に来る。その点西表は岐阜よりもカナダに似ています。猟をする人は尊敬されるし、ちょっとモテるみたいな。「この時期のイノシシは、シイの実を食べているから肉が脂も甘いけど、どんぐりを食べ出すと味が落ちる」と言うのも「この時期のヘラジカは水草を食べているから胃の中が真っ黒で栄養があって脂が乗っている」と言うカナダ先住民の視点に近いと思います。西表はおいしいものは自分の土地で食べるという狩猟採集的な文化が今でも残っている地域ですね。
その土地でどんな植物が生えて、それを動物が食べて、それを自分も食べるというように、動物とだけでなく土地とののつながりも見えている。そういうものとして捉えて、贈与みたいな形で分配する。岐阜のフィールドなど日本の多くの地域では獲る人だけに殺すことを任せて食べもしない。
でも、北海道はまた違っています。アイヌの人たちが農耕をあまりしないで維持してきた天然の広葉樹の森が残っているから、狩猟はすごくやりやすいですね。北海道はほとんど国有林でアクセスしやすいですし、集中して狩猟を極めたい時は一人で山に入って動物に向き合いたいのですが、北海道はそれができるので幸運だと思います。
西村 たとえば奄美大島って、ずっと狩猟をしていて農耕をやってこなかったと考えられています。すでに狩猟で完全な世界観があるんだから、もういいじゃない。農耕を始めたら、自然が贈り物をくれなくなっちゃうという感覚があるんじゃないのかと、お話を聞いていて思いました。奄美大島の人たちは、自然との関係性がすごく近くて、山や海に一つずつ固有名詞がついている。「こういう世界観があったんじゃないか」というお話をぜひお願いしたいです。
山口 カナダでも、トナカイを牧畜化するという話があったけれどできなかったらしいですよね。他にもビーバーの子どもはめちゃくちゃ可愛いので、連れて帰りたくなっちゃうんですけど、飼っては駄目だとされている。それはきっと動物を飼ってしまうと関係性が変わってしまうということなんだと思うんです。野生でないと今の関係が続けられない。そのうちヘラジカが贈与されにきてくれなくなったりするから駄目ということなのかなと。例えば飼ったら殺したくなくなるということもあると思うので、人間の意識が変わることも大きいと思います。
西村 今日のお話は、日本の自分たちの歴史を理解する上で、忘れてしまっている世界観なのではないかなと思います。さっきの万葉集の例でも、歌の情報はたくさん残っているけどそこから万葉集の世界観や時間感覚を知るにはジャンプが必要です。でも頭で理解するところから入るとちょっと違うんだろうな、難しいですね。でも、すごくおもしろいですね。そこに注目されて17年も関わってこられているのはすごいなと思いました。
インタビューを終えて
個人的な体験ですが、連絡先がわからなくなってしまった知人を夢で見たことがあります。どうしてもその知人に会いたくなり、公園の木々に必死に祈りました。その知人が住んでいる場所にも同じ種類の街路樹が生えていて、私の願いを伝えてくれるだろうと思ったからです。すると偶然が重なり5日後には本当にその知人に会うことが叶いました。
これは超自然的な現象で人に言うと笑われると思ってきましたし、実際に植物に集合意識があるのかはわかりません。それでも動物には種によって集合意識があると考え、何千年も暮らしてきた人々がいるカスカの人々の存在に、私は嬉しくなりました。自分たちが常識と思っている世界観を覆すきっかけを与えてくれるのが人類学の調査・研究のおもしろいところ。その一端を感じていただけたら幸いです。
(ライター:ヘメンディンガー綾 インタビュアー:西村勇哉 編集者:増村江利子)
この記事は、本学と連携し、株式会社エッセンスが制作しています。
https://esse-sense.com/articles/71