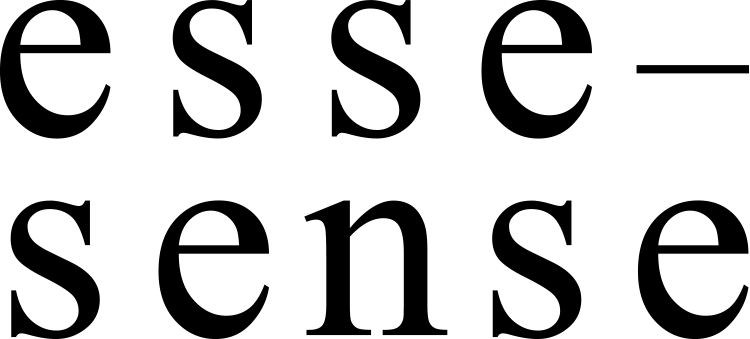リサーチタイムズとesse-sense(エッセンス)のコラボレーション記事をお届けします。esse-senseは、分野の垣根を超えた研究者たちのインタビュー記事を通して「あなたの未来を拓く」をコンセプトに、株式会社エッセンスが運営するウェブメディアです。本学の研究者たちにもスポットライトを当て、インタビュアーである西村勇哉氏(エッセンス 代表取締役)が、最先端の研究、そして研究者ならではのものの見方や捉え方に迫ります。ライターはヘメンディンガー綾氏が務めました。
通信技術の発展に伴い、映画は映画館だけではなく自宅でも鑑賞できるようになりました。ひょっとすると以前よりも映画に親しむ人は増えたのかもしれません。また、それと呼応するように毎年数多くの映画が上映されています。しかしそれは同時に、新しいものが生まれ、古いものが忘れられていくという消費のサイクルをも生み出す可能性があるということ。今日は、映画批評家としての立場から、作品擁護のために映画の再価値化を試みてきた阿部嘉昭さんのインタビューをお届けします。阿部さんは批評家としての顔を持つ一方で、詩を媒介に表現者としての一面も持ちます。批評と詩作。全く異なる2つの世界をつなげるものは一体何でしょうか。
阿部嘉昭
東京都出身。北海道大学大学院文学研究院 教授(当時)。1982年慶應義塾大学法学部卒業後、株式会社西友映画製作事業部、キネマ旬報社などでの勤務を経て、2007年から立教大学文学部文学科文芸・思想専修 特任教授 を務める、傍らで詩作活動を開始。2012年より現職。主な研究内容は日本映画における俳優身体、話法、映画技法。またマンガ、音楽(ロック/Jポップ)、アニメ、写真などの構造分析、詩・短歌俳句を中心にした文学研究、創作論など。
マンガに親しんだ幼少期
西村 最初はこれまでの経緯から伺いたいです。子ども時代はどのように過ごしていましたか?
阿部 子どもの頃は人見知りで寡黙でした。しかも小学校の低学年から近視で黒板が見えるふりをしていたんです。小学校の3年ぐらいから黒板にこういう字が書かれているんだなと予想できるようになって、そこから成績がオール2からオール5に向かい始めました。
西村 それは、逆にすごいですね。その頃はあまり本を読んだりもしなかったのですか?
阿部 マンガだけは読んでいましたね。
西村 そうか、マンガは近くで見れば読めますね。
阿部 はい。本屋さんに行って本棚の前に座り込んで棚全体を制覇していました。いやな子どもです。小学校の3年ぐらいでもう、つげ義春の漫画に感激していました。
西村 中高生時代からすでに詩作をされていたと拝見しましたが。
阿部 はい。詩を書いていることが人に知られると恥ずかしいのですが、その恥ずかしさを原動力にしているところがありましたね。「より恥ずかしくなるために詩を書こう」みたいな気持ちです。矛盾していますが。
西村 恥ずかしい気持ちを増やしていく。それはどのような感覚なのでしょうか?
阿部 一番恥ずかしいのは「俺の詩はすごいだろう」という態度。それが見えると、舌を噛んで死んでしまいたいくらいですよね。大学時代に雑誌「ユリイカ」に詩を応募したんです。それが掲載されていることが演劇クラブの先輩に見つかって。選評の書き出しが「夢見る二十歳」と書かれていたのをからかわれて。それで「もう詩なんか書くものか」となりました。
西村 なるほど。そして一度、やめたのですね。
阿部 はい。その後しばらくして、「現代詩手帖」に詩を送ったら、選考座談会の最終まで残ったのですが、現代短歌を散文詩にどうやって移行するかという僕の方法論を完璧に見抜かれてしまったんです。
西村 そうなのですね。
阿部 大岡信さんとか、吉増剛造さんとか、そうそうたる方々がいらして、吉増さんは「その感じは嫌いじゃない」と言って下さったのですが。その時平田俊子さんが賞を取られて、「詩の潮流が変わった。もう自分の出番はない」と思って読む側になりました。
一度は諦めた詩に、再び出会う
西村 そこから立教大学で教鞭を取られていた時にメールで詩作を再開されたとか?
阿部 はい、僕によく音楽の情報をくれる学生と情報交換をしていた時に、メールでポンポンと改行したら詩の分かち書きのような感じになったんです。そしたらその学生が「先生すごい、これ詩ですね」と言うんです。「こんなのいくらでも書けるよ」と頻繁に改行したメールを打っていたら、だんだんメール文が詩のような形式と内容を持ち始めたんですね。
西村 リズムがある詩、みたいな?
阿部 最初はそうでした。22歳ぐらいから詩を書いてなかったので、詩的なエネルギーが体内に充満してたから、言葉がダダダダダっと出てくる感じでした。例えば、詩を書くときに1編1編これまで使っていない語彙が入った方がいいと思うんですが、当時は、詩を長らく書いてなかったから全ての語彙がまっさらだったんですね。一方で、「評論は偉そうなので書きたくない」 とも思っていたので、評論で使わない言葉遣いをしていました。例えば、"である"って使わないんですよ。そういう書き方が評論にも逆流してゆきました。
西村 確かに、そうですね。
阿部 "である"がない評論って、当時はちょっと異常だった。 "である"を使わない、その天邪鬼の延長線上で詩では例えば3行詩の分かち書きもある。そういうのが気持ち良かったんですよね。なので、僕の詩もだんだん短くなって、ひらがなが増えて、威張らなくなっていく傾向にある。詩によって人格が淡くなったというか。
西村 評論の時の阿部先生と詩の時の阿部先生って人格が違うなと思いました。
阿部 僕の評論はよく「酔う」と言われます。読んで酩酊して意味がわかったような気がするけれども、後からそれを引用しようとすると全く意味が通じない。それは思考のスピードがマックスになっているということだと思います。それに対して、詩の場合は「いさめる、おさめる、なだめる」みたいな感じです。詩はゆっくり読まれたいので、飛躍をしてわかりにくくさせるとか、ひらがなを連続して読みにくくさせていて。とはいえ 評論と詩は思考の方式が違うんですね。先程西村さんがおっしゃったように詩的な直観力と学術論文はまた別の問題としてある。
 ENGINE EYE 阿部嘉昭のブログでは、評論や詩を発表している
ENGINE EYE 阿部嘉昭のブログでは、評論や詩を発表している西村 話している時はどちら側ですか?
阿部 両方です。阿部嘉昭という名前の漢字に全部「口」が入っているんですよ。「だからあんたお喋りなんだ」とサラリーマン時代に言われましたね。
西村 この「話している感覚」と「詩で書かれている感覚」って、やっぱり違うような気もします。例えば「まだないもの」を詩の中に入れられているのかなと思いました。
阿部 問題は、僕が評論を書きつつ詩も書いている時に一体何が起こっているのかだと思います。僕は研究論文の主軸が映画なのですが、そこにはテマティスム映画批評を確立した蓮實重彥(はすみしげひこ)先生の影響があると思います。テマティスム映画批評というのは、ある主題が反復されているという指摘を拡大して、1つの映画の全体像をつくる。それを他の映画にも適用して、ある映画と同じ形式が共通していることの意味まで問う 批評の形式です。テマティスム映画批評は、70年代の半ばから注目を浴び80年代は大ブームになりました。僕の最初の著書「北野武 vs ビートたけし」は蓮實さんの影響下で書かれたとも指摘され、以後はそこから離れよう離れようともしていました。
西村 つまり蓮實さんとは同じ批評の仕方はしないということですか。
阿部 映画評論にもいろいろな方法論や研究がありますが、僕がやろうとしてたことは単純なカルチュラル・スタディーズとか、単純なフェミニズム論でもないのです。部分的には言語学的なので、メトニミー(換喩)やアレゴリー(寓喩)という言葉も使うし、通常映画では使わないような思考方法を現代思想のジャンルから援用することもあります。
映画に関する文献主義に対しては微妙なポジショニングだと思います。公開当時の需要状況を考える社会学的な視座をもつ一方で、1本の映画を観ることによって観るとはどういうことかを原理的に考える。ですから自分の評論の注記は、ある時期は現代思想的な着眼がとても多くなりました。
僕がキネマ旬報社で働いていた時に、ベストオブキネマ旬報をつくる話がありまして、一旦編集担当になって、通常業務の時間が空いた時に古いバックナンバーを読んでいったんです。 戦後はつまらない印象批評が増えたなと感じました。 こうした批評は引用できない、と考え、映画批評の権威自体が崩壊してゆく一方で、 普段からわりと読む現代思想的なものを映画論に応用するようになっていきました。現代思想は、いわゆる考えの網目みたいなものを持っているから結局引っかかってくるんですね。
西村 なるほど。
阿部 先に網目をつくっておいて、そこに落とす形になる。その時に、いわゆる「これであってこれでないもの」を考える。つまりジャンルで言うと映画と現代思想の問題 、あるいは1本の映画で言うと、この細部と別の細部の問題でもある。それで先ほどのご質問に戻りますが、多分その"別の"ものを思考する方法が、詩的な直感力と似ているのかな、と思います。
 北海道大学大学院文学研究院・大学院文学院・文学部の教員が執筆した書籍を集めた「書香の森」のウェブサイトより。黒沢清監督作品を分析した阿部さんの著書「黒沢清、映画のアレゴリー」
北海道大学大学院文学研究院・大学院文学院・文学部の教員が執筆した書籍を集めた「書香の森」のウェブサイトより。黒沢清監督作品を分析した阿部さんの著書「黒沢清、映画のアレゴリー」西村 ものすごくおもしろい。今のお話は詩的な直観力であると同時に、作品の中か時代の背景を背負いながらどういう構造を見ていくのかということでもありますよね。後からどんな構造がそこに見出せるかをやっても駄目で、先に構造のあり方を知っておかないといけない。それで「今回たまたま触れることができたな」という要素を回収していくと、だんだん構造が表れるようになる。そういうことですよね。
阿部 そうですね、ただ僕の評論で一番着目しているのは、空間や身体の問題でもあるんです。現代思想系で身体というと例えばメルロ=ポンティ(※)を引用するのが定番なのですが、メルロ=ポンティと映画は合わないんじゃないかな。
(※)メルロ=ポンティ(1908-1961) フランスの哲学者。人間の知覚の主体である身体を、主体と客体の両面をもつものとしてとらえ、世界を人間の身体から考察することを唱え、現象学に大きく貢献した。
西村 確かに。
阿部 映画に適用できる身体論は、多分現代思想系ではあまり展開されていない。例えば身体についてある発見をするとします。俳優の身体を通じて一つの身体論を構築する時に、それを援用する参考資料がないんです。じゃあどうするかというと、ないから自分で書く。そうしないと書くスピードが落ちていくのかなという気がします。
西村 だとすると、やはり身体の中に構造が後から表れることがあるんじゃないかなと思います。
阿部 はい。でも、逆も言えますよ。構造の中に実は身体が呼びこまれていることもある。
西村 つまり構造の中に身体性があるっていうことですか?
阿部 映画の場合は特異なものが出てきます。例えば、定められた空間の中を動く、動かないという選択がなされた上で、その身体に対して物語が絡みついてくることがあるとする。すると、この身体は多分単独の身体ではなくなってくる。それなのになぜ単独の無名性に見える瞬間があるのか。そういう時に、物語はどうなっているのか、照明はどうなっているのか、構図はどうなっているのか。つまり、個別の状態によって違う身体が一人の俳優から現れ続けるというのが、映画の持っている富なんだということですね。
 阿部さんの著書の数々。映画やマンガなど、サブカルチャーも評論の対象となる(北海道大学 文学研究院ウェブサイトより)
阿部さんの著書の数々。映画やマンガなど、サブカルチャーも評論の対象となる(北海道大学 文学研究院ウェブサイトより)西村 映画ってどちらかと言うと現実と切り離したシチュエーションを撮ると思うのですが、今のお話はそこにも現実があるということですね。
阿部 そうですね。撮影されているものはひとつの局面では必ず現実です。同じような言い方をするなら、映画には過去はなくて、映されているのは全て現在です。そこに身体があるとすれば身体は時間と不分離になる。だけど、その身体が本当に持続しているのか。映画にはジャンプカットがあるし、感情が全然変わって見える瞬間があるなど、いろんな問題があります。
西村 映画って、シチュエーションを現実から少し切り離して、時間も切り刻んでいくと思うのですが。でも、そこには両方あるわけですよね。
阿部 はい。例えば時間性の断片のみに着目して、純粋な編集論みたいなアプローチをすると、その研究論文は画面の持続性を度外視しすぎたために瓦解して失敗する。
西村 なるほど。
阿部 細かすぎるものを考察していいのかという問題があるのです。僕も昔は、記憶力が良かったので、このカットはこうなって、俳優の演技はこうだったと微視的に言えたんですが、今はもうほとんど言えなくなった。今は記憶力が悪くなった弱者が主体になっているような映画論にシフトするだろうと思います。
年を重ねることで見えてくる世界
西村 そうするとブログにある花眼というタイトルの詩とも少し重なってくるなと思います。老眼という意味ですよね、すごくいい言葉だなと思いました。これをタイトルにしてしまうということは、心境も「これを世に出してしまおう」ということかと理解したんですが。
阿部 そうですね。実際にひどい老眼です。メガネを2つ使っているんですが、近い方を見るメガネは本棚が遠すぎるし、遠い方を見るメガネは本棚が近すぎて見えない。
西村 花眼という言葉には見えてなかったものが見えてくるみたいな意味もあるのかなと思ったのですが、映画でも見え方が変わっているということですか?
阿部 そうですね。例えば、いわゆる「憂鬱」のようなマイナスの感情に対して、自分の思慮が及んできている感じです。
西村 「ゆっくり感じる」みたいな?
阿部 そうですね。「遅延化する」というのは、歳をとった時の体の兆候でもあって、多分思考の兆候でもあるだろうなと思います。
西村 すると、阿部先生自体の身体が変わることによって、受け取る身体性も変わっていくっていう。
阿部 変わっていくと思います。例えば、昔はスクリーンの中できれいな異性の姿を見るのが好きでした。今はその感じは大分減ってますよね。そのかわり、より虚心坦懐に構造などを見ているのかもしれない。少し余談ですが女性をきれいに撮るのは監督の才能ですね。例えば、去年亡くなったゴダールもどんなわかりにくい映画でも、終始女性はきれいに撮っていますよね。まあ、女性がきれいだとあまり言ってしまうと、ルッキズムの観点から今はちょっと問題になりますが。最近、映画評論では「書き方の問題視」が槍玉にあがることが増えてきているんですよ。一番大きな問題は、ネタバレでしょうね。
西村 確かに。
阿部 ネットやSNSでネタバレした場合には袋叩きにあう。ところが、学術論文になった時に、結末に触れないと一体どうするんだっていうことになる 。 映画のプログラムに書く時は「結末について触れていますので映画鑑賞後にお読みください」という但し書きを最初につけるなど対応策を講じることもできますが。なぜそれほどネタバレに恐怖感を抱いているのか。結局は「物語を消費するため」に映画があるからなんですね。最近は早送りで映画を観るとか、10分の映画でまとめるというようなファスト映画の風潮も出てきていますが、物語では要約できないものが映画の中には充満している。詩もそうですね。評論や小説と詩の違いも要約の可能不可能だと思います。
「わからなさ」を探求する悦び
西村 今日のお話は、すごく人類学っぽいなとずっと感じてました。
阿部 そうですか?人類学にはそんな知見はないですが。
西村 フィールドワークで見えたものに対して構造をそこに見ようとする。それが映画でできるのは感動です。映画ってストーリーや設定があってそれを演技していくと思っていたんですが、その現場にリアリティと身体性が表れるし、同時にストーリーもある。詩的感覚、サブカルチャー、学術研究が全部つながって、学術研究としても新しさを提示できるということだと思います。
阿部 そうですね。でも、多分扱っている対象が好きだという時は、詩のわからなさと同じような謎を感じます。たとえば自分の思考方法に思考A、思考B、思考Cがあったとすると、そのA・B・Cの関係に実は謎が入っている。その謎が多分、思考の逼塞を打開する一つの方法になるだろうと思っています。それは詩作体験の具体性にも適用できる。例えば、詩であるフレーズを書いてその次のフレーズに詰まった時に、そこで10分、20分考える。このとき打開策が生じるとするなら、それは解答ではなく、謎そのものが降臨する、という感じです。考えるというのは、一種の探索、探すことではあるけれども 、近道を探しちゃいけないんだと思う。遠いところからポンと持って来る。
映画でも思考Aと思考Bというのを、近接した関係にせずに謎めいたねじれの関係に持って来ることで適用できる。それで近道の連続の逼塞を打開する感覚かな。
西村 それができる身体の資性とは、なんでしょうか。
阿部 表れている事象の一つひとつの間に、一種の遠さがある。それが世界と同じような構造をしているんだというような考え方をすべきなんじゃないかな。
西村 僕は40歳になるまで詩が一切読めなかった人間なんです。文字が少ないのに、読んでもわからないし読んだ気持ちになれない。長い本の方がゆっくりでも読んでいけば読んだ気持ちになれる、と思っていたんです。でも山尾三省さんの本を読んで、詩を読んだというよりも、こういうことを考えている人なんだということを読むことで、詩ってすごく考えられているんだとわかったんです。
阿部 詩が嫌いな人は「わからない=つまらない」になっている。一方「わかった=おもしろい」というのもあるけど、これはたいして問題じゃない。わからないけどおもしろい不思議なことが起こる。その時に、おもしろいのはなぜだ?読みものって、読む瞬間にみんながわかるという、そんなおこがましいことがあっていいのか?となります。そこで気がつくのは多義性、そして解釈不能なものが絶対にあるんだということ。それがいわばこの世の芯で、それをぼんやり見ているみたいな状態になると楽しいですね。
ちなみに、僕の詩の授業では詩の解釈をよくやります。でもひとつの解釈を見せた途端にそれを忘れてもらって、必ず絶えず新しい気持ちで読み直してくださいと言います。3年前の授業と今日の授業も、全く同じではありません。要するに詩は、読むこと自体が既にチャンスになってくるんです。するとわからなさで頭を抱えるのは馬鹿らしいことだとわかってくる。
西村 おっしゃる通りです。日本語や背景は理解できるかもしれないけれど、むしろ、わかったところでなんなんだ、という感じかもしれません。
阿部 たしかに探究の成功は嬉しいものだと思いますよ。けれども、それをやってしまって解釈のラインを実際の詩にベタっとくっつけてしまうと、もうその詩は読めなくなる。優れた詩というのは、何度でも多分新しいアプローチで読み直したい。つまり、消費をしないということです。それを作者が意図して書いているのかと言うと、おそらく作者もわかっていない。何がそう書かせているのかには、時代の問題とかいろんなことがある。だから詩について考えることって実は多いんですね。
西村 今のお話は学術研究のあり方につながります。例えば、ベルクソンを読むと、同じことを繰り返し書いていると思えてくる。その時に一つひとつの文字を読み込もうと思うと、なんか全然違うものが閃いたりもします。読書数をこなしたい自分と、深く読みたい自分の両方がいて、そういう本にどのように向き合っていくかは悩ましいです。
阿部 同じことばかり書いてあるじゃないかということは、僕も実はあって。それで僕は、現代思想のおいしいところをつまみ食いしている。著作間の微差や展開を読みきれていないのです。現代思想は、精読と乱読の間ぐらいの感じで読んだにすぎない。
独自の詩の形式が生まれるまで
西村 最後の質問ですが、阿部先生は今詩をつくることは好きなんですか?
阿部 僕は、妻が東京で仕事していて札幌赴任後は別居状態でした。それで一人暮らしの孤独を詩作の糧にした。それで詩を書きすぎていたぐらいになりました。ところが最近、妻が札幌にいることが多いので書けない日が多くて。たまに妻が仕事で東京に行くんですけど、その時に狙い打ちするように書いている。その意味では書きすぎていた詩が丁度いい頻度で書けるようになったといってもいいかもしれない。
西村 なるほど。
阿部 今書いている詩の型は、自分で書けなくなるように追い込む型なんです。
西村 それは今、ブログに書かれているのも同じですか?
阿部 同じです。今書いているのはトータルで12行。空きを入れると、全部で15行になります。それで1行の行脚が何字ぐらいとか、3行連を隣り合わせないとか、各連の行数が4 、2 、3だけに統一するとか、4連構成にするとかいろんな自己法則をつくっています。一種のソネット(14行詩)の変形みたいですが、つくってみたら瞬発的な力と、連が飛ぶ飛躍力が要求される。それでまさに「降りてくる」感じで詩がおりてきます。一度降りてきたら自分の責任において仕上げなくてはいけないので、何度も入れ替えるとか、語彙を変えるなどして12行書くのに1時間かけるという贅沢なことをして完成させています。これは評論の書き方とは全然違っている。詩はつくっては壊しつくっては壊しで、最初に思っていたことの痕跡が消えてしまっていることもある。でも、その詩作の時間が旅みたいな感覚で、それが好きで、その体感はからだに淡く残っていますね。
西村 最初に「見てもらう恥ずかしさがある」と言うお話も出ていましたが、詩をつくることが好きになっていますか?
阿部 好きになっているかはわからないですね。ただ、つくる頻度は年齢に応じて下げたい。今は2〜3週間に1編ぐらい、年間で25編から30編くらいは書いているんじゃないかな。これを一つの型にして、「きみも書いたらいいよ」とよく若い人に言うんですが、誰もやってくれないし、多分難しいんだと思う。
西村 今年の目標は、1編の詩を書くことなんです。今日は、詩は型から入ることもできるんだと思いました。
阿部 それは良いことですね。でも型から入るようにした場合、 もし次に別のものを書こうとすると多分反動が出るでしょうね。僕の場合、その反動を抑えています。今の形で100編近くあるので、もし見開きで詩集に載せてしまったら200ページ以上になる。だから西洋の詩集みたいに横書きにして、1ページ12行になるようにしようかなと。そんな詩集を誰かが「出しましょう」って言ってくれないかなと待っています。それもあって、100編にあまり近づけたくなくて、1個つくっては、前の詩を捨てようかなと考えたり。そうすると、実は詩集が締まってくるんです。
西村 今の形式っていうのは3行、4行、2行、3行?
阿部 最初が2行とか4行で始まる場合もありますよ。ちがう行数の連を並べるやりかたにはいくつかのヴァリエーションがあります。行が揃っていれば、誰かに歌にされてしまう可能性がありますが、それをなるべく拒絶し、詩篇として自立させたい。
西村 構成的な構造になっていないっていうことですね。
阿部 はい。たまたま、3...4...2...3行みたいなものを書いた時、この形がいいなと思って。自己模倣する形で、ずっと連作にしていったらどうかなと思ってやっていったら、本当に連作になっていったんです。しかも、丁度いい具合に1編をつくるのに苦労するのが良かったんですよね。
西村 試してみます。今年、何か1編でも書きたいなと思っていたので。
阿部 絶対に12行。3行が2つと、2行と4行だから足せば12行。このうち2行が難しい。瞬発力が要るから。でも楽しいですよ。パズルをつくっている感じはしないです。
西村 詩を読んでいてすごく身体性があるなと思ったので、それが興味を持ったところです。
阿部 そう言って頂けると嬉しいです。理路整然の理路という字があるでしょ。あれを壊している感じはありますね。
西村 ただ壊そうとしているだけではなくて、やはり出てこないとこの形としておさまらないと思うので。こういうものを書きたいです。今日はありがとうございました。
インタビューを終えて
いかがでしたか?インタビューの途中にある「読むものは読まれた瞬間に理解されていいのか」と言う言葉は、非常に印象的でした。というのも、私たちライターが書く取材をもとにした記事はわかりやすく、伝わらなければならないことが命題です。しかしわかりやすく書くことは1回読めば、2回目は読まれないかもしれない、つまり消費行為で終わってしまう懸念も含まれるということです。インターネットの発達に伴い、素人・プロに関わらずかつてないほど多くの文章が紡がれ、第三者に届く時代です。だからこそ、何度読まれても消費し尽くされない文章を書かなければと、気持ちを新たにした取材でした。
(ライター:ヘメンディンガー綾 インタビュアー:西村勇哉 編集者:増村江利子)
この記事は、本学と連携し、株式会社エッセンスが制作しています。
https://esse-sense.com/articles/105