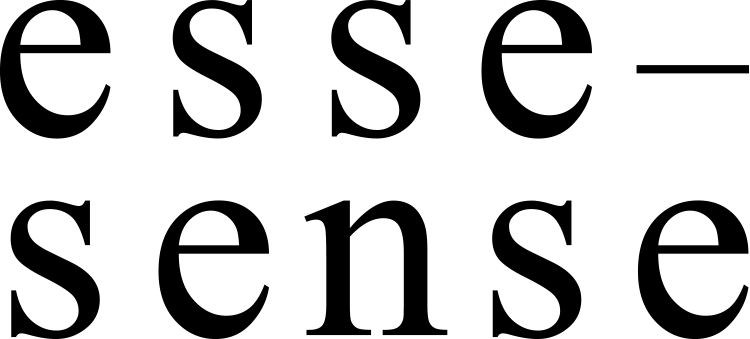リサーチタイムズとesse-sense(エッセンス)のコラボレーション記事をお届けします。esse-senseは、分野の垣根を超えた研究者たちのインタビュー記事を通して「あなたの未来を拓く」をコンセプトに、株式会社エッセンスが運営するウェブメディアです。本学の研究者たちにもスポットライトを当て、インタビュアーである西村勇哉氏(エッセンス 代表取締役)が、最先端の研究、そして研究者ならではのものの見方や捉え方に迫ります。ライターはヘメンディンガー綾氏が務めました。
小篠隆生さんは、ご自身が卒業した北海道大学のキャンパスマスタープラン作成をきっかけに研究者の道を歩み始めたユニークな研究者です。一般的に建築や設計と聞くと、どんな建物を建てるかにフォーカスすることをイメージしますが、小篠さんは建物の外側も含めた全体空間と、建物を取り巻く人々との関係性を考えることに主軸を置いておられます。建物は何十年と残り、景観をつくり、ひいてはその土地らしさを象徴するシンボルとなるもの。建物を中心に、そこに集う人によって建築が有機的に広がり、生かされていく様子を伺いました。

小篠隆生
北海道大学 大学院工学研究院 建築都市部門空間デザイン分野 准教授(当時)
一級建築士。1983年北海道大学工学部建築工学科卒、2006年から現職(当時)。専門は、キャンパス計画、都市計画、都市デザイン、建築計画。主な作品に、遠友学舎(2001年、日本建築学会北海道建築賞)、積丹町立余別小学校(2003年、文教施設協会賞)、東川町立東川小学校+地域交流センター(2014年、北の聲アート賞奨励賞、赤レンガ建築賞奨励賞、北海道建築賞、公共建築賞優秀賞)、東川小学校・地域交流センターとその周辺環境整備(2015年、アジア都市景観賞)。
建築の道を志したきっかけ
西村 小篠先生はなぜ建築の分野に進まれたのでしょうか?
小篠 最初から建築を目指すということがはっきりしていたわけではありません。高校の時に、ものをつくりたいなっていう意識が芽生えたんですが、ただつくるだけではなくて、人にそれを伝えて人と一緒に感動を分かち合いたい。そういう気持ちに目覚めたんですよね。そのきっかけは高校の文化祭です。自主映画を自分たちで撮ったりするうちに巻き込まれていったんです。映画づくりって様々な役割分担があって。演者、撮影、録音、音楽、美術、脚本。その中で美術周りを担当したんですが、それがすごくおもしろくて。そういう仕事をできないだろうかと考えて、芸術系の大学や、文系の大学で学ぶのも選択肢としてはあったんですが、やっぱりものを実際につくりたいと思って。それで建築に目覚めるんですよね。出身は東京なのですが、実家の周りには有名な建築がたくさんあって、それに普段から触れていたことが建築への気持ちを目覚めさせたと思います。
西村 何かをつくっていたりもしたんですか?
小篠 いや、絵を描いたりポスターをつくったりはしていましたけど、立体をつくったことはなかったですね。ものをつくりたいのと、いろんな人と協力しながらある方向にみんなをまとめていって、そこでなにかを形づくっていくプロジェクトがおもしろいのではないかと思ったのが最初だと思います。
西村 なるほど。もう大学に入った時には建築だと決めていました?
小篠 そうです。建築を学びたいから大学に行くという感じでしたね。
西村 実際に大学に入る時の建築ってどんな感じだったんですか?だいぶやりたいことに近かったのか。こういうこともあるかみたいな感覚なのか。
小篠 本来であれば、1年生から建築の科目がある大学に行くのが手っ取り早いんですが、北大は旧制の大学のシステムの名残が色濃くあって教養が1年半ぐらいあり、実際に建築に配属されるのは2年生の後期からだったんです。その間に当時工学部建築工学科教授の太田實先生がつくられたクラーク会館や百年記念館、北海道立近代美術館など北海道の建築を見て、建築の周辺を勉強するところから入っていきました。
西村 因みに、なぜ北大に行かれたんですか?
小篠 父が卒業生なんですよ、帝国大学時代の。
西村 なるほど。
小篠 東京出身なんですけど、第2次世界大戦前夜ぐらいまで北海道にいました。父の友人も北大の卒業生ばかり。家族旅行で北大のキャンパスを見に来たりしていたのが大きく影響したんじゃないかと思いますね。
西村 なるほど。東京から北海道だと、受験するだけでもすごい遠いので、珍しいですよね。北海道じゃないとできない研究分野もたくさんあると思うんですけど、建築だと東京でもできると思うので。
小篠 確かに、できますよね。しかし、北大で北海道という地域に建つ建築を学ぶようになって、首都圏東京の命題とはまったく違うものがあることを知ることになりました。
大学のキャンパスマスタープランに携わる
西村 寒冷地における建築といった話はあとで伺いたいのですが、その後どういう経緯で研究者の道を選ばれていったのかを伺いたいなと。
小篠 最初は研究者になろうと思っていませんでした。私は学部卒で大学院にも行ってないんです。設計をするということと、大学院に行くということは当時全然違っていると考えていました。私は早く実際の仕事をしたくて、東京の建設会社の計画・設計を専門に行う研究所に就職しました。
10年ぐらい仕事をして、恩師の小林英嗣先生から、「工学部の校舎を建て替える必要があるのだけど、大学内のスタッフでは計画をつくれないから、協力してくれないか」っていう話をいただいて。さらに工学部だけじゃなくて、「大学全体のキャンパスマスタープランもつくる必要がある。この2つをやるためには、実務経験のある君みたいな人が必要だ」と言われて。最初は、そのためだけに北大に来て計画や設計をするつもりでした。しかし、当時日本では、キャンパスマスタープランをつくった事例がなく、調査・研究をしないとマスタープランがつくれないということがわかり、それをやっているうちにおもしろくなりまして。キャンパスマスタープランの研究で学位もとって、ずるずると残ることにして今に至っているという。
西村 建て替えの時は、おそらくゼネコンの研究所とかにいらっしゃって、やりたかった実践の場にいたのではないかと思うんですが。それでも大学側に入った方がいいと思われたのはなぜでしょうか?
小篠 大学の外の企業として、このような計画・設計に関わる場合、やはり、常勤で現場に張り付かないと、打ち合わせもうまく進まないし、大学のニーズも汲み取れない。一方で、自分の出身校ですが、どういうふうに建物が使われているのかについて、そんなに知っていた訳ではないから、調査する必要もある。工学部の建物は、約10万平米ぐらいの面積があって、その中に数百人の先生と職員が働いていて、それに学生を入れるともっとすごい数になります。そんなところに外部のスタッフとして入っても、本音が聞けないんじゃないかなと思って、大学に在籍してやろうって思ったんです。
 北海道大学工学部の建て替えられた校舎
北海道大学工学部の建て替えられた校舎西村 工学部の建て替えとキャンパスのマスタープランはおもしろいと思えるテーマでもあったということでしょうか?
小篠 当時、キャンパスのマスタープランは、実は私立大にも国立大にも日本にはなかったんです。当時の文部省も、「計画はつくりなさい」と言ってましたが、その中身は実際には建物の配置図で「将来こういうふうにしたいね」ぐらいの将来計画という程度です。研究教育における将来像をハッキリさせて空間的なフレームを描いていく総合的なアカデミックプランと連動したキャンパスマスタープランは全くなかったので、非常におもしろいテーマだと思っていました。日本に事例がないので、海外の事例を調査することから研究の第一歩となりました。何をマスタープランの要素とすべきなのかがわからないので、それを研究のテーマとしました。最初の第一歩を踏み出すワクワク感が非常にありましたね。
西村 キャンパスマスタープランと、ただの配置計画の一番の大きな違いはどこでしょうか?
小篠 すごく簡単に言うと、どういう項目立てをするかという目次が全く違っているというところです。
西村 つまり、目指す目的が全然違うわけですね。
小篠 そうですね。北大の場合は、札幌キャンパスの建物の建っていない部分の面積の多さを重視しないといけない。北大は、建坪率が14%なんですよ。
西村 すごいな。ほとんど公園ですね。
 緑が目立つまるで街中のオアシスのような北海道大学
緑が目立つまるで街中のオアシスのような北海道大学小篠 まあそれは農場があるから顕著なのですが、国立大学の平均的な建坪率は20%台、東京の私立大学だと60%とかになっちゃうんですよ。
西村 私立大学だと、そもそもビルだけということもありますよね。
小篠 そうそう。北大はこのすごい面積のオープンスペースをどうしていくのかが、キャンパスマスタープランとして重要な命題になるので、単なる建物の配置計画と真逆なんですよね。建物をどう建てるかじゃなくて、建てない部分をどう残し、どう使うか。緑地とか生態系とか景観とか、道路とか広場といったパブリックスペースの計画、そういう項目が真っ先に計画要素として入ってくる。配置計画は建物の位置が主な計画要素なので、全く違うのです。
西村 昔は建てる場所のことは考えていたけど、それ以外はただ残ってる場所みたいな。
小篠 そうそう。残ってる空地に今度は違う建物をまた建てればいいねというぐらいの、そんな感じでやっていたんです。
原風景を取り戻すようなキャンパスマスタープランを作成
西村 科研の報告書で、大学は人材育成やプロジェクトを起こすといった形での地域貢献だけではなくて、関係や空間というフィジカルな面でも地域に対して貢献できると書かれていましたが、そのフィジカル面での地域貢献はどんなことがあるのか教えていただけますでしょうか?
小篠 最初にキャンパスマスタープラン96がつくられたのが1996年。日本初のキャンパスマスタープランと言ってもいいと思いますが、そこで残さくてはいけないものの一つに川がありました。学内に川が流れていたんですけど、当時は都市化によって川の水源が枯渇してしまったので干上がっていたんです。
札幌は豊平川(とよひらがわ)がつくった扇状地の上に都市ができあがっているので、湧き水が出る場所がたくさんあって、それが水源となり小川がたくさんあった。キャンパスの中にその川の水路が残っていたんですね。それを復活させたい、原風景を取り戻したいというのが長期的なマスタープランの大きな目標だったんです。川があったということは、北海道の場合はそこで鮭などの魚をとっていた先住民が暮らしていたということです。太古の歴史がある場所というものも含めて、再生を考えていく必要があるだろうと考えたわけです。
だけど、水道水をチョロチョロと流せばいいという話にはなりませんから「どうやって水を持ってくるの?」というということを考えると大きな話にもなるわけで。ですから、「キャンパスマスタープラン96」では実現できず、2代目の「キャンパスマスタープラン2006」の時にいよいよ実現できることになってくるんです。
当時は札幌市が、"水と緑のネットワーク計画"という計画をつくっていました。札幌市の北側にある中小河川の下流部の水質が、生活排水が流れ込んで非常に汚濁してしまっていました。それを改善させるためには河川の水位を上げるのが一番効果的だ、となった。問題は、どこから水を流してあげるのかということなのです。そのルートをいくつか考えようとしたけれども真ん中に札幌の中心部があって、都心部を突っ切って下流部に水を流さないと、中小河川まで水が通じない。都心部の地下に導水管を入れるとしたら、とんでもない土木工事が発生するのでコストがかかって実現性が低い。その時に、「川があった場所が北大にあるじゃないか」という話が出たんですよね。大学側も河川を復活させたいと言ったら、そこを使って水を流させてくれということで。キャンパスの中の旧河川に水を導水して、キャンパスの一番北側の部分から既存の河川に接続すればできる、となったんですよね。
では、キャンパスのところまでどうやって水を持ってくるのかという話ですが、札幌市の西側は小高い山で囲まれているんですが、藻岩山(もいわやま)という山に浄水場があって、その未処理水をもらって使われなくなった水道管で数キロ離れたキャンパスに水を持ってくる。その工事費と、さっき話した膨大な工事費とを比較したら全然違うよねという話になって、札幌市と協議して行うことになりました。ある種、Win-Winの状態が生まれて、川を復活させることができたんですね。
大学はキャンパスという空間で閉じてるのではなくて、社会に接続されているんだということが川の復活によって実践できた。キャンパスの川は単純に目で愛でるぐらいのものではなくて、都市施設として必要なものとしてキャンパスの中に存在しているという位置づけができたということになります。今、川が流れていることによって実は水辺の生態系が回復してきているということが、理学部や農学部の先生方の調査で明らかになってきています。NHKの番組でも紹介されていましたが、毎年カモの親子が子育てをしていますよ。
 自然が早期に回復する工法で復活した河川環境
自然が早期に回復する工法で復活した河川環境西村 すごいですね。地域における歴史的な背景を掘り起こしていくことで地域としての文脈に接続していったんですね。これが全く地域の文脈に関係なく、「ただカッコいい川をつくろうぜ」みたいな話だと地域の文脈にほとんど接続しないと思いますが。
小篠 そういうことですね。ですから、川の護岸はほぼ太古の昔から流れている状態を復元する形でコンクリート護岸は一切使わず、ヤシの繊維などで俵みたいな形をつくって川岸に埋めるという多自然川づくりの手法を採用しているんです。そうすると、ヤシ繊維の俵がポーラス(多孔質体)なのでそこに様々な種子が入ったり泥が付着して水辺の生態系が戻りやすく、そのうちだんだんそのネットも腐って、土に戻って固まっていくので護岸になっていくんです。
西村 最初のマスタープランから25年ほど経っていると思うんですけど、当時まだ計画だったもので、今は実現されてるものについても伺えますか?
小篠 学生やキャンパスを使う人の居場所づくりというテーマがあります。大学の人たちだけではなく、地域の人や来訪者も使えるようにインフォメーションセンターや総合博物館にはカフェが設置されたり、百年記念館の中の「北大マルシェ」で北大の牛乳でつくったチーズを食べることができたりしています。地域の観光案内にも掲載されるなど、こういった地域に開かれたものが実現しています。
 百年記念館の中の「北大マルシェCafé&Labo」では、北大構内で生産される北大牛乳と乳製品を楽しめる
百年記念館の中の「北大マルシェCafé&Labo」では、北大構内で生産される北大牛乳と乳製品を楽しめる西村 北大の博物館の中に、小さなミュージアムショップとカフェがありました。
小篠 ありますね。博物館のテーマに少し沿わせるような形で、オリジナルのメニューをいろいろと開発しています。
西村 そのカフェでコーヒーを飲みながら仕事をしていたら、突然横のセミナールームでサイエンスカフェが始まって研究者が喋り出したみたいなことがありました。
小篠 あそこはライブ感がある使われ方をしているので、おもしろいと思いますね。そういう意味では、交流の場所。北大の知と地域の人たちの接点で、交流が実現している場所です。
西村 人が参加することで知の交流をデザインして、それが広がって観光資源になっていく流れができていますが、最初のプランの段階ではどの辺りまでが計画の中にあったのでしょう。
小篠 知の交流や参加の話は当然計画に組み込まれていますが、観光は少し弊害もあるので難しい話ですね。芝生は夏場は非常に気持ちいいので、バーベキューをやりたくなるわけですよね。僕らもそうだったけど、北大はなにかというと外でバーベキューしながら飲むというという変な習慣があって。過去の話ですが、それを見た外部の人たちも、「こんなところでバーベキューできたら楽しい」とやるようになってしまって、ゴミやトイレの問題が出てきたんです。それで、全面的にバーベキューの禁止という話になってしまった。
OBの人たちは「いや、それが北大の伝統だ」とむしろ擁護するような人たちもいたりして。コロナの蔓延直前までは場所を限定して、用具は生協でキットを貸しているのでそれを使うようにして学内の人たちは可能にしました。そういう意味で野放図に観光という話ではなくて。北大のずっと守り続けてきた風景とか、そういう資源を愛でていただくのであれば良いし、そこに蓄積されている知の資源を体感するのであれば、それは構わないのだけど。節度ある楽しみ方をしていただくために禁止する行為もあるというように落ち着いています。
大学は、都市にあるべきもの
西村 都市における大学の役割は、レクリエーションのスペースの提供ではないということですね。先生は都市型の大学と、あと大学都市と、あと郊外学園都市の違いの研究もされていて。都市における大学の役割は、郊外学園都市とは全く違うと思うんですが、どういったところに役割があるのでしょうか?
小篠 今言われたのは都市と大学との関係ということになると思いますが、そもそも大学は都市に立地していないとだめだと思っているんです。高度成長期に関西圏と首都圏だけに適用された法律ですが、工場等制限法という工場のような大きな敷地を持つ施設は都心部には立地できないと定めた法律があったんです。この法律のために新しくキャンパスの新設や拡張することができなくなってしまったので、例えば、東京のお茶の水にあった中央大学をはじめ多くの大学が八王子などの郊外部に移転した。今は工場等制限法は撤廃されて、結局大学が都市に戻ってくる回帰現象が起こっています。
西村 そうですよね。
小篠 なぜかというと、丘陵地の山の上にキャンパスだけがあっても、大学における生活は単純に授業を受けて帰るというのではなくて、キャンパスの内外での人と人の交流が必要なわけですよね。自分の研究や学ぶことに触発を受けて、それが展開するのが大学であって、決められたカリキュラムを修めて単位を取るだけではない。単位化はされてないけど、自分の思想の形成には非常に重要な役割を果たす交流が必要なんですよね。そこに都市というものが大きく関わっている。そういうことが大学の形成史を研究するとわかってきます。
ベルギーのルーヴァン・カトリック大学を例に出しますが、ベルギーって地域によって公用語が違ってるんです。ワロン語とフランス語を話す地域がある。この大学があるルーヴァンというまちは、ワロン語が公用語になりかけたんですが、自分たちの研究はワロン語ではできないから、大学をフランス語圏の郊外のまちに移転させようという話になったんです。それでキャンパスの施設だけをつくるのではなく、まちごと大学と一緒に引っ越してルーヴァン・ラ・ヌーヴ(新しいルーヴァンという意味)というまちができました。
ヘメンディンガー 具体的には、まちのどの機能が移転したということなんでしょうか?
小篠 移転して元のまちがなくなったというわけではありません。実際には、3万人規模のまちをつくろうとしていましたから、駅の整備など交通インフラも必要で。それに大学と大学に関連した研究所や企業、そこに働く人々のための住宅、商業、それから基本的な社会サービス機能と行政機能の一部などです。つまり、まちの機能を新しくつくったのです。
ヘメンディンガー 学生寮だけではなくて一般の方の住宅ですか。
小篠 そうです。キャンパスの中に学生寮と一般の人が住む混在型の住居施設が建てられていて、一般の人たちも住んでいます。また、戸建ての住宅街もあります。鉄道で20分ぐらいでブリュッセルに行けるぐらいの距離ですので通勤圏にもなり得るということで、大学があって学生たちもいて、さまざまな活動がされているまちであれば、そっちに住んでもいいんじゃないかと思う人もたくさんいることになりますね。
ヘメンディンガー この大学はパブリック(公立)の大学ですか?
小篠 プライベート(私立)の大学で母体はキリスト教の大学ですね。大学が行政や鉄道事業者と組んでお金を出して。土地を長期ローン(100年)で取得したり、建物を建ててレンタルをして、デベロッパーを入れながら開発をしていきました。最初に私が行った時は、30年ほど前で、本当にまちができるの?という感じでしたが、5〜6年前に行った時はもう激変していて完全なまちになっていました。「まちが必要だ」というのはすごくよくわかるけれど、中心部にある建物は下は商店で上に教室や研究室があるというつくり方になっているので、どこからキャンパスが始まるかも、見ていてもわからないくらいまちと大学が一体化しています。
 商店や住宅が並ぶルーヴァン・ラ・ヌーヴの様子
商店や住宅が並ぶルーヴァン・ラ・ヌーヴの様子西村 すごい。
小篠 おもしろいですよ。「こうじゃないとだめだ」というのが彼らの主張ですからね。
西村 「それがいいよね」じゃなくて、そうじゃないと研究者としてやっていけないということですよね。以前関西大学の総合情報学部で教えていた時に、教えていたのがメディア論だったのでフィールドワークに行くんですが、キャンパスが山の上にあるので、フィールドワークのために山を降りるだけで1限が終わるんですよ。3限連続でやっても1時間半しかフィールドワークができない。学生のアンケートで「常に山から降ろしてほしい」と言われました。もちろん静かだし、すごく広いし、きれいなキャンパスなんですが、これは厳しいなと思いました。まちごとくっつけて動くのはすごいですね。ついて行くまちの人たちもすごい。都市がないとインスピレーションや、学びのもとが成立しないということですね。
小篠 そうですね。大阪大学は大阪外国語大学といっしょになり、最近箕面(みのお)に新しいキャンパスをつくったんです。その時に、大阪大学と箕面市とが連携をして大学が指定管理者となって市立図書館と大学附属図書館を複合化させ、キャンパスの中に誘導したんです。大学の蔵書と、市立図書館の蔵書が混ざっていて、大学の蔵書の書庫にも行けて閲覧することも可能。その横には区民センターも劇場ホールもある。ルーヴァン・ラ・ヌーヴとはスケールが異なりますがまちと大学が一緒になっている発想は洋の東西を問わずあると思いました。
西村 都心部でも、大きな駅の周辺でビルがサテライトキャンパスになっている大学がありますが、ちょっと切り離してしまっていますよね。本来の趣旨から言えばもっと町中に溶け込むような形でつくって、隣でタコ焼き屋さんがタコ焼きを売ってる、みたいな光景があってもおもしろいですよね。
小篠 新築でやることの限界がありますね。むしろ、衰退しかけたり、空き家や空店舗が出てしまってるところに、大学のサテライトを挿入するやり方の方が正解かなと思います。
西村 同志社大学が町中の町屋を借りてサテライトキャンパスをつくっているんですが、そういうのはおもしろいですね。
小篠 京都には結構たくさんあります。京都女子大学が、鉾町(ほこまち)の中心部の大きな町屋の管理をやりながらサテライトキャンパスにしています。
西村 友人が慶應大学で大学の前にある三田商店街の中の民家を借りてそこで授業をする"三田の家"を運営してたんですが、日替わりでいろんな先生がそこで授業をして、学生たちも授業をしてみたり。「住民も授業に参加していいよ」みたいな。ビールサーバーもあるからビールも出るんですね。大家さんが亡くなられて2年前に閉じましたが、すごくおもしろかったですね。
大学がまちにあるからできること
西村 今のお話は、リビングラボラトリの研究をされていらっしゃることとつながってくるのかなと。
小篠 そうですね。先ほどの話と関連づけて言えば、リビングラボ研究につながる研究として、コミュニティのハブに関する研究をやっておりまして『 「地区の家」と「屋根のある広場」―イタリア発・公共建築のつくりかた』(鹿島出版会)という書籍を出版しています。この中の「地区の家」が三田の例と似ています。地区の家はイタリアのトリノを中心に展開しているんですが、トリノ工科大学のキャンパスの目の前の地区がちょっと疲弊してしまって。それをなんとか立て直すために、大学院生や様々な専門分野の若手が立ち上がり、地域の住民と協働して、まちの人々に必要なニーズを実現するために創った拠点なんですよ。
最初に地区改善事務所という形で、学生を含むグループが元ケーキ屋さんの店舗を借りてよろず相談所的なものを始めるんです。すると地域の人たちが集まっていろいろと課題を言い合ってくれる。それをまとめて市に持ち込むんですが、市は全然お金がなくて対応してくれない。ちなみに、イタリアはたいてい行政にお金はありませんからそういう話にはならない。
しかし携帯電話のボーダフォンが財団を持っていて、財団の地域活動に対してのファンドに応募したら採用されたんですね。ボーダフォンが「俺たちは金を出すけど、市が何もしないのはおかしな話だ」という条件をつけ、トリノ市が協力をしてくれることになりました。この地区は18世紀ぐらいに建てられたアパートメントがたくさんある非常に古い地域で、シャワーもないアパートが多く、地区には日本の銭湯のような施設があった。歴史的建造物でもあったその施設を改造して地区の家にしました。それが波及して、現在トリノには10軒ほどの「地区の家」があります。
「地区の家」は大学の関係者が絡んではいますが、大学のためにやっているのではありません。その地域には移民の人たちがたくさんいるんです。移民の人たちを、どうやってイタリア社会に溶け込ませることができるかを考え、親が子どもたちを預けてイタリア語を学ぶコースをつくったり、履歴書の作成が難しい人には代筆してあげたり。地域活動も、音楽教室やヨガ、ダンス、自分の出身地域の文化を発信するなど、すごく幅が広いんですよね。社会課題を解決するような活動から、地域の一般的な活動まであるし、プライベートな誕生日パーティだってできる。本当にみんなの使える家になっている。さらにカフェは大人は千円ぐらいでワンプレートとグラスワインが飲めるようになっています。ずっとそこにいることができる居心地のよい場所ができました。私が初めて地区の家を訪れたのはトリノ工科大学と北大が提携して行っていたサマースクールの時です。その時、地区の家を紹介されて「これはおもしろい」と直感したのですが、まさにこれがリビングラボだということにも気がつきました。これがリビングラボ研究というテーマになった経緯です。
西村 おもしろい。先ほどの「三田の家」の兄弟で「芝の家」があるんです。マンションの1階のフロアを港区役所が借り上げて、それを坂倉杏介先生が10年間運営しています。「芝の家」がなくなりかける時に、みんなで「芝の家2(ツー)」をつくろうという話になって、移転の間に家を閉じたくないので、近くの広場、空き地を使ってみんなで「野外芝の家」を3ヵ月ぐらいやっていたんです。そもそも「芝の家」は何かをする場所でもない。イベントなどもやっていなくて。みんながなんとなくいろんなことをやっていると、それがちょっとイベントっぽくなったりするみたいな。
その板倉先生が、都市大学の近くのおやまち商店街で商店街の人と一緒になって、学生たちと一緒にイノベーションをしたり、散髪屋さんの目の前で公開ゼミをホコ天でやってたりして。もうなんかグジャグジャなんで説明できないんですけどおもしろいんですよ。
小篠 それがさっき出た大学と都市の融合が実践されている例ですよね。サテライトキャンパスと言わないで、大学と都市が融合することで都市に居住されている方々の活動と大学の研究活動がマッチングしていく感じがしますよね。
西村 そうですね。大学は都市の中じゃないとだめで、その都市で何が起こっているんだろうみたいなところから、みんなの家みたいな話になって今度は大学にもフィードバックが入る。
小篠 そうですね、当然そうなってくると思いますね。このような活動と成果が大学に戻ってきた時に、今度は地域をサポートする組織やサービスを、大学の方でも知恵を使って立ち上げるところが出てくるかもしれないですね。
西村 なるほど。
小篠 だから、大学にフィードバックした時には、地区の家の活動とはまたちょっと違ってきています。大学の知を使って、もっと新しいことを地域の中に実装化して課題解決していきましょうという話になっていくことになると思うので。
西村 リビングラボって、日本では地域側であったり企業がやっていたりすることが多いと思いますが、大学が積極的にやる意味がある。それも大学は都市がないと成立しないという話からすごくスムーズにつながるなと思います。大学が「地区の家」みたいな取り組みに展開していくと、例えば京都では本当におもしろくなるなと思います。
小篠 そうですね。京都の場合だと、ご承知の通り祇園祭りをやるために鉾町があって。その鉾を保存し、伝統をどうやって継いでいくかっていうのは、鉾町の町衆だけではできなくなってきているという現実がある。でもそこにある町屋の管理を大学に委託したら、関係しているゼミの学生も「半分鉾町にいるんだからじゃあ手伝ってね」というのができるようになったり。あの辺は祇園祭で一年中動いていますから、そういうコミュニティを存続させることに大学が寄与するっていうこともありますよね。
大学がないまちでも大学ができること
西村 すごくおもしろいですね。小篠先生が設計をされた東川小学校・地域交流センターの話も聞かせてください。東川町は大学がないまちですよね。大学がないまちでもできることがあるのが、この東川町の話なのかなと。東川町で手掛けられた時に気をつけられたことや、「交流センターはこういうふうにしなきゃいけないんじゃないか」と考えられたことを教えていただければと。
小篠 建物を計画して設計してつくって終わりというやり方では、地域の人たちに信用されて、お互いにコラボレーションする状況をつくるのは難しいんですよ。「どうせ外の人でしょ」と心の底では思っていて。なかなか本音を話してくれないですね。東川では最初は建築のプロジェクトから入っていきましたが、その間に、地域の人たちとの交流をアンダーグラウンドで個人的にやっていたんです。「そろそろあんた、ここに家でも建てなさい」って言われるぐらいにならないと話をしてもらえないことがある。
大学も僕もお金がないと動けないわけですから、興味本位でただやればいいのではなく、大学では研究という仕事として関わる必要がありますよね。しかし、建築の計画・設計というと一般的には時限つきなんです。例えば、「小学校を建て替えたいので計画をつくってね」とか、「設計をしてね」って。それではその計画や設計が終われば、関わりも終わってしまうのが問題です。それだと設計事務所だとか、コンサルタントと同じになってしまうんです。違いをつくるためには委託されたプロジェクトが終わっても関わり続ける、そういう状況をつくれるかどうか。「建築が建ったあともそこにいる」という状況をつくらないと地域の人は本当の本音で話をしてくれないのです。
西村 そうすると、「仕事として行くんだ」と前提があるけれども、仕事は別にいつなくなっても構わないというか。
小篠 そうですね。仕事の範疇を決めないってことですね。「仕事として受けてるのはこれだけなんだけど、こっちもやっているよ」という状態にしちゃうということです。すると、さまざまなことがわかっていく。同じようにプロジェクトに取り組んでもこういう理由でうまくいかないんだなとか、いろんなことが見えてくるんです。そっちを解いていかないと、こっちの本当に受けてる仕事が解けないことがわかってきたり。
東川小学校・地域交流センターは小学校に地域交流センターが複合していることで、学童保育などの放課後の子どもたちの教育を、東川町がバックアップしています。ボランティアの人たちも結構たくさんいらっしゃって、子どもたちの放課後を面倒見てあげたり、環境教育として農家の若手が米づくりの体験学習をやったりとか。竣工から7年経ちましたが、2年前に冒険遊び場をさらにバージョンアップしたいという話があり、遊びに来た子どもと親の居場所として東屋を設計、建築しました。これは完全に仕事ではないです。設計料もいただいてなければ何もない中で、冒険遊び場の方向性を示した基本構想から実施設計をやり、現場監理までやっています。
西村 「ここで何をしたら良いか」がわからないといけない。その中に、仕事の範疇外のものが入ってきてもなるべく積極的に関わって、結果的にそれが元々の仕事も良くしてくれるということですね。
小篠 おっしゃるとおりですね。
西村 それは大学と都市の関係にも少し似ていますね。ちょっと染み出しておかないと循環が始まらない。
小篠 そのとおりなんですよ。その辺のところをやれるかどうかが、地域に入る時の重要なポイントかなと思っていて、実践するようにしています。
西村 なるほど。前半ずっとお話を伺っていたキャンパスのあり方の話がそのまま割と地域の中の建築の話にも見られますね。
小篠 そうですね。
西村 いい空間のあり方ってなんだろうと考えた時に、良いキャンパスのあり方と似たところがあって、キャンパスはそれをすごくわかりやすく象徴的に見せてるものなのかなと思いました。
小篠 そうですね。東屋がどんな建物なのか、少しご紹介しましょう。屋根は透明のポリカーボネートで他の主要部は木造です。普通の住宅をつくる時に使われる120角の在来流通材で全部できあがっています。構造的には在来の木造工法だと筋交い(すじかい)が入りますが、そういったものは一切入れなくても構造的に持つような工夫をして、東川の風景が透過してくるようにつくっています。バーベキューができるかまどがついているのでその周りは耐火壁にして、漆喰を塗った上に学生たちに下絵を描いてもらって、木の葉を子どもたちみんなで描きました。
西村 雪が降っても大丈夫なんですか?
小篠 雪にも耐えられるような強度を持った折半屋根になっています。
 子どもたちの遊び場として新たに設計・建築された東屋
子どもたちの遊び場として新たに設計・建築された東屋西村 これで大丈夫なんだ、すごいですね。東川町の人たちはお得だなぁ。
小篠 タダでやっていますからね(笑)。今までの話をつなげていくと、やっぱり居場所づくりというのがキーワードかなと。東川町がまちづくりで "適疎(てきそ)=過疎でもなければ過密でもない"っていうワードを使ってるんです。都市化が起きて都市に人口流入があった時に地方では過疎地域ができます。過疎の対義語が過密です。でもその中間があっていいんじゃないかということで、適切な疎を「適疎」と呼んでいます。70年代後半ぐらいに主に農村計画学会で語られていた言葉ですが、それを東川町長が見つけて、適疎なまちづくりをスローガンにまちづくりをやっているのです。僕らにしてみれば都市計画的に適疎空間ってどういう空間なのかを実体化しておかないと、という思いもあって、それを明らかにするために東屋もつくりますが、研究もしています。
この「疎で構わない」という価値観は、アフターコロナにリンクしているんですよね。暮らしの価値を何に見出しているのか。そこを明らかにしたいなと思っていまして、街の中心市街地でアンケート調査をして、人々の意識と、活動の実態を把握し、一方で、物理的な空間の構成を調査し、それらを掛け合わせると、適疎な状態はこういう状態だと言えるんではないだろうか。そういうことを明らかにしようとしているのが一番最近の研究です。キャンパスの計画で知った外部空間と建築との関係に興味の対象がずっとあり続けて、それがあるので今、適疎というメカニズムを明らかにしようとしているのかなと思います。
西村 ありがとうございます。東川町は写真でまちづくりを行なっていますが、「風景を残そう」というのは、この時代においては最先端だと思うんですよね。なので、そういう時代の先を行くコンセプトでまちをつくっていくといろんな人たちがそこに関わっていくんだなと。
小篠 そうですね。
西村 きっと小篠先生が「東川町だったらやってもおもしろいんじゃないか。きっと意味あるんじゃないか」と思われたから東屋までつくられたと思うんですね。そういう意味では、どういう住民が住んでいて、誰が集まってきてるのかということと、実際にまちにおこっていくことが密接につながっているんだなと感じました。
小篠 そうですね。小学校・地域交流センターはつくってから7年ほど経つんです。校長先生は代々替わっていきますけど、それぞれお会いしていろいろとお話をしていますし、地域交流センターで、子どもの遊びも含めた教育を支援する活動を続けている人は、最初からずっと変わらないので、彼らの「こういう東川らしい教育をやりたいんだよね」という思いをなんとか実現してあげたいとずっと思っています。ですから、建築設計をやる前につくる基本構想・基本計画の時からどういう教育を東川町はやっていくべきなのかをずっと話し合いながらまとめてきたことが、今でもさらにバージョンアップされているのです。
西村 伺っていて改めて東川町に行きたくなりました。今日はありがとうございました。
インタビューを終えて
建物は内と外を明確に分けるものではありますが、その両者をつなぐのが建物を利用する人。小篠先生が手掛けられた北大のキャンパスマスタープランの例を見ていても、建物が時間をかけて人を育み、ひいては地域の文化をじっくりと醸成している様子が伺えました。消費されやがて取り壊されてしまう「箱」ではなく、まさに大地に根差すような建築が増える景色を見たいと思いました。
(ライター:ヘメンディンガー綾 インタビュアー:西村勇哉 編集者:増村江利子)
この記事は、本学と連携し、株式会社エッセンスが制作しています。
https://esse-sense.com/articles/59