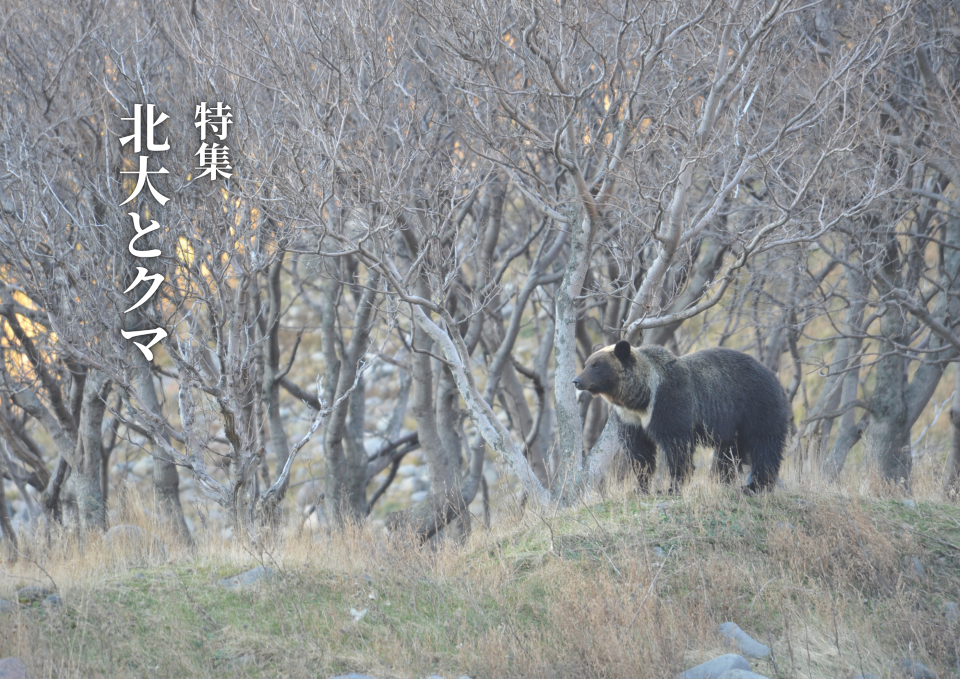<写真>アイツバマイゆふ特任准教授(撮影:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香)
北海道大学環境健康科学研究教育センター(CEHS)のアイツバマイゆふ特任准教授は、化学物質などの環境要因と子どもの健康に関する研究を行っています。アイツバマイさんの研究チームは長期にわたる出生コーホート調査のデータに基づき、妊娠中の母親の室内環境が小児湿疹に影響する可能性があることを明らかにしました。
「子どもが1日の大半を過ごす室内の環境が、喘息やアレルギーなど、子どもの健康のリスクになることは知られています。しかし、子どもが生まれる前の妊娠中の室内環境が生後の皮膚トラブル、特に湿疹のリスクに影響するかどうかについては、ほとんど研究がありませんでした。私たちは、子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)の質問票調査(アンケート)で集めたデータを分析し、この研究課題を探求しました。」とアイツバマイさんは言います。
エコチル調査は、環境省による大規模な国家プロジェクトです。国立環境研究所のコアセンターがプロジェクトを統括しています。アイツバマイさんが所属する環境健康科学研究教育センターは、北海道(札幌、旭川、北見)の調査を推進する北海道ユニットセンターとして、その他全国に14機関あるユニットセンターと共に調査を推進しています。2011年に妊婦の参加登録を開始したエコチル調査では、2014年までに全国で約10万人の妊婦が参加し、その後生まれてきた子どもと母親(母子ペア)を追跡しています。この研究の強みは、その豊富なサンプル数と詳細な情報量にあります。
保護者はアンケートを通じて、子どもの湿疹に関連する症状、参加者の基本的な特徴(年齢、子どもの性別、親のアレルギー歴など)、および室内環境(住宅の種類、建物の築年数、住宅の素材、掃除習慣、室内のカビの発生など)について答えました。合計で、1.5歳児をもつ71,883組の母子ペアと、3歳児をもつ58,639組の母子ペアが回答しました。アイツバマイさんの研究チームは、収集したデータを統計的手法を用いて分析しました。その結果、妊娠中の室内環境要因と湿疹のリスクとの間には、特にカビの発生があるほど湿疹のリスクが高くなることが示されました。
その他、妊娠中の住宅の床材について調べたところ、合板フローリングの床材(木板を貼り合わせた床材)の方が、畳よりも小児湿疹のリスクが高いことも明らかになりました。日本の住宅では、圧縮された木材を重ねて使用した床材が一般的です。アイツバマイさんは、このタイプの床材には、木材を接着するための接着剤等に含まれるフタル酸エステルや、光沢剤や難燃剤として使用されるリン酸トリエステル類などの合成化学物質が含まれていることを指摘しました。
 木製の合板フローリング床材には、接着剤、コーティング、難燃剤などのためにさまざまな種類の合成化学物質が使用されているという。 (写真: Dusan Petkovic/Shutterstock)
木製の合板フローリング床材には、接着剤、コーティング、難燃剤などのためにさまざまな種類の合成化学物質が使用されているという。 (写真: Dusan Petkovic/Shutterstock)
アイツバマイさんは、別のコーホート研究、『北海道スタディ』についても話してくれました。この研究では、特に住宅内のハウスダストとフタル酸エステルおよびリン酸トリエステル類の尿中代謝物を分析しました。ハウスダストの濃度と尿中代謝物の濃度との間に高い相関関係が認められたことから、これらの物質はハウスダストを通じて体内に取り込まれる可能性がある、と説明しました。さらに、北海道スタディでは、ハウスダストに含まれるこれらの合成化学物質の濃度が高いほど湿疹のリスクが高まることが報告されています。エコチル調査のアンケートを基にしたコーホート研究と同様に北海道スタディでも、妊娠中の住宅環境と小児湿疹の発症との間に相関関係があることを指摘しています。
北海道スタディは、2002年に始まった北海道全体を対象とした長期的な出生コーホート研究で、CEHSが主導しています。この研究では、地域の医療機関や北海道の住民と緊密に連携しています。北海道スタディとエコチル調査の開始時期は、約10年間の開きがありますが、どちらも共通の目的を持っています。それは、生活習慣を含む身の回りの環境要因が健康にどのように影響するかを理解することです。この目的を達成するために、リソースを共有し、互いの研究を支援しながら進めています。
 環境健康科学研究教育センターの実験室で血液および尿サンプル中の化学物質を分析するために使用する機器を紹介するアイツバマイさん。(撮影:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香)
環境健康科学研究教育センターの実験室で血液および尿サンプル中の化学物質を分析するために使用する機器を紹介するアイツバマイさん。(撮影:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香)CEHSでは、研究の実践だけではなく、研究結果をさまざまな取り組みを通じて社会やステークホルダーに還元することに尽力しています。昨年度は、8~9月に北海道大学総合博物館が主催した「北大の探求心2024」での展示会に参加しました。北海道スタディやエコチル調査の成果として、環境が健康に与える影響について来場者が学べる情報コーナーを設置しました。子ども向けのインタラクティブな学習資料も用意するなど、地域社会における健康教育の推進にも力を入れています。
アイツバマイさんは、「CEHSでは、年に1回または2回、環境と健康に関するさまざまなテーマで公開講座やセミナーを開催しています。北海道スタディの参加者さんに、20年以上も継続的に参加してもらうためには、長期的な関わりを維持することが重要です。そのため、単にアンケートを送るだけでなく、ニュースレターなどの資料を通じて、研究の進展や成果も共有しています。」と説明しました。



展示会は2024年8月30日から9月29日まで、北海道大学総合博物館で開催されました。(撮影:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 Aprilia Agatha Gunawan)
身の回りの化学物質に関連する健康リスクを考える際、アイツバマイさんは、完全に「ゼロ・ケミカル」のライフスタイルを実現することや、完璧に清潔な家を維持することは不可能であると強調します。
「むしろ、より実用的で効率的な掃除方法に焦点を当てる方が良いアプローチです。例えば、床を広く軽く掃除するのではなく、カーペットなど埃の溜まりやすい場所を念入りに掃除することをお勧めします。また、普段使用している製品にどのような化学物質が使用されているかを知ることも重要です。それによって、選択肢があれば自分で製品を選ぶことができます。また、意外と守られていないのが、正しい使い方をすることです。以上のことを念頭において生活することで製品からの化学物質の過度な取り込みを防ぐことができるのではと考えています。これらは全て当たり前のことですが、過度に心配しすぎるのは良くないと思います。それでは生活が大変になってしまいますから。」
この記事の原文は英文です(Spotlight on Research: Environment during pregnancy and the risk of childhood eczema | Hokkaido University)
【再編:広報・コミュニケーション部門 Aprilia Agatha Gunawan】