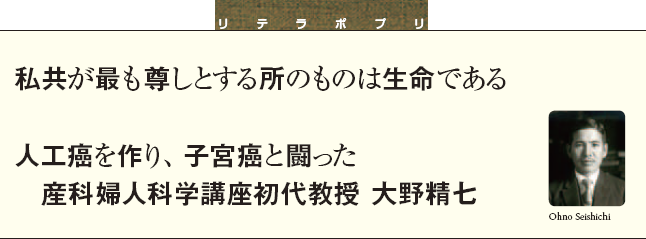大野精七(1885-1982)は、茨城県生板村に生まれた。生家は農業を営んでいたが、大野は臨床医を志して12歳で単身上京し、独逸学協会学校中学校、第一高等学校へと進学した。
▼「私共が最も尊しとする所のものは生命であつて、次は名誉、其次は財産でありませう。随つて人間の最大幸福は健康であると思ひます」(「祝辞」『香蘭』創刊号、北海道帝国大学医学部附属医院看護婦香蘭会、1931年、1頁)
1908年、東京帝国大学医科大学に入学後、産科婦人科教室に籍を置いた大野精七は、大学病院の外来に、子宮癌の患者が後を絶たない状況に直面した。
▼「私は始め産婦人科教室に這入つたが、臨床医家として立つにはどうしても病理学の必要なる事を痛感致し、特にお願ひして病理教室の人となつたのである」(『東京帝国大学病理学教室50年史』下巻、1938年、357頁)
産婦人科医として子宮癌の早期発見につなげるため、大野精七は、1914年9月から病理学教室の山極勝三郎教授に師事し、人工癌の発生研究に取り組んだ。
▼「私どもの実験材料はニワトリでありまして……[輸卵管が直に見える部位ではないので]すべて開腹をしてやつたのであります。実験部位の検査が開腹であつたということが……非常に困難でありました。十分注意をして消毒してやりましたけれども、癒着性の腹膜炎を起こしやすいのです。動物をなるべく長く生存せしめる必要があるので、したがつて注射試験は厳重なる消毒のもとに大体1カ月~2カ月以上の間隔をおいてやらねばならぬということがございました」(『癌の臨床』11巻13号、1965年12月、858頁。[ ]は補記、以下同様)
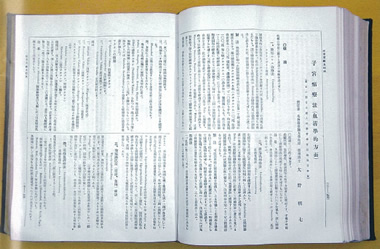
第26回日本婦人科学会総会での宿題報告(1928年3月31日)
子宮癌治療の技術改良のため、大野精七は「子宮癌療法(血清学的方面)」の担当者として学会報告をした(『東京医事新誌』第2570号、1928年5月、26~27頁)
このような煩雑な実験操作を、大野精七は、1917年まで約3年間も取り組んだ。41羽に施した実験から、大野は、遂に、3羽に人工的癌腫瘍を発生させることに成功した。
癌の病理学的研究に一区切りをつけた大野精七は、外科学教室で臨床研究を積んだ後、1917年9月に産婦人科学教室に戻った。
▼「東大産婦人科教室に入り、専門医になるべく勉強していたが、大正9[1920]年の中頃北海道帝国大学総長、佐藤昌介先生が教室主任磐瀬雄一先生を訪ねて、私を新設北大医学部産婦人科教授に懇望して来られた。私は東京で開業する積りであったが、磐瀬教授始め白木先輩その他からすすめられ遂に札幌行きを承諾した」(『北大医学部50年史』1974年、372頁)
産婦人科医として開業間近まで準備を進めていた大野精七は、北海道帝国大学からの招請を承諾し、約2年間のドイツ留学を経て、1924年4月、産科婦人科学講座の初代教授に就任した。そして札幌の地で、再び子宮癌の問題に挑んだ。
▼「子宮癌は早期に発見し、根本的全剔出手術をほどこせば効果的である。私は北海道の婦人のため「子宮癌の話」と云う理解し易い小冊子を作って一般大衆の啓蒙に努めた。癌の治療法として手術あるいは放射線療法の外に何か血清学的方面に治療法を見出さんと考えた……昭和4[1929]年より卵巣の乳腺下移植を試みた……私の卵巣移植の主なる目的は子宮癌のため子宮並びに附属器を全剔出した患者の欠落症状を防ぐため、患者自身の卵巣をその乳腺下に移植したのであった」(前掲『北大医学部50年史』373頁)

健康保持の秘訣は、スキー(1920年代後半、手稲山にて)
大野精七(左から5番目)は、健康法として体育を奨励し、スキーの普及にも邁進した(大学文書館蔵)
大野精七は、子宮癌患者を救うため、卵巣の乳腺下移植に関する研究や血清学的研究に取り組む傍ら、附属医院で産婦人科患者の診療を行い、夜間・急患の手術も厭わず自ら執刀して、治療にも尽力した。
▼「当時、大学病院の外来診察は午前のみで午後及び夜間に時間外診察を乞う者が多かったので、私は病院通用門の南側に急患用時間外、外来診察所をつく[った]」(前掲『北大医学部50年史』373頁)
1948年3月、大野精七は「子宮癌研究の思い出」等を最終講義に北大を退官し、その後、札幌医科大学・東日本学園大学の初代学長を歴任した。
1982年12月30日に、97歳の天寿をまっとうした大野精七は、門下生に次の言葉を遺している。
▼「もし元気になれたら、もう一度世の中のために働きたいよ」(『光雪とともに 教室開講60周年記念誌』1985年、78頁)
大学文書館 山本美穂子
Yamamoto Mihoko