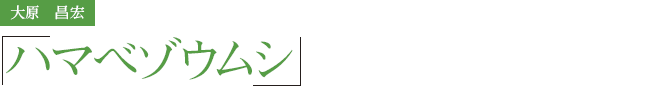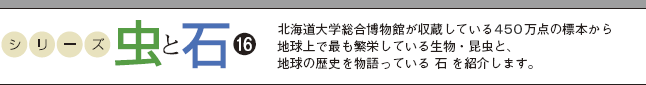
 ヒョウタンゴミムシ
ヒョウタンゴミムシ
 ハマヒョウタンゴミムシダマシ
ハマヒョウタンゴミムシダマシ
 ハマベゾウムシ
ハマベゾウムシ
陸前高田市立博物館は、東日本大震災で発生した32メートルの津波を受け壊滅した。館職員は亡くなり、収蔵資料も甚大な被害を受けた。展示物や人文系資料は流されたが、自然史標本は残った。自然史系収蔵庫の入口は一カ所で、そこに棚が集中し、標本は引潮で流されるのを免れた。密室に津波がよせ、室内には数トンの圧がかかったと予想される。昆虫標本箱のガラスはゆがみ、箱内の標本の昆虫針がくの字に曲がった。標本は海水とヘドロを被り、救出された時は腐敗状態であった。
◆
これらの標本の復旧に全国の博物館が援助を申し出て、北大総合博物館も化石、植物、昆虫分野で標本レスキューに参加した。昆虫分野で受け持ったのは1001個体の甲虫の標本。海水を浴びた標本を、脱塩、殺菌処理をし、学術標本として研究に使用できるように作り直す。腐敗し、バラバラになった体の部位をひとつずつ糊で台紙に貼付け、元の状態に近い形に修復する。
写真は、陸前高田市の名勝「高田松原」の浜で採集されたハマベゾウムシ Aphela gotoi。海水で育つアマモを食べる代表的海浜甲虫である。ハマヒョウタンゴミムシダマシ Idisia ornata、ヒョウタンゴミムシ Scarites aterrimus、みな高田松原の浜で採集されたものである。
◆
高田松原は、砂が津波で流され浜自体がほぼ消失。これらのハマベゾウムシは生き残ったとしても近隣のアマモのある浜までたどり着けなければ子孫は残せない。では、高田松原の近くにアマモの残された浜はあるのか。戦後の開発で多くの浜は自然状態を呈しておらず、名勝とされ保護された浜も限られている。過去の時代、大津波で被害をうけた自然環境は、近隣の被害を免れた地域から生物たちが移り住んで、時間をかけて自然と復旧したのであろう。現代の日本の海岸線は壊滅的な被害をうけると、限られた生物の生息地が壊滅したことに他ならず、復旧は難しい。
◆
レスキューをした昆虫標本は、再度その地域で採集できないかもしれない。過去の自然環境を語る証拠標本。その意味は深い。修復を終えた標本は、陸前高田市立博物館が再建された時に戻される予定である。
(総合博物館 おおはら まさひろ)