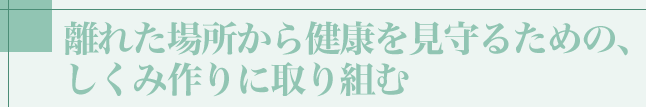![]()

ちょっと体がだるい、ちょっと熱が出たなど、「病院に行こうかな、それほどでもないかな……」と判断に困ったことはありませんか。そのようなときに利用できる健康相談システムについて研究している小笠原克彦さんにお話を伺いました。
病院が遠くて簡単に行かれない、病院に行こうか迷っている、そのような場合に離れた場所の看護師にモニター越しに相談できるシステムが、遠隔相談システムです。モニターにはほぼ等身大に人が映し出されるうえ、会話のタイムラグがほとんどないため、同じ空間にいるような雰囲気のなかで相談できます。また、看護師が相談者の顔色や表情も見てとれるように、鮮明な映像になる工夫が凝らされています。このシステムは北海道内や東北、東京などのドラッグストアに試験的に置かれていて、10歳から90歳まで幅広い年齢層の方が相談に訪れています。
「病気に関しての情報はインターネットを使えば簡単に集めることができますが、逆に、情報が多すぎるために多くの人にとっては判断が難しくなっています」と小笠原さん。どの情報が正しいのか分からない場合でも、このシステムを使うことで、病院に行ったほうがよいのか、それとも自宅で様子をみたほうがよいのか、その場合はどのようなケアが適切なのかといった具体的なアドバイスを、看護師から受けることができるのです。
このシステムは2011年に発生した東日本大震災の直後も活躍しました。石巻市をはじめとする東北地方のドラッグストアが試験的に導入したのです。医療従事者が不足した環境だったこともあり、多くの人がこのシステムを利用しました。現在でも他の地域と比較して相談件数が多いといいます。その他にも、地方事業所を多く持つ組織や、病院が遠い地域の市町村にも導入し共同研究を進めています。
「さまざまな場所に導入されることで、健康相談がより気軽に行えるようになり、健康維持につながります」と小笠原さん。今後は高齢者の自宅に設置することも検討しているといいます。多くの人が健康を維持するためには、遠隔相談システムをどこに導入すればよいか。小笠原さんの挑戦は続いていきます。

後ろのモニターには、遠隔地に設置された相談ブースが映し出される