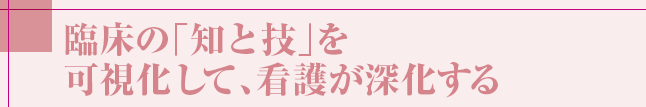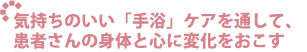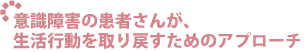![]()
看護技術は、とかく、看護師一人ひとりの「思いやり」や「資質」の問題としてとらえられがちです。しかし、現在、実証的なデータに基づいた看護研究の重要性が高まっています。客観的なデータから、看護の効果を確認し、だれでも利用可能な「知と技」にすることは看護師だけではなく患者さんにとっても大切なことです。その具体的な取り組みとして、患者さんの語りを自然言語処理で分析し、看護の、身体と心への影響を研究している矢野理香さんと、意識障害の患者さんから自発的な行動を引き出すための方法について脳波をもとに研究している林裕子さんに聞きました。


「手浴」を行いながら患者さんと会話する
「手浴《しゅよく》」というケアを通して、客観的に示すことが難しい「脳血管障害患者の認識の変化」を研究しているのが、矢野理香さんです。
「手浴」とは、お湯の中に手を入れて洗浄すると同時に、お湯による温熱効果を生かしたマッサージ・運動を行う看護の手法です。矢野さんは、「手浴」が、麻痺を抱える患者さんにとって、単に「お湯で手を洗う」行為以上の意味があることに着目したのです。手を触れあいながら、看護師と患者さんが会話をすることは、心地よい温熱の効果による身体への影響だけでなく、心を揺り動かすことにもつながります。1日15分の「手浴」を繰り返していくうちに、患者さんの話す言葉はネガティブな内容からポジティブなものへ変化していきます。その変化を記録し、自然言語処理や統計を使って分析することで、患者さんの語りの変化、さらに心の変化を可視化することができると、矢野さんは言います。
手の麻痺を抱えている患者さんは、手を「嫌な記憶や動かない現実に向き合うもの」ととらえている場合もあります。「手浴は、患者さんに自分の手を直視することを強います。しかし、手浴ケアを実践する中で、手の動きや感覚の変化を患者さん自身が認識し、語りは少しずつポジティブなものへ変化していきます。看護師も、手に触れることを通じて、患者さんの思いを共有することができるのです」。「手浴」は、患者さんが、以前とは異なる今の自己の状況を受け入れ、次に進もうとするプロセスの、「その人らしく生きること」を後押しする技。ケアの内容と、患者さんの心の変化を「だれにでもわかる形で記述する」ことが、客観的なデータに基づく看護学を作るために重要だと考えているのです。


意識障害の患者さんから自発的な行動を引き出すための方法について、脳波の分析結果をもとに研究しているのが、林裕子さんです。脳卒中や交通事故により意識障害となった患者さんの中には、意識が戻らない人もいます。そのような患者さんは、自律神経機能は保たれているものの、自分の意思を表現したり、何らかの行為をすることはないと言われています。
ただし、ある感覚刺激を増やすと、意識障害の患者さんの脳が活動することは、古くから知られていました。林さんは、意識障害の患者さんに対して、複数の異なる感覚刺激によって大脳機能の活動を高めるという基礎研究から、たとえば「ごはんを食べる」という状況を意図的に作り出すことで、自発的な活動を引き出すことができるのではないかと考えました。
意識障害の患者さんは、自分で座ることができないため、「座る体勢をとること」から始める必要があります。もちろん、意識がないため、すぐにバランスを崩し倒れてしまいます。しかし、重要なのは「座る体勢をとる」ことを繰り返すこと。重力の中での身体の感覚を患者さん自身が経験し、埋もれた記憶を刺激することにつながるのです。「座る」「手を洗う」「スプーンを持つ」といった「食べる」につながる一連の動作を、「二人羽織」のように看護師が働きかけて時間をかけて再現し、繰り返します。「今からご飯を食べる行動が始まるんだ」という状況を作り出すことが、患者さんの自発的な行動を引き出すことにつながるのです。
林さんは、脳波計を使い、看護師によるケアが、どのように意識障害の患者さんの脳に変化を起こしているのかを観測し、その効果を研究しています。
看護実践を、看護師の個人的な「資質」や「熟練」の問題としてしまわないこと──矢野さん、林さんが、ともに目指しているのは、看護師一人ひとりの持つ経験知を、だれもが利用できる「知と技」にすることです。「経験豊富な、いい看護師さん」の技術は、そのままでは、その看護師にしかできない個人的なものにとどまり、必ずしも受け継がれるとはいえません。看護師の経験知を可視化することではじめて、ほかの看護師が学ぶことができ、将来の看護・医療のあり方を変革させていく力となるのです。