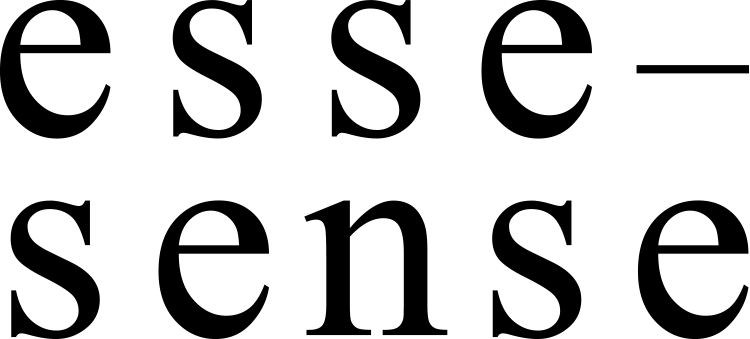リサーチタイムズとesse-sense(エッセンス)のコラボレーション記事をお届けします。esse-senseは、分野の垣根を超えた研究者たちのインタビュー記事を通して「あなたの未来を拓く」をコンセプトに、株式会社エッセンスが運営するウェブメディアです。本学の研究者たちにもスポットライトを当て、インタビュアーである西村勇哉氏(エッセンス 代表取締役)が、最先端の研究、そして研究者ならではのものの見方や捉え方に迫ります。
加藤博文さんは、北海道の先住民であるアイヌの人たちと、本州から移住してきた和人との間で過去に起きたことを知り、共生していく環境をつくるために設立された北海道大学アイヌ・先住民研究センターのセンター長を務めます。
同時に、北米やオセアニアの研究者と連携をとりながら、これまで日本になかった「先住民考古学」を、大学を軸足にしつつも地域のコミュニティと連携をとりながら伝え・広めていきました。
研究者として大学や分野の中に留まらず、幅広い眼差しで過去と今と未来を見つめ、積極的にコミュニティの中に入り研究を進める加藤さん。今回は幼少時代のエピソードから、最近の研究内容までを伺いました。
 加藤 博文
加藤 博文北海道大学アイヌ・先住民研究センター長。1966年、北海道夕張市生まれ。1989年に札幌大学外国語学部ロシア語学科卒、1996年に筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科を満期退学後、同大学大学院地域研究科、島根県立大学北東アジア研究センターを経て、2001年から北海道大学大学院文学研究科北方文化論講座で考古学を担当。2007年から北海道大学アイヌ・先住民研究センターの設立に関わったことをきっかけに、先住民考古学に出会う。2010年より北海道大学アイヌ・先住民研究センターにて考古学担当教授に就任。2020年4月から同センターのセンター長を兼務する。
研究に入口はあれど、出口はない
西村 加藤先生は北海道のご出身と伺っているんですが、なぜアイヌ文化のことを研究し始めたのでしょう。
加藤 私の場合、子どもの頃の関心と現在の研究が必ずしも直結していないところがあります。幼稚園の頃からお城が好きで、とにかくお城に関する写真集を常に見ている「お城フェチ」の子どもでした。「お城好き」と言っても、天守閣ではなくて地味な石垣だったり、土塁、縄張り図(門の位置などが書かれた平面図)が好きでした。身近にお城があったわけでもないし、城下町に住んでいたわけでもないんですが。叔母が静岡の鷹匠町(たかじょうまち)という城下町に住んでいまして、叔母の家に行くと「なぜ自分は城下町に生まれなかったんだろう」と思っていましたよ。
西村 どこのお城に行かれていたのですか?
加藤 具体的にどこ、というよりも、電車や昆虫好きと同じような趣味的な世界でした。日本のお城の石垣や土塁、場合によっては廃墟に見えるようなものでも、逆に当時の暮らしが想像できたりするところが好きだったんです。未だにお城は好きなんですが、最近50を過ぎてからようやくわかってきたのは、本当に好きなことは自分の職業にしちゃいけないんですね。
西村 そういう意味では、お城は「好き」の領域に残っているんですね。
加藤 好きですね。このような背景から考えると、むしろ歴史学の世界に入っていくのが普通なんですが、小学校の教員をしていた父の知り合いで考古学の先生を紹介してもらったことがあったんです。「研究するなら考古学がおもしろい。しかもこれから研究するなら語学が必要だ」と言われて、外国語学部でロシア語を学ぶことになりました。ただ語学に関心があったわけではないので、大学時代は市町村の教育委員会が発掘調査をする発掘現場に参加して、石器の図を描くなど技術的なことを学んでいました。
 1977年、姫路城を訪れた幼少期の加藤教授
1977年、姫路城を訪れた幼少期の加藤教授加藤 その後、筑波大学の大学院に進学して、考古学を本格的に学ぶ機会を得ました。その1年後に旧ソ連が募集していた奨学金留学生に応募してロシアに留学することになって、そこで尊敬できる先生や仲間たちに出会えたんです。
西村 ロシアで今までと違う文化に触れて、いいなと思った部分はありますか。
加藤 私が留学したイルクーツク国立大学は、小さな地方大学であるにも関わらず教授や准教授以外にも考古学研究室だけで30人ほど研究員がいるんです。彼らは発掘調査をして論文を書いて、純粋に研究だけして大学からお給料をもらっていました。ロシアって紅茶文化の国なので、驚いたことに研究室で朝9時、11時、お昼、15時、そして帰る前にお茶の時間があるんです。そしてそれらはすべてディスカッションする時間なんですよね。
西村 なるほど。
加藤 形而上学的な議論や研究の議論が延々と続くわけです。当時ロシアは社会主義国でしたが貨幣経済にシフトしつつあった時代で、今思えばすごく贅沢な時代でした。大学院前半にこうした世界を見られたのは大きかったです。
西村 僕が大学に行ったのはもうその後の時代です。見てみたかったと言う意味では少しうらやましい。
加藤 下の世代の人たちとは、見ている世界が違うだろうと思います。僕らの頃は院に入る門こそあれど、出口は求められていなかった。誰も「時間」というものをセットしていなかったんですよ。だからどんなに時間をかけてひとつの問題を考え続けてもいいし、一生かかって何かを調べてもいい。少なくとも僕たちはそう信じていました。今の学生は2年で修士論文を書かなくてはいけない。それでは考える時間は十分には与えられていないんじゃないかと思いますね。
西村 ディスカッションして、ぐっと煮詰めていく時間をどれだけ贅沢に取れるかが、良い研究につながっていきますね。
 ロシア留学時代の加藤教授(写真右)。1991年に撮影
ロシア留学時代の加藤教授(写真右)。1991年に撮影加藤 そうですね。僕はペテルブルクの科学アカデミーの研究所でもしばらく研究させてもらいましたが、ここの研究員も大学の先生とは違うポジションで研究してるんです。彼らは呼吸をするように常に知識を吸収して、そこで新しい疑問点や課題が生まれて、それがまた次の研究につながっていく。研究することが、まるで呼吸をするようにエンドレスなんです。
西村 そんな中で、先住民考古学に入って行かれた経緯をお聞かせください。
加藤 最初は筑波大学の大学院地域研究科で文部技官としての職を得て、その後2001年に北海道大学で北方考古学の研究者として着任することになりました。当時は人類がアフリカからどうやって地球上全体に拡散していったかということを研究テーマとしていました。
2005年に北大の当時の総長、中村睦男氏が北海道大学とアイヌ民族との歴史的な関係を見直して、アイヌ民族をはじめとする先住民族の教育研究を行うための研究拠点をつくることを表明しました。新しくできる研究センターの設置準備委員会に関わり、そこからセンターと関わることになります。2007年から2009年までは運営委員として、また兼務教員として関わりました。
私は北海道生まれですが、このセンターで考古学と先住民族の関係を考えるまで、実は北海道におけるアイヌ民族や、先住民族と考古学の関係が見えていなかったんです。それで北米やオセアニア地方における先住民族と考古学の関係を遅まきながら調べはじめました。そして先住民考古学という領域があるということを初めて知ったんです。先住民考古学をリードしている海外の研究者を北海道に招聘していく中で、先住民考古学を日本で、この北海道で実際に展開しなくてはいけないんじゃないかと思うようになりました。
 他国の研究者とともに国際会議に参加した時の様子
他国の研究者とともに国際会議に参加した時の様子
その遺産は誰のもの?
西村 先住民考古学を日本で展開する価値があるな、と思われた背景を教えてください。
加藤 ちょうどその頃、知床がユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界遺産の登録を迎えようとしていました。世界遺産は文化遺産と自然遺産でそれぞれ審査する組織が異なります。文化遺産であればICOMOS(国際記念物遺跡会議)という委員会が審査します。一方自然遺産はIUCN(国際自然保護連合)と自然保護に関わる委員会が審査をします。いわば人間VS自然みたいな二分法になっている。これ、実は現在の世界遺産の議論の中では問題になっているんです。
当時はまだ、日本政府が公式にアイヌ民族を日本の先住民族とは認めていませんでした。世界遺産委員会の中には、地域の先住民族との協業や先住民族を巻き込んだ管理運営システムを受持しなさいという評価基準があるんですけど、知床では活かされなかった。どういうことかと言うと、世界遺産の指定範囲にはアイヌ語の地名やアイヌ民族の遺跡がたくさんあるんですが、環境省主導で自然遺産として登録していくにあたって、アイヌの文化遺産は審査機関が違うので審査の対象にならなかったんです。
西村 それは「目に見えている遺跡」と、「見えていない遺跡」の違いなのでしょうか。例えばすごく有名な遺跡とそうじゃない遺跡のような。
加藤 今、すごくいいことをおっしゃっていただきました。例えば、新しい遺跡が見つかったとき、「最大であるか」とか「最古であるか」という観点から注目されます。しかし、その評価って今を生きている私たちの主観であって、その遺跡を実際に使ってきたり、そこに暮らしていた人たちの基準や価値とは必ずしも一致しないんです。
考古学は、科学的な分析を行ったり、数値的なデータの蓄積を行ったりして客観的な資料に根ざしてはいますが、どの遺跡をまず選ぶのかとか、遺跡からどんな情報をピックアップするのかという段階で、既にそこに研究者の主観が介在している。知床の話では、この遺跡とこの地域は大事なんだという選定の段階で参加できる人は研究者で、そこに暮らしている人たちの視点は必ずしも一致していない。研究って、こうした不平等性があると見えてきました。その背景にあるのが、先述した自然VS人間や環境VS社会のように二分法で分けられる近代的思想。フランス人の哲学者ブルーノ・ラトゥールが言った「近代化の否定」という思想が、自分の研究ともオーバーラップしてきたんです。
西村 世界自然遺産になることによって、逆に文化遺産に先住民や住んでいる人がアクセスしにくくなるという問題も出てきますね。
加藤 そうです。特に世界自然遺産の場合には、保護すべき人類の普遍的な価値と認められた自然系、生態系を守らなくてはいけなくなりますから、人間的な活動はある程度制限されます。実際にアイヌの人たちが、例えば自分たちの祈りの場とか聖地として思っている場所が指定区域の中にあったとしても、自分たちの文化遺産として自由なアクセスができなくなるわけです。
西村 奄美沖縄も自然資産に認定されたので、何かしらの反省を組み込まないと同じようなことが起こってくるのかかもしれないですね。
 知床のフィールドワークの様子
知床のフィールドワークの様子
「見えやすいもの」と「見えにくいもの」
加藤 今では複合遺産という概念があります。例えば、エアーズロックはウルル・カタ・ジュタ国立公園の中の、世界遺産ウルルの中で複合遺産になっています。先住民であるアボリジニの人たちにとって、大事な宗教儀礼の空間であることが追加で認められた。ではなぜ知床を複合遺産にできないか。
西村 すごく単純化して聞くと「エアーズロックは大きい」ということでしょうか。一方、アイヌの人の祈りの場はどこですか?と。
加藤 要するに、私たちが見ているものの中には「見えやすいもの」と「見えにくいものがある」ということです。
西村 見えなくなってしまうものってどういうものでしょう?
加藤 評価をする側の立ち位置によりますね。アイヌ民族に関しては明治・大正・昭和とずっと様々な書物で「滅びゆく民族」って書かれてきたんです。近代化や現代化という中で、アイヌの伝統的なものが失われていく。使用する人も減るから、アイヌ語はユネスコの危機言語に登録されています。地名もどんどん変わります。札幌というまちの名前もアイヌ語由来です。北大の学生に聞いても札幌は何となくアイヌ語だと気づく人もいるけれど、本来どういう意味を持った言葉かを知っている人はほぼいません。
人間は普段意識しているものはある程度目に入るし、理解するんだけど、関心がないと全く触れないんですよね。どんなに知的なレベルが高い人間であったとしても、問題意識が落ちてしまっていると、それは単なる記号にしか過ぎなくなります。これが一つ。
西村 はい。
加藤 そしてもう一つが、これもフランス人ですが、哲学者のミッシェル・フーコーが人種という考え方は、「生きていい集団」と「滅ぶべき集団」っていうものを分ける二分法であるということを言っています。つまり近代のいろいろな枠組みっていうのは、人間VS社会、あるいは自然VS人間で、自然は人間に乗り越えられるものだという考えがある。でもその二分法の中で、残すべきもの、残せないものがやっぱりつくられていくわけですよね。今の基準で、良し悪しや大事なもの、大事ではないものみたいに切り分けるのが合理的だという仕組みができてしまっているのです。
連続を見るか非・連続を見るか
西村 世界最古の都市について調べていた時に、数年前まではエリコが世界最古と言われていたが、今は違う都市が最古の都市と言われると知って、世界最古ってなんだろう?と思ったのを思い出します。
今の話と直接的には関係しないかもしれないんですけど、加藤さんのアイヌ民族文化の形成過程の解明に向けた総合的研究で、海洋民を民族集団と捉えてしまうと見逃してしまうことがあると論文に書かれていました。もっと個別に捉えるべきということでしょうか。
加藤 海洋民の文化というのは、北方の海からある海洋民の人たちがやってきてひとつの文化をつくり上げる。ところが、ある段階で文化が崩壊をしていなくなってしまう、という説明が定説だったんです。ところがいろいろな研究要素を積み上げていくと、実は民族集団もさまざまな集団が交じり合いながらできてくるアイデンティティみたいなもので、ある種ひとつの社会的な現象なんですね。政治か、経済か分かりませんが、ひきつける磁場みたいなものが弱まった時に、人々は個々の小さい集団に戻る。
それを例えば土器の紋様や生活スタイルから見ると、ある段階でまるでひとつのファッションの流行のように、ある文化や伝統が流行ったように見えるわけです。それが消えた時、その文化をつくっていた人たちも消えたかのように見えるんだけど、でもそれらをつくった人はそのままいるわけです。
西村 犬を食べていたところから、食べない方に移っていく。じわじわと染み出すように、そっちに移って行った人たちと、移らない人がいますよね。
加藤 見えやすいもの、見えにくいものの話にまた戻るんですけど、私たちは混沌として多様性を持って存在する物の中から、わかりやすい物を選んで説明する。日本列島の縄文文化には犬を食べる文化はありませんが、でも、北海道を含む日本列島の北方では、2000年くらい前から犬を食べる文化はあります。それがアイヌ社会の中に継続するかと言うと、やっぱり食べなくなっちゃうんです。
一方で、連続するものがないかと言うと連続するものはあって。例えば、クジラをお祀りする儀式だとか。クマを儀礼の対象とするものは断絶することなく、脈々と何千年もの間、続くわけです。つまり、何を見るかなんですよ。連続したものを探すのか、断絶したものに注目するか。これは研究者の選択によって、いかようにも解釈は変わります。
西村 裏側の背景をどれだけ捉えられているかが、何かを見た時の理解を変えるんですね。
加藤 そういう意味では、世界観やものの見方を考える上で、さまざまな国の研究者と一緒に研究をすることも大事なんですね。従来の考古学っていうのは、土器や石器といった物質文化に注目して掘り下げていくんですが、遺跡というひとつの空間からどれだけ情報を抽出できるかが重要ですから、植物や動物の研究者と一緒に共同研究することが多いです。
西村 考古学は、データが語ることと、主観を排除しない考え方の両方を大切にしているんですね。
加藤 そうですね。主観だけだと「ただの物語」。客観的なデータがあることで仮説を第三者が検証できる。ただデータだけで語ると、背景にしているところが見えなくなる。人間がつくり出している世界や、頭の中の思想や思考っていうものが、やっぱりひとつひとつの判断をするときの基準になっているんですよね。
西村 なるほど。
加藤 大学院の頃から研究者になる時に、どこかのコミュニティに属しますよね。でも僕たちが対象にしているものって、最初からそんなふうに区分されたり分類されていない。遺跡から出てくる情報ってカオスですから。どうやって調理しようかっていう時に、自分が帰属するコミュニティだけでは、やっぱり足りないですよね。自分の理論や方法論から逸脱しないように緻密に研究を蓄積していくことによって、なにか形をなすということも研究のひとつのあり方だと思っています。
でももうひとつの考え方として、あえてその枠を自覚しながらも壊して越境してしまうということで、より自分が解放されるというか、自分の本当に知りたいことに近づくことができる世界をつくっていくやり方もあるんだと思います。もしかすると、周りから見たら、僕のやっていることはすでに考古学じゃないのかもしれない。
 Society of American Archaeologyのメンバーとともにミズーリで
Society of American Archaeologyのメンバーとともにミズーリで
変わるものと変わらないもの
西村 加藤先生の最近の研究や関心のことも伺いたいです。先住性と集団帰属意識の歴史的決定が最新で取り組まれている研究ですよね。
加藤 知床や礼文島での考古学的なデータが蓄積されてきて、報告書も書いているんですが、その中で見えてくるのが、そこに暮らしていた人の変化なんです。例えば変わるものでいうと、土器のスタイルや模様。変わらないものとしては儀礼とか信仰みたいなもの。連続性と非連続性が見えてきています。従来の研究はこうした多様でわからないものを区分したり、分類をして説明をしてきました。それに対して、むしろもうちょっと正面から多様性の持つ本質というか。その多様性自体が、実は重要なんじゃないかということを極めたいと思ってるのが、最近の研究です。
この研究の結論はまだ見えていません。変化するもの自体が本来の姿かもしれない。そういう意味では、自分たちの分析概念として使ってきたもの自体が持つ基盤の脆弱さをあぶりだしたいとも思っています。
西村 いろんな研究者が関わるとなると、どういった分野の方がいますか?
加藤 客観的な数値データを提供してくれたり、分析する分析科学の人たちが入ります。そういったものを分類してクリアなひとつの方向性を出す研究っていうのも、大きな研究プロジェクトの一角には常に必要ですから。一方で、ものを決定づけていくプロセス自体を批判的に見るグループも必要です。そういう中には歴史学の研究者や、文化人類学の研究者も入ってきます。
こうした中で、実は私が一番苦労しているのが考古学なんです。このままいくと、考古学はいわゆる一次資料提供者の階層に甘んじる恐れがあるわけです。学問として考古学が成り立つためには、考古学自体が新しい、何か世界を切り拓くような理論を生み出さなきゃいけないと思うんですが、既存コミュニティの中では見えてきません。
西村 これまでも考古学者は人類学的視点、あるいは歴史学の視点を個人の中に取り込みながら結論を出してきたので、チームになった時にそれを他者に委ねてしまうと一次資料提供者みたいになってしまう、ということですね。さらにその向こう側に入って行くための新しい位置取りが必要ということでしょうか?
加藤 とはいえ空間や場のつながりを一番持っているのは考古学者なので、考古学者があるひとつの研究のフィールドを特定したり、もしくは研究のプラットフォームを設定して、マネージャーとして、この議論をするためにはこういう研究者に参加してもらうと、こういった展開や異分野の化学反応が起きるということを構想する。そうしたことが次の新しい領域を生み出すきっかけになるんじゃないか、とは考えています。
西村 おそらく、一般の考古学者のイメージって、「掘る」みたいなところがあると思います。
加藤 そうですね。冒頭でも触れましたけど、僕がロシアに留学した時に出会った人の中でイルクーツク国立大学のゲルマン・イヴァーノヴィッチ・メドヴェージェフ先生がいらっしゃったんです。この方がまさに遺跡という場所をプラットフォームにしていた。この先生は地球の表層として地層ができてくる中の構成要素のひとつが人間なんだ、という地球規模の視点で世界を語る「地質考古学」を提唱していた人でした。
本当に世界を知りたいと思ったら、まずその地層がどうやって形成されたのか、そこに水がどういう営力を与えていたのか、植物はどういう営力を与えていたのか、気候はどうだったのか。そういうことを全体的に復元していかないと、本当の意味での人間の活動なんてわからない、と。
西村 地理的条件と考古学というものを一緒に考えるっていうのは、まだまだもっと知られた方がいいような気がします。
加藤 そうですね、海外だと考古学で教育を受けた人が物理化学を学んで年代測定を極めるといった例があるんですけど、日本の考古学者はあまり越境しないんです。逆に教育委員会や博物館で調査を研究している人たちの方が、幅の広い目線みたいなものが必要なんだということを自覚している人が多い気がします。
学びは地域コミュニティの中にある
西村 なるほど。最近の関心についても伺っても良いでしょうか。
加藤 一番関心があるのはやっぱり文化遺産と、それから所有権の問題です。さきほども申し上げましたが、最近は遺跡って誰のものなんだろうとか。誰が歴史を語る権利を持っているのかということを、考えたり、書くことが多いですね。
いわゆる北海道の文化遺産を考える部分で、まだ十分にコミュニティの人たちが参加できる場がつくられていないんです。歴史自体を叙述するのも研究者であれば、資料をフィールドや書物から拾い上げてくるのも研究者。そして一般の人は研究者の書いた本や研究者がつくり出した博物館の展示でしか研究に触れることができない。
本来の研究のあるべき姿って、研究の全てのプロセスで地域コミュニティの人が参加できる状況をつくっていくのが理想的なんだろうと思います。どんなに大学院で博士号を取ろうが研究を突き進めようが、いわゆる考古学者とか研究者のスキルや知識では、ある自然の特定の空間がその地域に住む人にとって大事な信仰の対象であるっていうことはわからないから。どんなに縄文の遺跡を世界遺産にしたとしても、地域の人たちがその場所は大事だと思わなければ、所詮はただの野原。アイヌの人たちの歴史文化遺産も地域の人たちが実感できるようなものにしていかないと、おそらく風化してしまうんだろうと思います。
西村 それは結構難しいですよね。大事なことを教えるときに、結局教育というフレームで子どもたちに教えてしまって、意外と少し違うものになっていきがちです。
加藤 我々が暮らしていく場所や空間が大事だよと教えてくれるのは、教科書や教室の中だけではなくて、おじいさんやおばあさん、地元の人かもしれない。実態はおそらく、もっと多様なんですよね。今後は研究者の行っている研究を地域ベースで、コミュニティベースで展開するということがあっていいんだろうと思います。北大に関して言えばフィールド科学を重視しているわけですし、アカデミックコミュニティに関してももっと理論的に極めてもいいと思います。年齢関係なしに必要なもの、知りたいと思ったことを学ぶことができるような場を提供していくのも、多分大学という空間が持っている機能なんだと思います。
 遺跡発掘に先立ち、祖先の霊に祈りを捧げるカムイ(神)ノミ(祈る)という儀式が行われた
遺跡発掘に先立ち、祖先の霊に祈りを捧げるカムイ(神)ノミ(祈る)という儀式が行われた西村 お話を聞いていて禅の十牛図を思い出しました。その最後の図は、まちでお酒を飲む絵なんです。真の自己を発見した人は、悟りを置いてお酒を飲みに行くみたいな。そういう展開が研究者でも行われると、地域コミュニティと研究者が出会うきっかけになりますね。
加藤 僕は、なくなったものを実践しようとしているのかもしれません。象牙の塔にいて、研究と社会を切り離してしまうと、先住民考古学とコミュニティとの連携は成立しなくなります。地域コミュニティというフィールドに出て、そこで日常的な延長線上で研究を行っていくと、おそらくそこには学問として切り離されない本来の知の体系があるはずなんですよ。
西村 もし研究者として極めていきたいのなら、地域コミュニティとの関わりを持ったり深めていってもいいのかなとも思ったんですが。
加藤 そうですね。もし、研究者を目指す人たちに対して考えてほしいことを言うなら、学問にも社会にもさまざまな壁があるのですが、それは結局誰かがつくったものですから。自分でつくったものではないわけだから、壊せばいいんです。どんな学問を選んでもいいんですけど、学問も結局誰かがつくったものなので、そこに縛られる必要性はないんですよ。
このインタビューを終えて、私は星野道夫の「約束の川」(平凡社)を手に取りました。星野道夫はアラスカの大自然に魅せられてアラスカに暮らし、野生動物や厳しく雄大な自然、そして先住民の暮らしを写真とエッセイで残した写真家です。
星野道夫が友人と共に、先住民の年老いた友人の家を訪ねた時のエッセイに、こう書かれていました。
「近代化の中で、村の生活は大きく変わりつつある。けれども、便利なもの、より楽な暮らしへの移行を、そこに生活することのない誰が批判できるだろう。僕たちは無意識のうちに、彼らの暮らしを古い博物館の中に閉じ込めようとする。しかし、時の流れの中で、人の暮らしもまた変わり続けてゆく。」(ケニス・ヌコンの思い出)
人間の暮らしの中は必ず変わりゆくもの。もちろん先住民の人にとってもそうです。それでも変わらずにあり続ける祭礼や祈りといった精神文化のよりどころには、その民族にとって絶対的かつ本質的なエッセンスが詰まっているように思えます。
世界遺産という眩しい光の中で、人知れず闇に埋もれてしまう誰かにとっての聖地がある。その事実を知るだけでも、私たちの眼差しはほんの少しだけ変わるのかもしれません。
考古学は、かつての人々の暮らしやあり方を知るだけでなく、まさに今を生きている私たちにとっても、羅針盤になってくれるのだと思います。
(ライター:ヘメンディンガー綾 インタビュアー:西村勇哉 編集者:増村江利子)