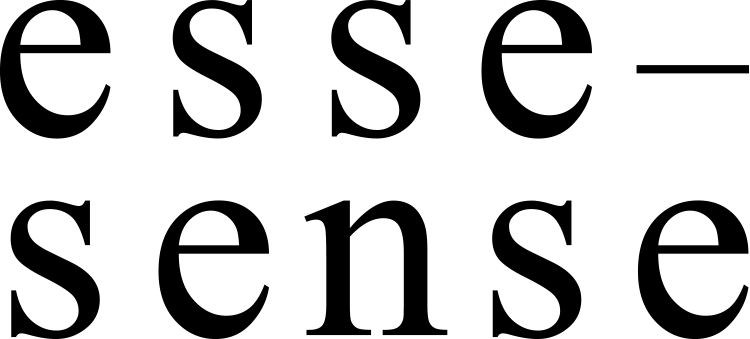リサーチタイムズとesse-sense(エッセンス)のコラボレーション記事をお届けします。esse-senseは、分野の垣根を超えた研究者たちのインタビュー記事を通して「あなたの未来を拓く」をコンセプトに、株式会社エッセンスが運営するウェブメディアです。本学の研究者たちにもスポットライトを当て、インタビュアーである西村勇哉氏(エッセンス 代表取締役)が、最先端の研究、そして研究者ならではのものの見方や捉え方に迫ります。ライターはヘメンディンガー綾氏が務めました。
大学時代に出会った京劇に魅了された北海道大学大学院文学研究院中国文化論研究室教授を務める田村容子さんは、京劇の男旦(女形)や、中国の近現代演劇、またプロパガンダ芸術などをテーマに研究を続けています。
国立の演劇大学が北京、上海だけで3つも存在する中国において演劇は、社会の中で役割をもって扱われています。中国における演劇が、どのように社会の中で位置づけられ、また社会に対してどのような役割を果たしているのか。その変遷は、20世紀前半の初期の頃ではまた現代と異なる状況を見せてくれます。
社会における演劇の扱われ方とその変遷を、異なる国の異なる歴史を見ることで、私たちは演劇にどのような可能性を知ることが出来るか。その一端を京劇の変遷と共にお届けします。
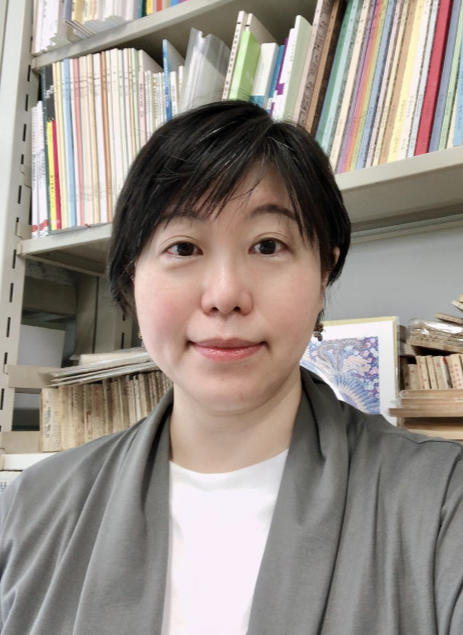
田村容子
北海道大学大学院 文学研究院 中国文化論研究室教授。1975年愛知県名古屋市出身。神戸大学大学院文化学研究科博士課程単位取得退学後、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館にて助手(東洋演劇)を務め、福井大学教育地域科学部・国際地域学部准教授、金城学院大学文学部教授を経て、2020年より北海道大学大学院文学研究院准教授、2023年より同教授。博士(文学)。専門は中国演劇、中国文学。著書に『男旦(おんながた)とモダンガール 二〇世紀中国における京劇の現代化』(中国文庫、2019年)、編著に、『中国文化55のキーワード』(ミネルヴァ書房、2016年)など。
日本の古典演劇が身近にあった幼少期
西村 田村先生が演劇と出会った経緯について伺えますか。
田村 祖母が三味線を弾いていたので、祖父母が歌舞伎を趣味で観に行ったりするような環境で育ちました。そのため幼少期から日本の演芸に関心を持っていましたが、自分が舞台を観に行くことは高校を卒業するまではなく、むしろ文学や漫画、絵などに関心のある中高生だったと思います。
西村 そこからなぜ演劇に関心を持つようになったのでしょうか。
田村 大学の3年次に日本芸能を専攻するゼミに入ったのですが、ゼミの先生が現代劇、伝統芸能、ダンスなど舞台はなんでも観る方でした。「今月はこういうお芝居を観に行くので、行きたい人はチケットを取ってあげるよ」と誘ってくださって、そこから月に何本もお芝居を観に行く生活が始まって、だんだんハマっていきました。
西村 当初、おもしろいなと思われた劇は何ですか?
田村 大学3年生当時(1995年)、平田オリザさんが主催される青年団が演劇シーンに出てきました。それまでは先入観で、日本の現代演劇はアングラ演劇的というか、肉体中心で俳優の熱量で見せるというイメージを持っていたのですが、平田オリザさんは"現代口語演劇"を提唱されていて、"静かな演劇"と言われていたんです。登場人物がみんなボソボソと、淡々としゃべり、劇場に入った瞬間からもう舞台の上にセットが完成されていて、俳優もあらかじめそこにいて、なんとなく演技を始めるスタイルで、演劇への先入観をぶち壊されたという感じがして好きでした。
西村 そこから大学院に進学した経緯について教えてください。
田村 大学1年生の夏休みに中国に旅行に行って、上海と近郊の都市を回りました。当時の中国は「改革開放」政策(社会主義計画経済に資本主義的市場経済を導入した政策)が1970年代の末から始まって、80年代に経済成長を遂げていき、90年代の初頭は上海でも高いビルが建っているのは中心の一部だけで、田舎っぽい雰囲気が残っていました。外国人もまだ珍しがられるような時代だったので、中国の方たちがすごく温かく接してくれたのですが、中国語が全然話せなくて。その後大学2年生と3年生の夏休みに2週間程度の短期留学の語学研修プログラムに参加して、上海と天津に行き、「中国っておもしろい」と思い始めていました。
そして3年生の時に、ゼミの先生が上海京劇院という大変有名な劇団を大学に招聘し、京劇の公演を観に行って「京劇、すごいな」と思ったんですね。それで大学4年生の時に卒論のテーマを京劇にしようと考え始めたのですが、先生に相談したところ「中国語がそんなにできないのに京劇の研究はできるのか。もし中国や京劇に関心があるなら、1年間の留学のプログラムに行ってみたら」と言われて。それで4年生の時に天津にある南開大学(なんかいだいがく)に留学しました。留学中は中国の演劇をたくさん観て帰国して、京劇の卒業論文を書いて、「もうちょっとやりたいな」と思って大学院に進んだという経緯です。
西村 京劇のどんな点が一番おもしろかったのでしょうか。
田村 日本の伝統演劇では、能や狂言は全体として静かでゆっくり動く印象を持っていました。中国の京劇は、同じように型のある伝統演劇でありながら、ものすごくアクロバティックな演技を見せたり、役柄によっては女優であってもものすごく激しく動いたり。そのあたりに日本の伝統演劇にはないエネルギーを感じて惹きつけられました。
 京劇『覇王別姫』(『梅蘭芳』北京出版社、1997より)
京劇『覇王別姫』(『梅蘭芳』北京出版社、1997より)西村 中国の演劇はストーリーが中心で、少しアクション活劇的な要素があるのですか。
田村 そうですね。実際、京劇のアクロバティックな演技はカンフー映画などにも影響を与えています。
西村 すると、演者の方はトレーニングを受けられるんですか。
田村 はい。基本的には幼少期から訓練を始めないと、とてもプロにはなれないと言われています。ただ、中国は世襲ではなく学校制度をとっていますので、子どもの頃から京劇を習って、才能もあって努力もできて、それを続けたいと思った人が専門の学校に行くという感じです。体操の学校などに近いものがあります。
西村 演劇をされている方はみなさん鍛えていますが、鍛え方がちょっと違いますね。そこからさらに博士課程に進んで研究者になったのはなぜですか?
田村 大学では中国のことを専門的に学んでいなかったので、大学院は「中国学を専門的に勉強できる大学院に行くべきだ」という指導をいただいて、神戸大学の大学院に行きました。しかし周りの同級生は、みんな学部の時からずっと中国文学を専攻していた人たちなので、私と知識の量が全然違うんですね。私は現代中国語はまあまあできたのですが、中国の文学は古文、日本で言うところの漢文が難しいんです。ですので、修士課程の2年間は、とにかく中国文学の勉強の仕方や研究の仕方を覚えるのでもう精一杯。その2年間では自分の本当にやりたい研究はまだできていないという感覚があったので、ここまで来たら博士課程に進んで留学しようと思いました。
西村 さらに、博士課程からどうしてまた研究を続けようと思われたのでしょうか。
田村 博士課程の2年目に中国に留学して、中国の演劇関係の仕事に就きたいと思っていたぐらいでしたが、中国にいると「日本の古典演劇や伝統演劇は中国とどのように違うのか」とよく聞かれるんです。その時点では日本の演劇に関する知識が全然足りず、このままではいつか行き詰まると思い、日本に戻ってきました。それで早稲田大学の演劇博物館が助手を募集しているのを見つけ、応募して採用していただきました。
本当は、この助手の間に博士論文を完成させるべきなんですが、博物館の業務が結構忙しくてできなくて。私は助手の中でもアジア枠で採用されたのですが、私一人だったので、アジアのことはなんでも聞かれるんです。私自身、中国の狭い部分しか知らないので、必要に迫られていろいろと学んでいくうちに、「中国演劇のことをもっと勉強しなきゃ」というふうになっていきました。当時、中国の演劇関係の知り合いと連絡を取り続けていて、中国で大きな演劇フェスティバルがあると、すぐ現地に飛んで行って観たりはしていました。実際の舞台作品を観るとおもしろいので、「これを論文に書きたい」という気持ちが湧いてくる。それが一番大きかったかなと思います。
西村 京劇の中で好きな劇や、印象的だった劇はありますか。
田村 一番心を惹かれたのは、伝統的な型を打ち破って、新しい内容に変えていくことですね。中国では、伝統をただ守って継承しているだけでは駄目。さらに、それを突破しなければいけないという発想が強く働いていて。どの伝統演劇の劇団も、新作をたくさんつくるんです。それもある意味では、政策がそうなっているので、つくらざるを得ない状況もあるんですが。伝統的な演劇の形を使って、こんなに新しい演劇がつくれるんだなということがおもしろかったです。
西村 「伝統的な劇」のイメージがなくて、『三国志』と『水滸伝』ぐらいしかわからないですが、どんなふうに新しくなったのですか?
田村 例えば、京劇のような伝統演劇の演技の様式を使ってシェイクスピアの『マクベス』を演じてみる。それも「西洋のものを翻案してみました」で終わらずに、新しいアイデアを取り入れたり、シェイクスピアが描いた物語の中に、現代の中国人の欲望が見えるような作品になっていたりするのがすごくおもしろいなと思わされます。
西村 それはおもしろい。観てみたいです。失敗すると大変なことになるんでしょうけれど。
田村 本当に玉石混交です。無数の新作がつくられて、駄作もありますが、うまくいった作品はすごくおもしろいです。
中国における近現代演劇の移り変わり
西村 京劇の研究では、男旦(ナンタン 男性の演者が演じる女性役)に焦点を置いた研究から始めていますが、なぜ男旦に焦点を置かれたのでしょうか。
田村 元々、日本の伝統芸能の中でも男性が女役を演じるのがおもしろいと思っていました。そもそも、演劇の中で歌舞伎の女形や宝塚の男役のように、異性装と言われる演技術、つまりジェンダーを飛び越えることに、私自身が憧れと関心を持っていました。でも中国演劇を観たら、女性の役は当たり前のように女優が演じているんです。調べてみると、1920年代ぐらいから女優が台頭してきて、それまで男性が演じるのが当たり前だった女役を女優が演じるようになっていった経緯があり、1940年代から50年代ぐらいにかけては「もう女役は女優がやりましょう」と統一化されていく流れがあるのですが、なぜそうなったのかを調べたくて研究テーマにしました。
西村 清の時代に京劇が生まれて、中華民国に変わる頃に女優が女性役をやるようになっていくという、そんな感じであっていますか?
田村 そうですね。中華民国成立前の首都北京では、そもそも女性は公の舞台に立ってはいけないという決まりがあり、演技ができる女の人も、芸者のような方が個人のお屋敷の中で芸を披露するのが主流だったと思います。中華民国になって、女性も舞台に立つことができるようになったので、次第に女優の数が増えていきました。
 京劇の男旦(『梅蘭芳』北京出版社、1997より)
京劇の男旦(『梅蘭芳』北京出版社、1997より)西村 そうすると、元々やっていた男性による女性役の人たちが廃業していくんですね。
田村 京劇の演技術って体力も使うし、子どもの頃から訓練しないとできないので、そんなにすぐには廃れないのですけれど。時代が進むにつれて女優の演技術も向上していきますし、20世紀初頭から新作がつくられて、女性のできる演技術に合わせた役柄の、新しい演目がつくり出されることによって、女優の人気がどんどん上がっていったんです。この辺りは、劇場設備の近代化とも関わっています。照明技術が向上していくと、「女の人の役は女優がやった方がきれいなんじゃないか」という価値観が観客の中に出てきたりして。ずっと正統派として君臨してきた男優の人気を脅かす女優も出てくるという現象になっていきました。
西村 女優が台頭してくるのは、いつぐらいの話ですか?
田村 何度か波がありますが、一番最初に台頭したのは、1915年ぐらい。20世紀初頭ぐらいまでの中国は、成人した女性は結婚しないと生きづらい社会だったので、女優としての生命も非常に短いものでした。若い頃に一時期人気になった女優も、最後は必ず誰かの妻や妾(しょう)になるなどして、舞台を降りてしまうのです。その後、1920年代後半から30年代にかけてもう一度大きな女優のピークが来て、それはかなり長く続きました。
 京劇の女優(『中国京劇図史』上巻、北京十月文芸出版社、2013より)
京劇の女優(『中国京劇図史』上巻、北京十月文芸出版社、2013より)西村 そのピークはなぜ起こったのですか。
田村 男優から直接芸を習って、演技術に優れた女優が現れたことが一つ。また、1920年代後半から30年代にかけて中国にハリウッド映画などが入ってきて、西洋的な女性の審美観が新たに入り込んでくる。そうすると、舞台の上のどのような女性が美しいかという価値観にも大きな変化が生じてきて、女性の役は女優がやった方がいいという観客の審美観につながっていったのだろうと思います。
西村 清の時代の京劇と、全然違うものになっていると思うのですが、演目はあまり変わらないのですか?
田村 大きく変わらず残っている演目もあります。
西村 同じ演目だけど、全く違うものであるという状態になるのでしょうか。
田村 そういったものもあります。清の時代は、纏足(てんそく 子どものうちに女性の足を布で巻いて、骨を変形させ、足を成長させないようにする風習)があり、女性役の男性の俳優は、舞台の上でそれを表現するために、特殊な厚底のハイヒール状の義足を履く演技の仕方がありました。19世紀末の清の終わり頃に、纏足そのものが中国で廃止されていくようになると、それに伴って、いかに伝統的な演技であっても「中国の廃れた風習をやるべきでない」という発想になっていくんです。すると同じ演目で同じ登場人物であっても、清の頃にされていた演技と20世紀以降の演技が変わってしまうというようなことが結構あったと思います。
西村 社会状況によって大きく左右されるんですね。
田村 そうですね。日本の伝統芸能は、その時の社会の尺度に合わせてそこまで変えないと思うのですけれども。
西村 そうですね。
田村 京劇は、時代や観客の価値観に合わせて表現をかなり変えていく演劇です。
西村 不思議ですね。
田村 私の考えとしては、京劇は伝統演劇ですが、20世紀の半ばぐらいまで俳優たちの中では、現代を写す演劇であり続けることを諦めていなかったのではないかと思っています。
西村 スーパー歌舞伎みたいな感じですか?
田村 日本の演劇ではそれが近いかもしれません。ただし、スーパー歌舞伎は現代的なコンテンツをいかに歌舞伎に落とし込むかを、楽しんでおられるかなと思います。
西村 逆ですね。
田村 そうですね、逆な感じがします。京劇の演技では、どれだけ同時代の人たちに肉薄できるか、身を以て迫ることができるかをやっていた感じがします。
西村 日本にそういうものはないのでしょうか。
田村 ジャンルとしては、ないと言ってもいいと思いますし、それが中国演劇や京劇の一つの魅力かなと思っています。
西村 おもしろいですね。「どんどん変えていくぞ」という勢いを感じますね。
ヘメンディンガー 日本の能は武家社会の中で発展してきて、一方、歌舞伎は庶民も楽しむことができるものでしたが、それらと比較してみると、京劇は誰に向けて演じてこられたのでしょうか。
田村 19世紀の末ぐらいまでは、京劇も宮廷演劇だった時もありますし、一部の貴族たちが屋敷に劇団を呼ぶ形で演じられるものであったと考えていいと思います。その後、20世紀の半ばに人民共和国が成立するまでの中華民国の時期は、劇場で大衆の前、あるいは、お金を払ってくれる資本家のために上演するようになり、人民共和国以降は、建前としてですが政治のために上演するようになりました。人民共和国になって京劇および演劇にとって良かったことがあるとすると、それまで中国では役者は一番蔑まれる職業だったのですが、人民共和国になってからは、演劇関係者は「人民を教育する社会教育者」という位置づけになったことです。演劇を演じる関係者側にも「大衆を啓蒙する」という意識があったと思います。
西村 社会教育者としての演劇は、ある種ものすごく発展した状態ですね。演劇の可能性をしっかりと活かせている。ある種、科学がいろいろな人をパトロンとしながら進展してきたように、中国において演劇はいろいろな人がパトロンになりながら発展をしてきているので学ぶべきところが多いですね。
田村 演劇が社会教育の一つとして位置づけられてから長いので、社会教育としての演劇は、ある程度国家の意思を反映する。その一方、国家の政策と距離を置いた演劇は、それぞれが芸術的な作品をつくる。それは両立しても矛盾がない感じがありますね。
西村 ビジネスと科学と芸術とが同じぐらいの位置にあるという、そんな印象を改めて受けました。あるべき姿であるような気もしますね。
田村 ただ、「なんの制限もなく作品がつくれる日本や海外の芸術家がうらやましい」というふうに言う人もいます。西村 国家と芸術の関係という意味では、自分たちができていないものがたくさんあるというように見えるので、国家と芸術の関係だけを見ると発展していると思いますね。
民衆心理を映し出す演劇
西村 ゼミのWebサイトに「中国では、演劇や絵画のようなビジュアル文化は、"共通言語"の役割を果たしてきたといえる」と書かれていましたが、共通言語としての演劇ってすごくおもしろいなと思いました。中国はそもそも文化も方言も全く違うエリアがたくさんある中で、一定の共通性が京劇の中にあるということだと思いますが、演劇を読み解くことで、当時の社会全体が見えてくるみたいなおもしろ味があるのかなと。
田村 授業でよく学生に話すエピソードとして、京劇の演目の中で『水滸伝』という古典小説にもとづいたものがあります。その中で、宋江(そうこう)という主役級の男に斬り殺されてしまう妾の閻婆借(えんばしゃく)という登場人物の女性がいるんですね。脇役ですので、小説では斬り殺されてから物語にも出てこないのですが、京劇および、中国の他の伝統演劇の中に、閻婆借が生前に浮気していた男性を、あの世に道連れにしようと幽霊になってとり殺しにくるという演目があるんです。
これは、すごくおもしろい演目だと思っています。要するに、小説だけを読むと閻婆借がその後どうなったかは書かれていないのですが、『水滸伝』の話を知っている民衆の想像力の中では、「死後はどうなったんだろう」と関心を持っていたのではないかと思うんですね。中国の古典小説は、一部の上層階級の男性知識人である書き手が、同じく男性知識人である読者に向けて書いているところがあるんですが、その他大勢の、文字も読めなかったであろう、大多数の民衆たちの想像力によってつくられた物語が、演劇にはまだ残っている。小説では描かれない部分が描かれるのが、中国演劇のおもしろいところだと思います。
西村 当時の文字が読めなかった人たちは、死後のことを演劇として観ることでほっとするなど、民衆心理が垣間見られるのでしょうか。
田村 不幸な目にあって死んだ女性の幽霊は、中国の伝統的な社会ではすごく恐れられているんです。それを物語化し、かつビジュアル化して、みんなで観て安心したいという欲求があったのではないかと思います。
西村 それは「自分もそうなってはいけない」という恐れですか?
田村 いえ、不幸なまま死んで成仏できていない女性の霊というのがその辺にいると恐ろしいので、鎮魂してあげないといけないという考えではないかと思います。
西村 なるほど、おもしろい。今みたいな話は、中国各地で同じようなものがあったりするのでしょうか?
田村 前近代の中国では女性に人権がなかったので、結婚相手を自分の意思で決められませんし、女性の側からは離婚を言い出せない社会環境で、自殺してしまう女性も結構多かったようです。そうして首をくくって死んだ女性が幽霊となって、この世に身代わりを探しに来るお話もあります。基本的にはそういった幽霊を演劇で描くことで、鎮魂するという目的の演劇がつくられていると思います。
西村 なるほど。いろいろとおもしろい。社会の状況を映し出すものとしての演劇という視点が常にありますね。
ジャーナリズムと演劇の関係性
西村 演劇とジャーナリズムの相互連関についても研究をされていますが、このテーマに関心を持たれた背景や理由について教えてください。
田村 私自身のおもな専門分野は、20世紀以降の中国演劇です。20世紀のとくに前半の演劇は、映像も写真も残っていないものが多いのです。京劇はどんどん形を変えていくので、かつての演じ方を特定したり、復元したりするのが非常に難しい。それで当時の新聞や雑誌に書かれているレビューをひたすら読んで、そこからどういう演出がなされていたのかを復元する研究をしてきました。すると、だんだんレビュー自体がおもしろいと思い始めたんです。とくに上海で新聞や雑誌がたくさん発行されていたのですが、そもそもレビューを執筆しているジャーナリストがプロデューサー的な立場を兼ねているケースも非常に多いことがわかってきて、その中の何人かのジャーナリストが演劇業界を動かしている様相も見えてきて、それが非常におもしろいなと感じました。
西村 当時のジャーナリズムは、西洋文化として入ってきたジャーナリズムでしょうか?
田村 そうです。近代的な新聞や雑誌を印刷して発行する技術は、そもそも西洋人が19世紀末に始めたもので、西洋から入ってきたと言っていいと思いますが、書いている人たちは中国人です。
西村 なるほど。そうすると元々すごい力がある人たちではないですよね。やっているうちにある種の権力のようなものも発生してくるということですか?
田村 そうですね。小さなタブロイド新聞社がいくつもあって。それぞれの新聞に、主筆というデスクのような人がいて、この人に発言力があります。やがて投稿制度が始まると、主筆に採用されたくて、書き手でもある読者はいろいろなレビューを投稿し、常連になってくるとコラムも掲載する。そこであるタブロイド誌とまた別のタブロイド誌のコラム同士で、演劇についての言い争いが始まる。これを筆戦(ひっせん)と呼ぶのですが、「また筆戦が始まった」と言って、新聞の売り上げや演劇のチケットの売り上げも上がる、みたいなことがありました。これはちょうど現代のSNSと似たような感じです。ある新作演劇を売り出すために、新聞や雑誌のレビューでわざと炎上させるようなことが既に行われていました。
西村 新聞社をやる人って、リベラル寄りなイメージがあるのですが、いかがですか?
田村 そんな感じです。ジャーナリストと言っても、演劇の脚本を書いたり、映画監督をやってみたりするマルチクリエイターが当時はたくさんいました。
西村 そういう人たちは新しい表現や挑戦を好みそうな気がしますが、実際にそういったものが評価されていくのでしょうか。
田村 そうですね。日本や西洋への留学から帰ってきた人もいて、翻訳劇をやったり、中国の物語に翻案しているけどベースは海外のものという作品もありました。
西村 先程映画の話が出てきたので、映画と関わる人たちも被ってくるのかなと思うのですが、そこから新たな映画と演劇の関係も生まれてくるのでしょうか?
田村 はい、日本で歌舞伎に対抗し、明治期に出てくる新派(しんぱ)という演劇があります。その新派劇に、日本留学中に影響を受けた中国人もいて。その人たちが、日本の新派劇の俳優から直接新派の演技術を教えてもらい、中国に持ち帰る流れがあります。それが中国では新しい近代劇の萌芽期の一潮流に位置づけられていて。彼らは、従来の型のある演技や、京劇の演技術から離れた新しい演劇のジャンルをつくり出そうとしていたんです。でも、その人たちの多くが映画業界に流れていって。中国の初期の映画をたくさんつくっていますね。
西村 そうすると、伝統的な芸術分野というカテゴリーもありつつ、一方で同時に、20世紀初頭に起こった新しい熱を取り込んでいく様相もあるんですね。
田村 そうですね。あとおもしろいと思うのは、今申し上げたような新聞、雑誌、映画という新しく生まれたメディアに、伝統演劇の京劇の俳優たちも好んで参入していくところです。京劇側が「我々は伝統演劇だからそういう新しいものには関わりません」といった態度ではなく、むしろ飛び込んでいって、映画俳優の演技術を京劇に取り入れたりしています。こうして20世紀初頭の映画や演劇では、新しいジャンルの演劇と京劇の俳優が共演し、影響しあう動きが見られます。
西村 日本の明治時代みたいですね。
田村 そうだと思います。
プロパガンダ芸術としての演劇
西村 時代が進んで20世紀中盤から後半になってくると、中国ではプロパガンダ芸術が登場しますが、これを研究のテーマとして扱われたのはなぜでしょうか?
田村 中国には、現代京劇というジャンルがあるんです。中でもおもしろいと思ったのは、1960年代につくられた現代京劇です。中国が文化大革命という政治闘争をおこなっていた時期の作品で、当時は革命現代京劇と呼ばれていました。物語は基本的に中国共産党の宣伝のためにつくられています。例えば日中戦争期に、中国共産党がどんなふうに戦って、日本軍を打ち負かしたかといった話を京劇で演じるんですね。ですので、登場人物のほとんどが軍服を着ている。それが舞台作品として本当におもしろいなと思ったのですが、あまりにも政治的なイデオロギーの濃すぎる作品で、どうやって研究していいのかよくわからなかったんです。博士論文を書いている最中に、20世紀の京劇を通史的に見た時に、中華人民共和国という国ができた後の京劇の変遷も追いたいと思って、ついに現代京劇に手をつけることにしました。
西村 なるほど。そもそも中華人民共和国になった後の京劇は、プロパガンダとしての京劇ではなくて、一般的な京劇も続くんですか?
田村 まず、1949年に中華人民共和国が成立する前、1942年に毛沢東が「文芸講話」という文芸の方向性を示す講話を発表しています。その講話の中で、「中国の文芸は労働者・農民・兵士のためのものである」と言うんですね。基本的に、人民共和国の文芸は党の方針を人民に伝え、奉仕するためのものであると毛沢東が明確に位置づける。そのため、1949年以降の中国は、どんなジャンルであれ、芸術作品はすべて政治のためにつくられるという建前になっています。京劇の伝統的な演目も、1950年代に大きな京劇改革が行われて、それ以前の伝統的な演目の内容が点検され、中国共産党の方針に合わない演目は基本的に禁止されるか、内容を書き換えるというふうに大きく手を加えられました。
西村 伝統的な演目であっても変えられるということですね。
田村 そうです。
西村 例えば、先ほどの『水滸伝』では、『水滸伝』自体は演じるけれど、演じ方が全然違うということですか。
田村 そうです。『水滸伝』にもとづくものでも、先程お話ししたような幽霊が出てくるような演目は、毛沢東時代には上演できなくなりました。
西村 ある意味、そこで一度分断されて、新しい流れが生まれている。
田村 そうですね。民衆は文字で見るより、音楽やビジュアルを伴った演劇で何かを訴えられる方が理解しやすいと毛沢東が考えて、「演劇や民謡の形式で中国共産党の物語をもっとつくるべきだ」ということになり、現代京劇がつくられていくんです。
西村 演劇は、政治的にかなり力の入っている分野だったんですね。
田村 これは今の中国でもそうだと思います。演劇をものすごく重視しています。
西村 演劇学校は盛んになっていくのですか?
田村 演劇学校の制度も整えられていきます。現在、国公立の演劇大学が、北京と上海だけで「中央戯劇学院」「上海戯劇学院」「中国戯曲学院」などいくつもあります。地方都市や専門学校を入れると、もっとたくさんあります。
西村 そんなにあるのですね。話を戻しますが、プロパガンダ芸術としての演劇は、どのぐらいの期間、主たるものとして続くのですか?
田村 プロパガンダ演劇は毛沢東時代の産物で、1976年に毛沢東が亡くなると、中国は「改革開放」という経済優先の路線を取っていきました。すると次第に忘れられていくのですが、作品数が結構多いのと、1960年代から70年代の中国の演劇人たちは、ほぼそれしかつくることができなかったので、ものすごい才能がそこに結集していて名作も多い。ですので、今でも建国記念日などのタイミングで上演されますし、現在の若い俳優も、現代京劇の練習をすることがあります。また、60年代、70年代の頃に若者だった世代の人たちが、懐メロ的な感覚で今でも楽しむことがあると思います。
 革命現代京劇『紅灯記』(革命現代京劇『紅灯記』外文出版社、1972より)
革命現代京劇『紅灯記』(革命現代京劇『紅灯記』外文出版社、1972より)西村 すると、プロパガンダ芸術としての演劇は、1940年代後半ぐらいから80年代ぐらいまで続いたのでしょうか。
田村 そう考えていいと思います。
西村 プロパガンダ芸術というのは、中国に限らないと思いますが、他にどういった国でどういったものがあるのでしょうか。
田村 中国以外では、社会主義圏に多いのではないかと思います。社会主義圏同士は横の芸術交流を非常に盛んにおこなっているので、中国も元はソ連に学んで重視し始めた経緯があります。他には、ベトナムや北朝鮮。こうした国では今でも現役で、盛んにプロパガンダ芸術がつくられているのではないでしょうか。
西村 例えばロシアでは、バレエですか?
田村 そうです。私が今一番おもしろいと思っているのは、プロパガンダ芸術の中でも革命現代バレエというバレエです。中国では現代京劇がつくられたのと同時期、毛沢東の時代に、現代バレエもつくっていました。ソ連から入ってきたバレエという芸術様式を、まず中国人の身体に合うようにつくり変えて、さらに中国共産党の宣伝をのせる。すごく変わった作品がたくさんつくられていて、今観てもおもしろいです。この原型はソ連にあるのですが、ソ連では衣装を軍服にしてはいません。
西村 中国の革命現代バレエは、衣装が軍服なんですね。
 革命現代バレエ『紅色娘子軍』(張雅心編『様板戯劇照 張雅心撮影作品』人民美術出版社、2009より)
革命現代バレエ『紅色娘子軍』(張雅心編『様板戯劇照 張雅心撮影作品』人民美術出版社、2009より)田村 はい、軍服の女性兵士が踊ります。これが中国からベトナムにも伝わって、ベトナムや北朝鮮にも似たような作品があります。
西村 全くイメージがつきません。
田村 一見すると奇妙なものに見えるかもしれませんが、当時のバレエダンサーの技術がものすごく高い。クラシックバレエのダンサーに京劇の演技術を訓練させて、京劇とバレエが融合したような作品になっています。当時踊っていた方の回想録を読むと、「クラシックバレエダンサーとしての身体の使い方と逆の動きが、京劇では要求される。このやり方がうまくいくはずがない、とわかっていたが、反論する人はだれもいなかった」と書かれていて。おそらく、現代のクラシックバレエのダンサーでは踊れないのではないかと思います。
西村 完全に新しいものになっているようで、おもしろい。
田村 ソ連は、あくまでもバレエの様式を崩さずに、その中で中国の社会主義革命の成功を描くような作品をつくっていました。それを見た中国の人たちが、「もっと中国人の手で中国式のバレエがつくれるはずだ」と思って、こういうものをつくったようですね。
西村 中国という国の、文化を取り込む力のすごさを感じますね。
田村 そうですね、発想としては奇妙に思われるかもしれませんが、作品を観ると名作が多く、授業で大学生に見せても、ハマる人がいます。
西村 社会を表すものとしての演劇と、もはや社会をつくり出すものとしての演劇。演劇の力を裏表逆に使っているみたいにも見えます。
田村 中国に限らず社会主義国のプロパガンダ芸術では、現実をリアルに描いてはいけないんです。現実では社会主義革命は成功していないので、描かれるのは近い将来に成功するであろうちょっと斜め上の、ユートピア的なあるべき未来。それを舞台や文学の中に描き出さないといけない。
西村 すごいおもしろいですし、さっきの京劇とのコントラストもすごいですね。20世紀初頭の京劇は、社会の状況を反映しながらどんどん変わっていく。それに対して、ある意味社会を反映しない京劇というジャンルが現代京劇として出てくる。それが今またちょっと崩れて、混ざっていると思うのですが。今は、社会を表すような演劇が出てきているんですか?
田村 中国の演劇人の仕事は、少し特殊です。所属劇団は、基本的に国公立なんですね。中には民間でやっている方もいますが、大きい作品をつくろうとするとお金がかかるので、公の支援を得た方がつくりやすい。そうすると国の言うことを聞かないといけないので、仕事として淡々と政府のプロパガンダ作品をつくるのですが、一方で、例えば海外から資金を得ていたり、あるいは、国内の民間企業から資金を得ている場合は自分の芸術的情熱を込めたものをつくる。同じ方が、全然違うタイプの作品をつくっていたりすることは結構ありますね。
西村 やはり劇作家の方は表現したいものがあって、チャンスがあれば出すし、仕事としてはやるべき仕事もあるという感じでしょうか。
田村 そういう方が多いと思いますね。中国って、基本的に世に出る芸術作品のすべてが検閲を受ける社会体制なので。フリーランスで好きな作品を発表して、それだけで生きていくことは非常に難しい社会構造なんです。
西村 今の中国の劇作家の方の、心象風景を見たいですね。劇作家だけではなくて、俳優の方々もそこには一緒にいると思いますが、葛藤が渦巻いてそうです。そうでもないのでしょうか?
田村 現地の方たちは、淡々とされています。例えば、上演するはずだった演劇が初日でいきなり上演禁止になったりすることも珍しくない。しかもなぜなのか理由は知らされず、よくわからない理由で検閲に引っかかる。私は日本社会で生きているので、最初は衝撃を受けました。中国の演劇人は「まあしょうがないね。次行こう」という感じで淡々としているように見えます。でも彼らが言うのは、「こういうことが繰り返されると、自分の中で自己検閲が働いてしまう。ひるんで自己検閲を始めたら終わりだ」と言いますね。みんな芯が強いなと思います。
西村 葛藤があるというよりも、演劇が社会にちゃんと定着していて、それが仕事として成立しているんですね。社会の方を映す像としての演劇、そしてそれをコミュニケーションのツールとしての演劇として置き換えた時にすごくパワフルさを感じました。
インタビューを終えて
文字や宗教など、日本が多くを学んだ中国。今回のインタビューで最も違いを感じたのは古典芸術に対する態度です。現代の日本では古典は踏襲し守るものという風潮が強く、そこから新しく何かを生み出すという姿勢には慎重になります。一方、中国では「守・破・離」の「離」が評価される。この新しいものを生み出すダイナミズムには、私たちも見習うことがあると感じました。
(ライター:ヘメンディンガー綾 インタビュアー:西村勇哉 編集者:増村江利子)
この記事は、本学と連携し、株式会社エッセンスが制作しています。
https://esse-sense.com/articles/132