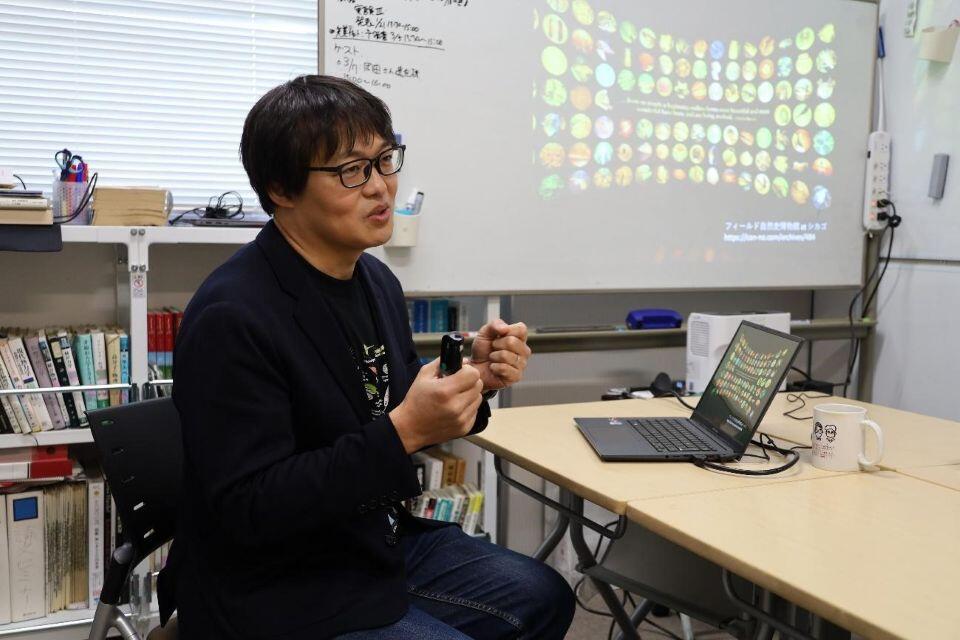<写真>電子科学研究所 越後谷駿 特任助教(撮影:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香)
顕微鏡を覗けば、地球上のあらゆる環境に微生物を見つけることができます。そのなかにはゾウリムシやミドリムシに代表される原生生物と呼ばれる単細胞生物が含まれています。電子科学研究所の中垣研究室では、物理や数理の手法を用いて原生生物の巧みな行動機構の研究に取り組んでいます。今回は、中垣研究室の3名の研究者にお話しを伺いました。
――今、どんな研究をしていますか?
越後谷 私は、ソライロラッパムシという、淡水にすむ大きさ1ミリほどの小さな生き物の研究をしています。原生生物の中では大きい方で、肉眼だと点や細長い針のように見えます。石などに固着する時は針のようなラッパ状の形態で、遊泳する時はコーン状の形態(円錐形)になります。この違いが肉眼で見た時の形態の違いに結び付いています。また、ソライロラッパムシは名前の通り青色っぽく、光の当たり方によって青緑色っぽく美しい透き通った体をもち、水の中を漂っています。私は、ソライロラッパムシの「行動変化」と「生息場所の選択」という2つをメインに研究してきました。
 空色が美しいソライロラッパムシ ※1(提供:越後谷駿 特任助教)
空色が美しいソライロラッパムシ ※1(提供:越後谷駿 特任助教)――とても小さな生き物ですが、どうやって泳ぐのですか。
越後谷 ソライロラッパムシは繊毛虫に分類されていて、ぬいぐるみの毛のような「繊毛」と呼ばれる細い毛に覆われています。繊毛を一生懸命に動かして水をかき、水流を起こすことで泳ぎます。さらには、その繊毛で口に向かって水流を起こすことで、周囲にいるバクテリアを捕食できます。繊毛を巧みに使って泳いだり食事をしたりして、活発な動きや行動変化をするのがソライロラッパムシの面白いところです。
 ソライロラッパムシの3つの形態変化。ソライロラッパムシは遊泳や逃避、固着など行動に応じて、自身の形態を変化させる。※2(提供:越後谷駿 特任助教)
ソライロラッパムシの3つの形態変化。ソライロラッパムシは遊泳や逃避、固着など行動に応じて、自身の形態を変化させる。※2(提供:越後谷駿 特任助教)――小さい体で工夫しながら活動しているのですね。
越後谷 もし光や波など外部からの影響を気にせずランダムに固着していたら、ソライロラッパムシは数億年という長い時の流れを生きられなかったでしょう。彼らは環境の変化に応じ、自身が生存できる環境を選んできたはずです。そこで、どういう環境で行動が変化するのかに興味を持ちました。
――どのような環境で動きが変わるのですか?
越後谷 ソライロラッパムシは「光から逃げる」とか、「特定の化学物質に寄っていく」という性質もあるのですが、私が着目したのは、周囲の形によって、固着場所をどう選択しているかについてです。ソライロラッパムシは、私たち人間のような「目」を持っていません。にもかかわらず、彼らは周囲の形に応じて固着場所を変えることを発見しました。凹凸のある特殊な容器で飼育すると、ソライロラッパムシは1番目、もしくは2番目に狭いところに固着します。この研究は、2023年度に博士課程を修了するまでの5年間をかけて、紆余曲折もありながら、わかったことです。
 容器のすみっこに集まっているソライロラッパムシ。丸い容器の内側に作られた突起の溝部分(左端)に固着していることがわかる。※3(提供:越後谷駿 特任助教)
容器のすみっこに集まっているソライロラッパムシ。丸い容器の内側に作られた突起の溝部分(左端)に固着していることがわかる。※3(提供:越後谷駿 特任助教)――なぜそのことに気づいたのでしょうか。
越後谷 容器の中でソライロラッパムシの培養をしていて、餌となる麦粒を入れておくと、ソライロラッパムシがどこにも見当たらなくなりました。どこに行ってしまったのかとよくよく探してみると、麦粒と容器の底との間にびっしりとソライロラッパムシが隠れていたのを発見しました。そこで、この現象は化学物質によって引き起こされるのか、光の有無によって引き起こされるのかと疑問に思いました。研究を進めていくと、化学物質や光といった要因によるものではなく、周囲の形に応じて固着場所を選んでいることがようやくわかりました。容器の中で「すみっこ」の狭い場所に行くと、ラッパ状の形態になり、固着するのです。
 すみっこに固着するソライロラッパムシ。養分となる麦粒のくぼみに密集して固着している。スケールバーは1 mm。※1(提供:越後谷駿 特任助教)
すみっこに固着するソライロラッパムシ。養分となる麦粒のくぼみに密集して固着している。スケールバーは1 mm。※1(提供:越後谷駿 特任助教)――どうして「すみっこ」を選ぶのでしょうか?
越後谷 外敵から身を守ったり、表面張力で最後まで水が蒸発しにくいような溝で、たまった水を利用したりするためだと考えられます。すみっこをうまく使って、生き延びているんですね。
 形状を変化させた容器の設計図。様々な形状の容器で、ソライロラッパムシが固着する時の形態変化を観察している。※3(提供:越後谷駿 特任助教)
形状を変化させた容器の設計図。様々な形状の容器で、ソライロラッパムシが固着する時の形態変化を観察している。※3(提供:越後谷駿 特任助教)――どうやって「すみっこ」を選ぶのでしょうか?
越後谷 ソライロラッパムシがすみっこに固着する方法について、正直なところはっきりとはわかっていませんが、泳いでいる状態からすみっこを選ぶまでに行動プロセスがあることが分かりました。ラッパムシは通常、まっすぐ泳ぎ、構造物にぶつかると進路を変えてまた泳ぎ始めます。一方、固着前のラッパムシは構造物の表面に沿って移動しており、探索モードを切り替えていることが分かりました。すみっこは構造物によって形成されているので、壁に伝って移動していけば早くすみっこにたどり着けるというわけです。
この探索モードの切り替えがどのような要因で起こるかは、まだ明らかではありません。ラッパムシごとの個体差や固着プロセスに複雑な多様性があるからです。単細胞生物といっても、結構繊細で複雑なんです。ただこの探索モードの切り替えは、すみっこが含まれている複雑な観察容器でよく観察される行動変化でした。そのため、構造物との接触頻度の増加など、構造物との何らかの相互作用が関わっているのではないかと考えています。現在は、何によって探索モードを切り替えているのかという仮説を確かめています。
――学部時代は物理学を専攻されていたと伺いました。そこから、どうしてソライロラッパムシの研究をすることになったのですか。
越後谷 たまたま理学部の廊下で、光に応じて、法則性をもって、特徴的なパターン行動をする原生生物の話を聞き、原生生物の行動に興味をもったのが現在の研究を始めたきっかけです。ソライロラッパムシを初めて見たときは、その青くて美しい姿に感動し、自分で培養してみたいと強く思いました。
――最後に、ソライロラッパムシは越後谷さんにとって、どのような存在ですか?
越後谷 ソライロラッパムシはこちらが意図していないこともたくさんしてくるので、結果を考察するのはなかなか大変です。しかし、そうやって何度も振り回されるたびに、思い入れや愛が生まれてくるので、観察することがとても楽しみになっていきます。
 物理エソロジー研究室の先生方。右端が越後谷さん(撮影:齋藤有香)
物理エソロジー研究室の先生方。右端が越後谷さん(撮影:齋藤有香) 【文:国際感染症学院博士後期課程1年(サイエンス・ライティング・インターン)坪智也(取材当時)
写真:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香】